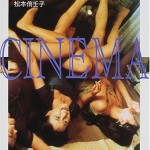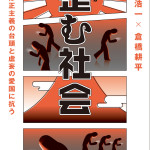⑪ 柴田錬三郎『江戸群盗伝』と山田風太郎『風眼抄』
小田光雄
六興出版社に関して、もう一編書いておきたい。
六興出版社は『風雪』や『小説公園』といった文芸雑誌とともに、多くの小説、文学書などを刊行している。その一端は前回も示しておいたが、全出版目録が編まれていないために、それらの全貌を把握することが困難である。
最近も古本屋で柴田錬三郎の『江戸群盗伝』を入手している。これは「新・時代小説選集」と銘打たれているので、シリーズとしての刊行だと思われるが、何冊出たのかはわからない。1958年刊行で、定価は360円、発行者は吉川英治の実弟吉川晋、発行所はまだ六興出版部のままだ。しかも装幀は後に三浦綾子の『氷点』の挿絵を担う福田豊四郎による箱入で、異色の「解説」は翌年に『ちゃんばら芸術史』(実業之日本社)を著わす大井広介である。私が60年代半ばに読んだのは新潮文庫版だったから、これがその前版ということになるのだろうか。そこには『続江戸群盗伝』も収録されていて、それも新潮文庫になっていたからだ。
この『江戸群盗伝』を読み返していると、最初に読んだ時に、物語トリックが、今はそのタイトルが浮かんでこないのだけれど、小学生時代に愛読していたポプラ社の「怪盗ルパン」シリーズの一冊と同じだと連想したことを思い出した。また「新・時代小説選集」のような出版があったことで、後の山田風太郎の『風眼抄』の刊行へとつながっていったのではないかと考えたりもした。
風太郎の初めてのエッセイ集ともいえる『風眼抄』は1979年に六興出版から出されている。これは四六判より一回り小さい判型で、発行者は賀來壽一とあり、社名も経営者もすでに代わってしまったことを伝えていよう。しかし時代小説を出版していた時代の編集者はまだ残っていて、それがこの一冊へと結実していったのではないだろうか。
私はかつて拙稿「江戸時代の書店」(『書店の近代』所収、平凡社新書)において、山田風太郎の『八犬伝』(朝日文庫)と柴田錬三郎の『江戸群盗伝』(集英社文庫)などを並べて言及している。それもあって、六興出版社=六興出版の柴田や山田の編集者が同じであればと夢想したことにもよっているのだが、私のような読者のつながりから考えても、そうした編集者の存在を想定することも許されるであろう。
私見によれば、この大津絵を配した田村義也による装幀の『風眼抄』は風太郎にとっても、読者にとっても、また近代エッセイ史においても、画期的な一冊だった。この五十編ほどのエッセイ集はまさに風太郎の人柄とその物語の出自をも伝えるもので、この一冊を触媒として、彼の『警視庁草紙』に始まる「明治開花物」は新たな照明と評価を得ることになったと思われる。
夏目漱石の『硝子戸の中』や『思い出すことなど』を彷彿させるそれらのエッセイは、いずれも感銘を与えてくれるが、冒頭の「わが家は幻の中」という一編こそは、『風眼抄』のみならず、風太郎の核心といえるので、それを紹介してみる。そこでは風太郎の「大した歴史」ではないとの断わりをふった「わが家の歴史」が述べられている。それは父も母も幼少時に亡くなった風太郎の遠いきれぎれの記憶であり、若かった父と母だけでなく、雑誌や本、大神楽の獅子舞い、大演習の兵隊たち、大地震のことなどが「生家略図」とともに語られていく。そして「私の人生のうちでも、いつも春の日が照っているような気がする、一番愉しく、なつかしい想い出」に関しても。
(……)近くのれんげ畑で子犬といっしょに転がりまわっていたことや、五月の節句に幟を立ててもらって、酔うような白い初夏の光の中で、その柱が、ギイ、ギイ、とものうく鳴るのを聴いていたことや、また庭の桜の下にむしろを敷いてもらって、そこでひとりで遊んでいて、「ああ幸福だ!」と、心の底から感じたことや——それは、それ以後、一見どんな幸福な状態にあっても、いちども心の底からそんな感じをいだいたことがないから、ふしぎにそのことを記憶しているのである。
ただ風太郎のことだから、これが単なる「なつかしい想い出」だけで終わるわけではない。そうして彼は次のように考えるのである。
もし人間が、文字通りどんなことでもやれる、という空想的な独裁者になったとしたら、そのやりたいことの一つに、自分が子どものころの世の中を再現させる、ということがありはしないか。だから、いまもしある地方のある町を、タイムトラベル的にすべて昭和初年の風景、服装、行事で復活させたら、五十男はみんな涙をながしながら馳せ集まるのではないか——ついでにこの着想はさらに飛躍するのだが、それはただ空想ではなく、現実に、ひょっとしたらあの毛沢東は、同じ心理で中国の歩みをとめてしまったのではあるまいか。
風太郎は毛沢東の名前を挙げているが、この着想は73年のジョージ・ルーカスによる「ある地方のある町」を舞台とした映画『アメリカン・グラフィティ』でも試みられていた。この映画を評して、論創社から『サルトル』も出されているフレデリック・ジェイムソンはノスタルジアこそが後期資本主義の商品に他ならないと述べている。それが日本においても90年代以後、顕著になっていったことはいうまでもないし、21世紀を迎えて、ノスタルジアという商品はさらに広範に拡がっていったと見るべきだろう。
それゆえに風太郎の「わが家は幻の中」というエッセイは、来たるべき時代を予見していたのかもしれない。彼がこのエッセイを書いたのは『風眼抄』刊行と同年の79年で、これが最も新しいものであるから、同書を企画した編集者にしても、これを読んだことがきっかけになったと考えらえれる。その「あとがき」で、この一冊が「私という人間のすべてが、散乱したかたちながら、まんべんなく浮かび出すようになっている」とし、それは「編集の方で、そうなるように配慮されたに相違ない」と記していることはそれを裏づけていよう。風太郎の「あとがき」に「編集の方」の名前が記されなかったのも、その「配慮」があったからだろうし、本当に編集者は誰だったのだろうか。
なお、これを書いた後、賀來が吉川英治の女婿で、元講談社の編集者にして考古学者であることを知った。それで六興出版の後期の単行本の由来を納得した次第だ。
—(第11回、2017年1月15日予定)—
バックナンバーはこちら➡︎『本を読む』
《筆者ブログはこちら》➡️http://d.hatena.ne.jp/OdaMitsuo/