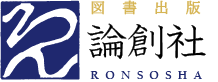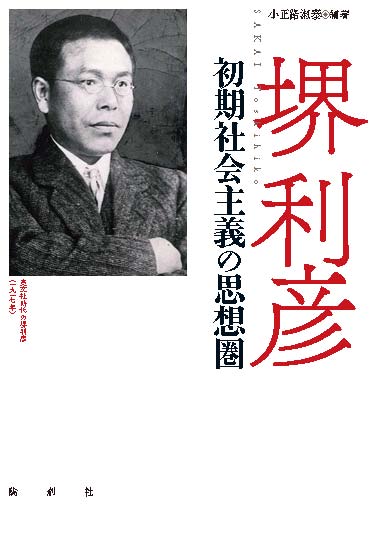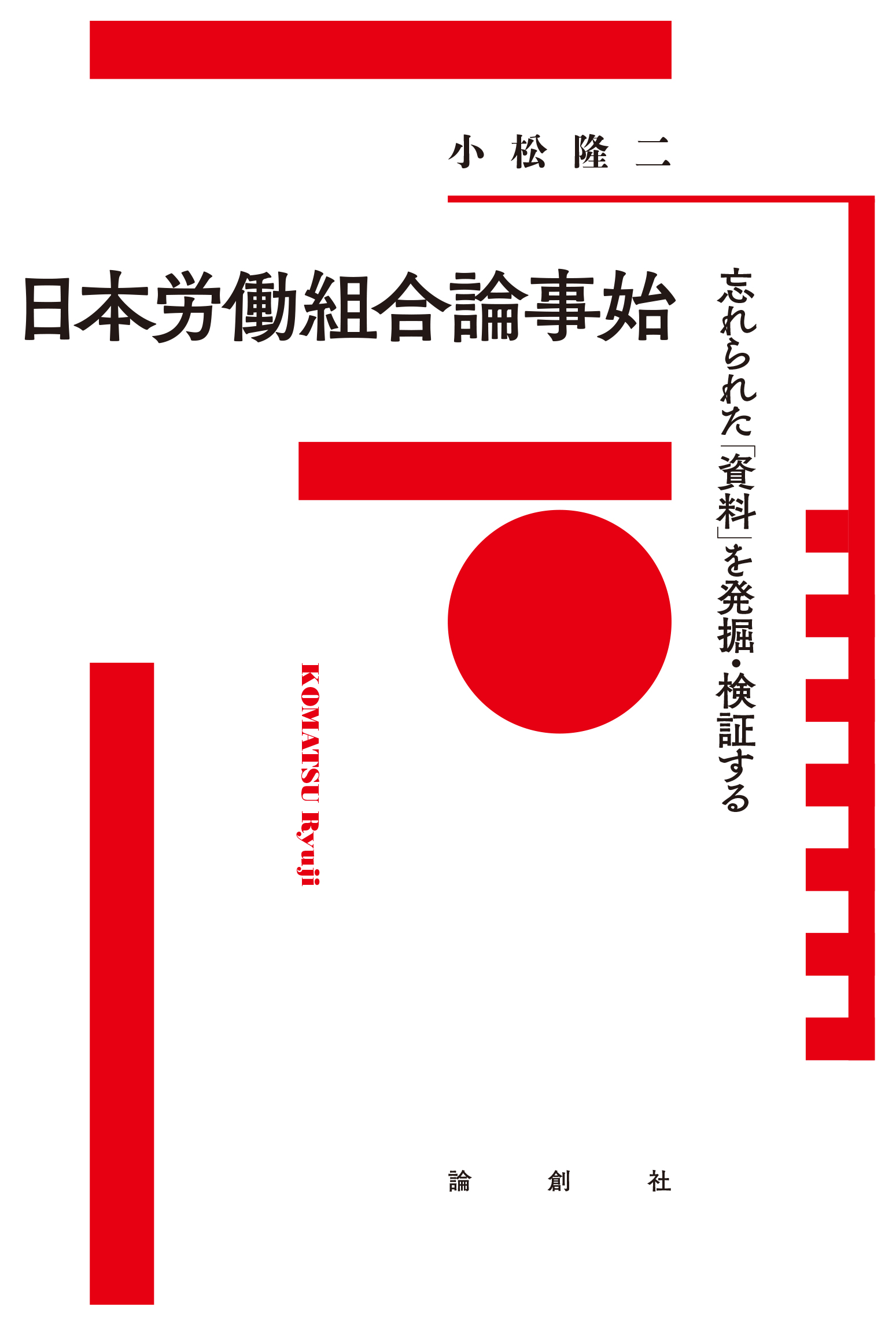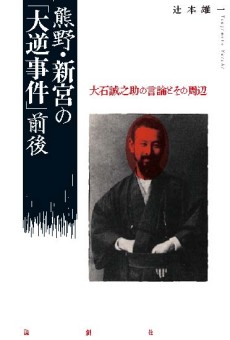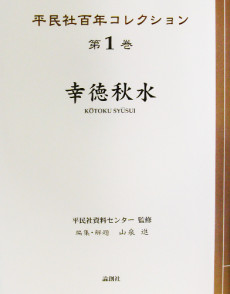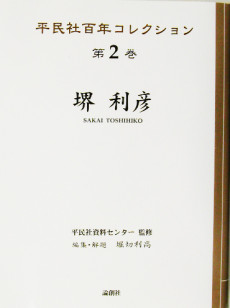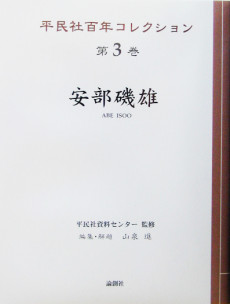- 2019-6-4
- お知らせ, 論創通信, 矢口英佑のナナメ読み
No.11『幸徳・大石ら冤罪に死す―文学・政治の〈呪縛〉を剥ぐ』
矢口英佑〈2019.6.4〉
最近、私が目にした書籍には珍しいのだが、本書には著者の怨み、怒りがマグマのように渦巻き、熱い思いとなって文中のそこかしこから噴出しているように見える。私にはそのストレートさが、著者の資料対象に注がれる緻密な視点と分析から表出されているだけに、ついつい引き込まれて、思わず〝にやり〟としてしまう箇所が一つや二つではなかった。
幸徳とは幸徳秋水であり、大石とは大石誠之助であり、冤罪とは大逆事件を指していることは言うまでもない。
そもそも著者には、次のような、やりきれない、持って行き場のない怒り、抗議の意識が強い。本書の「まえがき」をそのまま引用してみよう。
明治四三年(一九一〇)五月末から翌年正月にかけ、二六名もの人びとを拘束し、取調べ、公判を行い(皇族事案として大審院で一審だけで終審)、そのすべてをわずか七か月間で仕上げ、二四名に死刑判決(翌日に半数は恩赦で無期に)、その一週間後に一二名の執行――という凄まじいものだった。ことは条件付きながら明治憲法二九条でも保証された言論・表現・集会の自由内のことであり、その権利の蹂躙(大部分が公判で初顔合わせした活動的な市民)、しかも全員「……加えようとした」という未遂事案である。司法が一貫して首相・桂太郎(第二次)、及び背後に見え隠れする元老・山県有朋ら政治の僕であり、司法と政治が創り出したフレームアップ(捏造)の冤罪、つまり国家権力犯罪事件であった。
著者にはこの「国家権力犯罪事件」が、現在、日本で「大逆事件」と呼ばれ、歴史用語として定着してしまっていることに強い反発、異議申し立てがある。なぜなら、〝大逆〟などと名づけられるほど、著者の言葉にならえば〝どこかおぞましい響き〟を持った罪など「被告」たちは犯していないからである。
ただし著者が問題とするのはその点ではない。つまり、国家権力によって事件を捏造し、二四名もの人間に「大逆」の名をかぶせ、死刑判決を出し、そのうち一二名を判決からわずか一週間後には処刑してしまったからである。そのことこそ大きな問題なのである。
しかも、この〝大逆〟という言葉は、裁く側が持ち出し、判決文に組み込んだことに始まっているのである。裁く側のセンセーショナルな官製語に新聞社が飛びつき、大々的に使い始め、一気に広まり定着してしまったのだった。
だからこそ著者は、判決文に「大逆罪」の言葉を公式に登場させたのには、「法の論理を超えた情緒的(あるいは扇情的)飛躍がある、と断じるのである。なぜこのような事件が起きた(でっち上げられた)のか、当然、著者の深い洞察力に基づいた分析を示していくのが本書の目的にほかならない。
本書はこの国家権力による捏造事件を取り上げているのだが、その目次を見ると、
第一章 『田園の憂鬱』への道程
第二章 創造された「大逆事件」
第三章 異国で「大逆」――閔妃暗殺事件
第四章 山県における権力の用法
第五章 秀吉に擬した築邸三昧
第六章 大正という世相の下で…
第七章 明治一五〇年から顧みる同一〇〇年
とあるように、「大逆事件」の「被告」たちに割かれた紙数はそれほど多くない。むしろ、この事件の周辺から、真相に迫ろうとしているのがわかる。
たとえば、第三章では「大逆事件」の15年前に起きた朝鮮王朝第26代・高宗の王后だった閔妃殺害事件が取り上げられている。彼女が日本の朝鮮半島での影響力を排除しようとしていたがゆえの、これも国家権力による仕組まれた暴挙だった。
この事件と「大逆事件」とは、何も関わりがないような意外性を読み手に与えそうだが、文芸、特に与謝野鉄幹への関心が強い著者だったからこそ、持ち得た視点だったろう。
「幸徳秋水らへの予審調書で「宮城に迫る」や「二重橋に迫る」という表現が繰り返され、判決文にもいわば決めの言葉として登場」している点への着目が「司法エリートたちには何か具体的なイメージがあった」となり、「画策し「爆裂弾」の小説も」と第三章の第二節の題目につながっていくのである。
ここでの「画策」とは、与謝野鉄幹が終生、この閔妃事件を画策したとして誇り続けたからであり、「爆裂弾」とは、朝鮮の政府高官を爆裂弾で襲おうとする「小刺客」という小説を書いていたからである。
また第一章が「『田園の憂鬱』への道程」となっていることも、著者の文芸的関心の強さを示している。この小説が取り上げられたのは、佐藤春夫は父親の友人だった大石誠之助を幼いときから知っていたこと、『田園の憂鬱』に大石誠之助の刑死が影響していることなどがあったからだろうが、この第一章だけで十分に佐藤春夫論として通用すると思われる。
第四、第五章は山県有朋に関わる記述に占められている。なぜなら、若き日、高杉晋作の奇兵隊に入った下級武士の子・山県有朋はやがて、明治政府では日本陸軍の基礎を築き、官僚制度を確立し、文官試験制度を創設し、政官界の大御所として隠然たる影響力を持ちつづけたのだが、この山県有朋こそ、「大逆事件」という国家権力による犯罪事件を起こさせた張本人と見なしているからである。
しかも著者の山県有朋の人間分析の視点はなかなか興味深い。これは山県に限らず、著者は「冤罪であるのを承知の上で犠牲者を造り出していった者たちを調べていくとき、どうしてもその者の人間性に踏み込まざるを得なくなる」からだと言う。
そして、人間性はプライベートな面によく表れるとして、豊臣秀吉が城造りに凝ったように山県も大邸宅造りに入れ込んだ様子が実に詳細に記述されていく。第五章だけで8枚ほどの地図や見取り図が挿入されていて、土地勘のある私などには、これらを見ているだけで、権力者の権力がとんでもなく絶大であったことを思い知らされる。
「決死の士数十人を募って、富豪の財産を奪い、貧民を繰り出させ、諸官庁を焼き討ちし、高官連を殺して、その上で二重橋に迫って(天皇を殺す)大逆罪をなす」というストーリーを作り上げ、「全国各地から26人の被疑者(公判廷で初めて顔を合わせた者が大部分)が摘発され、役を振り分け」ることなど、どうということもなかっただろう、と変な納得をしてしまうほどである。
これほどの権力者がなぜ国家権力犯罪事件を起こしたのか。著者の言葉によれば、山県は「凶暴なる社会主義者」を恐れたのではなく、主義理想からで、資産を持ち、正業についている「市民」という存在、彼らは「厚く広く厖大な層に成長し得る」そのことを恐れたのだと言う。「秘めたる英国賛仰者であった青年期以来」の山県のコンプレックスが「個人自主本位の道徳観念」を敵対的存在と認識していたからだと言う。
自己の絶対化と絶対者(天皇)の絶対化への不安と恐怖、これこそが山県を「大逆事件」に導いたものだったとする著者の結論は、山県自身の言葉から紡ぎだしているだけに重さを増している。
バックナンバー→矢口英佑のナナメ読み
〈次回、2019.6.10予定『古本屋散策』〉
『幸徳・大石ら冤罪に死す』 四六判上製320頁 定価:本体3,000円+税
——————《「大逆事件」関連本》——————