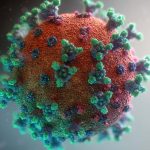② 時代小説と挿絵
小田光雄(2016.3.15)
中里介山の『大菩薩峠』を読み始めたのも一九六〇年代で、それは角川文庫版だった。
ちなみに『角川書店図書目録(昭和20-50年)』に目を通してみると、角川文庫版『大菩薩峠』は一九五五年七月に第一、二巻が出され、以後は毎月続刊で、翌年のやはり七月に第二十七巻が刊行となり、ほぼ一年で完結したとわかる。おそらく当時『大菩薩峠』を全巻揃いで読むことができたのはこの角川文庫版だけだったかもしれない。それにこの時代の文庫は定番化でもあり、ロングセラー化していたことから、私も六〇年代半ばに読むようになったと思われる。ただ町の書店には見当たらず、隣の市の大きな書店で一冊ずつ買い、何ヵ月もかけて読んでいったのだが、第二十巻ほどで挫折してしまい、残念ながら現在に至るまで、最後まで読み通していない。
まだ文庫にほとんどカバーがかかっていなかった時代なので、それにはグラシン紙と「現代日本文学」分類を示す緑帯が巻かれていただけだった。しかし長い巻数ゆえもあってか、文庫としてはめずらしく、挿絵入りだった。これは今になって考えれば、活字だけで終始することを危惧した事情もあろうが、それよりも『大菩薩峠』の新聞連載の挿絵入り原型、及び同様の戦前の春秋社版を考慮したことに起因しているのだろう。
後に気紛れに古本屋の均一台で何冊かを再購入したことを思い出し、それらを探してみたら、第四、五、六巻が出てきた。挿絵を見てみると、巻によって異なり、第四巻は正宗得三郎、第五巻は野口昂明、第六巻は光安浩行で、各巻に六、七枚の掲載があった。一ページを占めるようなものではなく、三分の一ほどの小さな挿絵だが、それを目にして、かつて主人公の机龍之助ばかりでなく、間の山の芸人のお玉=お君や宇治山田の米友のイメージを確認しながら読み進めていったことも思い出された。そしてお君が歌う間の山節を覚えてしまったことも。この歌に関しては「三省堂と『図解現代百科辞典』」(『古本探究』所収)でもふれたが、それは次のような歌である。
夕べあしたの鐘の声
寂滅為楽と響けども
聞いて驚く人もなし
花は散りても春は咲く
鳥は古巣に帰れども
行きて帰らぬ死出の旅
私はまだとても若く、少年だったのに、時代もまた高度成長期だったのに、『大菩薩峠』のような物語とこのような歌に引き寄せられていったことになる。
角川文庫版のすべての挿絵家を確認できないけれど、おそらく全巻にわたって挿絵があったはずで、龍之助が信州の白骨温泉に滞在しているシーンも描かれ、それで白骨温泉という奇妙な地名を覚えたこと、ぜひ一度行ってみたいと夢想したことも、記憶の中から浮かんできた。もっとも白骨温泉行きが実現したのは、それから四十年近く経ってのことであったが。
この当時、100円から130円の定価だった角川文庫版は目次裏の注記によれば、挿絵家とともに、編輯顧問として白井喬二、中里幸作の名前が挙げられている。前者はいうまでもないが、後者は「中里」の奥付検印を押している介山の実弟の著作権継承者であり、まだこの時代までは介山の血縁も健在で、文庫ですらも検印が必要とされていたことを教えてくれる。それに加え、編輯として南波武男と笹本寅の名前が記されている。これは笹本が前述の春秋社版の編集者だったことから、角川文庫版の企画編集、全巻解説に携わったという経緯と事情を問わず語りで伝えているし、同じく南波もその関係者だと推測される。
この角川文庫版は一九八〇年代を迎えて、角川書店の子会社富士見書房の「時代小説文庫」として、装いも新たにカラー表紙がかかり、合本復刊されるのだが、それにはもはや挿絵も編集にまつわる注も省かれ、同じ文庫でも別の印象を与えるものとなってしまったのである。それゆえに同じ『大菩薩峠』ではあっても、まさに異版のような感触をもたらし、物語もまた最初に読んだ版によってイメージも確立されると実感したことを思い出す。
ここまでくれば、当然のことながら、論創社が二〇一四年から一五年にかけて刊行した『大菩薩峠[都新聞版]』全九巻に言及しなければならない。この論創社版は、従来の『大菩薩峠』の単行本が中里介山による三〇%の削除を施したものであるという校訂者伊東祐吏の発見に基づき、初出の『都新聞』連載に、井川洗涯の挿絵をそのまま付しての出版である。
私も以前に「同じく出版者としての中里介山」(『古本探究Ⅱ』所収)を書き、その『都新聞』の記念すべき書き出しが単行本と異なることを指摘し、それを引用しておいた。だがまさかその連載分に三〇%の削除があるとは想像もしておらず、今回の論創社版の刊行によってようやくそれを知ったことになる。
ただ最初の単行本である玉流堂版は、介山自身が編集や印刷などすべて手がけているので、その削除がどうして生じたのかはわかるように思われた。またそれだけでなく、連載時の挿絵もそのまま収録されたことで、私たちは大正時代の読者と同じように『大菩薩峠』を読むという体験が可能になったのだ。春秋社版を企画した木村毅の回想によれば、『都新聞』連載時には多くの女性読者がいたとされ、玉流堂版に関しても、読み巧者である菊池寛や直木三十五の絶賛を受けていたという。そして春秋社の円本普及版としての『大菩薩峠』が出されたことで、新しい時代小説、大衆文学として多くの読者を獲得していったのであろう。
なお先述したお玉=お君の姿と間の山節の歌は『大菩薩峠[都新聞版]』第三巻の233ページに出てきている。それを見て、もし最初にこの論創社版を読んだならば、物語としても登場人物のイメージにしても、やはり角川文庫体験とは大きく異なっていたように思われる。
またこの拙文と関連するのだが、たまたま『日本古書通信』(三月号)の連載「古本屋散策」168の「昭和三十年代の新潮社の時代小説」でも、十点ばかりの装丁と挿絵について言及しているので、興味のある読者は参照されたい。
それと同様に、「出版人に聞く」シリーズ12『「奇譚クラブ」から「裏窓」へ』においても、飯田豊一がアブノーマル雑誌における挿絵の重要性について語っていたことにもふれて頂ければと思う。日本の近代出版史や文学史にあって、挿絵の問題はとても重要で、日本の出版のオリジナルな分野のコミックの誕生も、挿絵をその揺籃の地としているように見える。本連載でも少しずつそのことをたどってみたい。
—(第3回 2016.4.15予定)—
バックナンバーはこちら➡︎『本を読む』
《筆者ブログはこちら》➡️http://d.hatena.ne.jp/OdaMitsuo/