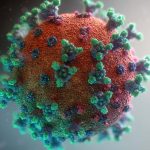⑭〈矢牧一宏と七曜社〉
小田光雄
これも「出版人に聞く」シリーズ〈10〉の内藤三津子『薔薇十字社とその軌跡』の補遺として、何編か書いてみる。
本多正一編『幻影城の時代 完全版』(講談社)に、内藤が「薔薇十字社と島崎さん」という一文を寄せている。彼女はそこで渡辺温の『アンドロキュノスの裔』や『大坪砂男全集』の編集に際し、探偵小説誌『幻影城』を創刊することになる島崎博の助力を得たこと、彼と『三島由紀夫書誌』を製作したこと、薔薇十字社の資金が潤沢で存続していれば、『幻影城』も出したかもしれないこと、手形で引き受けてくれる印刷所を紹介したことなどを語っている。
そうした意味で島崎も内藤の出版に寄り添った一人だが、本来の彼女のパートナーは矢牧一宏であった。彼は文芸書出版において、いくつもの出版社遍歴を重ね、刊行した本は300冊を超えるであろうし、私たちの記憶に残る何冊もの書物をもたらしている。その矢牧は出版社遍歴の果てに、1982年に亡くなり、「遺稿追悼集」として『脱毛の秋』(社会評論社)が刊行されている。そのタイトルは彼が19歳で発表した小説からとられ、それも含めた遺稿の他に、60余の人々が追悼文を寄せ、各人から見られた矢牧の軌跡が語られている。残念なことに年譜は収録されていないが、それらの追悼文の集成からは矢牧の出版人生といっていいほどの軌跡が浮かび上がってくるので、それらをたどってみたい。
矢牧は1946年創刊の文芸誌『世代』の同人で、先述の小説もそこに発表されている。『世代』同人は吉行淳之介やいいだももの他に、後に弁護士や経済学者となる大野正男、中村稔、日高晋を配し、矢牧の編集と著者人脈もこの時代に培われたし、これらの同人たちの出版代行人でもあったと考えられる。彼は旧制成蹊高校を中退し、『世代』編集に携わり、その発売元であった目黒書店から出版人生を始めている。だが『世代』は53年に終刊となる。
様々な追悼文をつなぎ合わせると、その後、矢牧はある教科書出版社や河出書房を経て、おそらく55年前後に七曜社を設立する。私はこの事実を『脱毛の秋』で初めて知ったのだが、確かに七曜社の本があるはずだと探してみると、河野典生の『憎悪のかたち』が出てきた。四六判上製のカバー装丁は小林泰彦によるもので、当時のミステリーの表紙としては垢抜けていたと思われる。奥付には刊行者として矢牧の名前が記載され、62年4月の出版であるから、七曜社がかなり長く存続していたとわかる。彼が七曜社以後に設立した出版社はそれよりも寿命が短かったからだ。それ以後の出版社とは天声出版、都市出版社、出帆社であり、これらについては断片的だとしても、他でも証言されているが、七曜社に関してはここでしか語られていないので、それをトレースしてみる。
七曜社時代について、『世代』の同人だった宇根元基と都留晃が追悼文の中で回想している。宇根元は矢牧の金策相手であり、都留は七曜社に参画していた。七曜社の出版物の全容は判明していないけれど、宇根元が記しているところによれば、岩崎呉夫『芸術餓鬼』、中村稔『定本宮沢賢治』、太田文平『寺田寅彦の作品と生涯』、立原えりか童話集『ちいさい妖精のちいさいギター』などが刊行されていたようだ。
そして矢牧は「こうした返本の山に囲まれて」いた。それゆえに「彼の発行者としての悩みも勿論お金のことばかりでした」と宇根元は書いている。資金繰りは融通手形を乱発していたらしく、宇根元もスポンサーとして資金を調達しただけでなく、手形割引や裏書にも応じていた。しかし最終的には高利の出版金融にも手を出してしまったようで、在庫はゾッキ本として流出してしまう。同様に追悼文を寄せている芳賀章は七曜社が倒産した時、在庫処理を引き受けたことから矢牧と知り合い、それがきっかけとなり、矢牧の企画編集による『田中英光全集』や『原民喜全集』を芳賀書店から出版したと述べている。二人の全集と芳賀書店のイメージはうまく重ならないでいたが、これで納得がいくのである。
また矢牧に誘われ、創立期の七曜社に加わった都留も次のように証言している。それによれば、当時の七曜社は当てこんで2万部も刷った経営理論の本が売れず、事務所は返本で埋まり、「水ものといわれる出版の難しさと資金力のない出版社の頼りなさ」が露出し、「自転車操業と借金の言い訳」の毎日だった。そのような中でも、矢牧に対する印刷屋や製本屋の信頼は厚く、しかも彼は「資金繰りの苦しさを楽しんでいるかのように見えた」という。
先の河野典生の『憎悪のかたち』に示された「ミステリー・シリーズ」は矢牧の企画で、都留が編集したが、資金不足のために中絶してしまったらしい。七曜社から始まる矢牧のあきれるほどの出版社設立と倒産を回顧し、安岡章太郎の「矢牧は最後の編集者、もう彼のような編集者はいない」との言を引きながら、都留は矢牧が「天性の編集者」であったことを認めつつも、当然のことながら出版社の経営者にふさわしくなかったと述べ、次のような言葉で追悼文を結んでいる。
今にして思えば、七曜社時代、経営者として、資金繰りの苦しさと取組み、その妙味を知ったばかりに、時に道を違えて出版社を経営しようと思い立つ誤りを犯したのではないだろうか。
だが矢牧にしてみれば、どのような資金繰りが待ちかまえていようとも、出版者として生きるしか他に道がなかったように思われる。
—(第15回、2017年4月15日予定)—
バックナンバーはこちら➡︎『本を読む』
《筆者ブログはこちら》➡️http://d.hatena.ne.jp/OdaMitsuo/