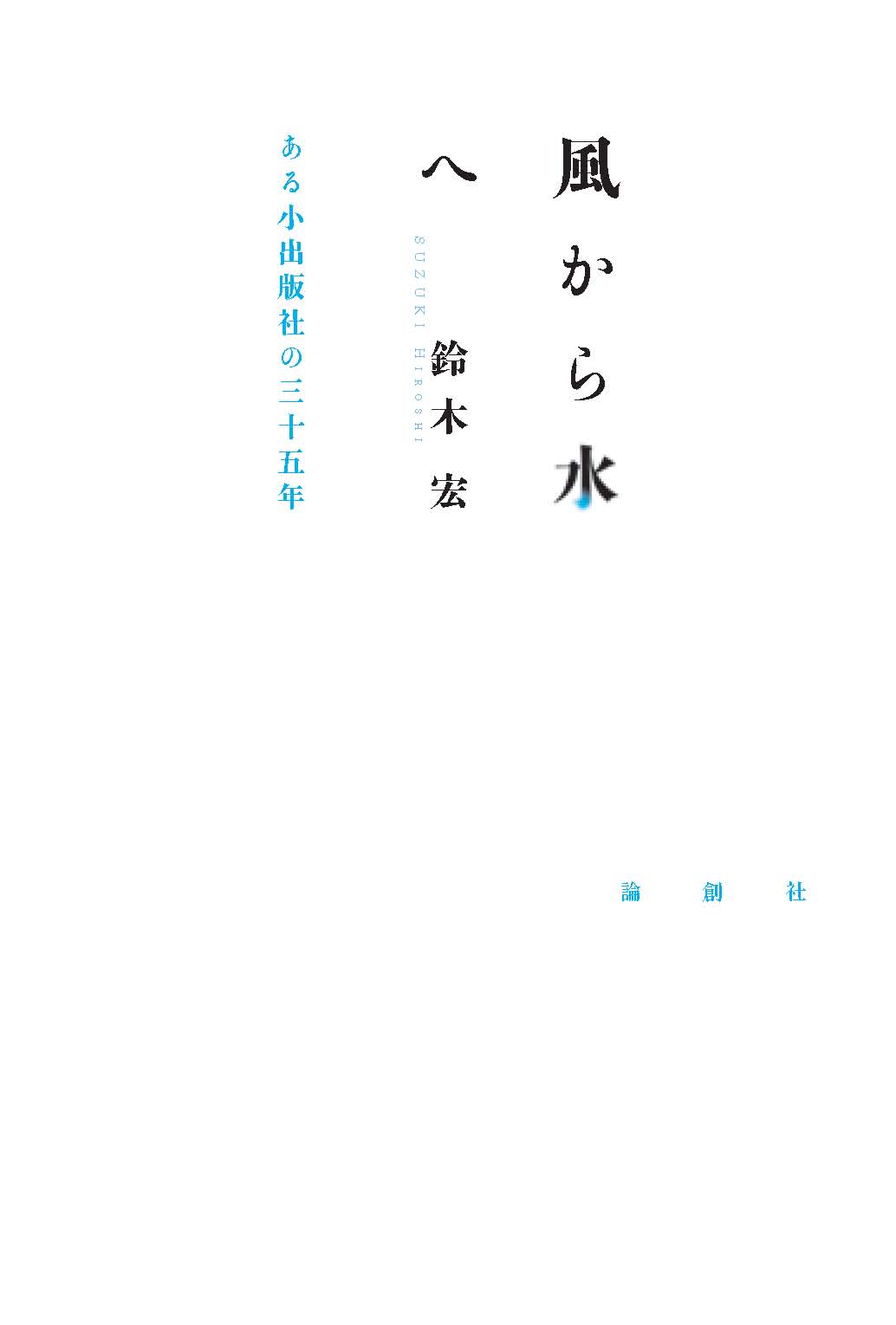㉑ 再びの丸山猛と須賀敦子
小田光雄
前回、鈴木宏の『風から水へ』の刊行に際し、榎本香菜子という女性から葉書をもらったことを既述した。また彼女が1970年代に関内のキディランドでアルバイトを務め、そこにいた今泉正光を鈴木に紹介したことも。
今回はやはりその関内のキディランドにいた丸山猛のことにふれてみたい。それは榎本も「丸山猛は須賀敦子さんと親しく、ユニークな人生を歩み仲良しだったので、どこにいるのかもわからなくなり淋しいかぎりです」としたためていたからだ。実は2009年に拙ブログ「出版・読書メモランダム」で、「丸山猛と須賀敦子」を書いている。それゆえに本タイトルを「再びの丸山猛と須賀敦子」としたのである、後半は重複してしまうが、それは避けられないことを承知してほしい。
70年代のキディランドの書店人脈に関しては、今泉の『「今泉棚」とリブロの時代』(「出版人に聞く」1)に語られている。彼によれば、一緒に仕事をしたことはなかったけれど、丸山はICU出身で、社員としては抜きんでた本読みで、自分とはウマが合い、仲がよかった。それに奇妙な関係というか、後の丸山夫人が今泉の部下、同じく今泉夫人が丸山の下でアルバイトをしていたという。それからキディランドが会社更生法下にあり、丸山と異なり、今泉は組合運動に携わっていたことから、77年には西友に入社する。また個別の選択であり、一緒ではなかったけれど、丸山も西友に入ることになった。これは余談だが、『営業と経営から見た筑摩書房』(「出版人に聞く」7)の菊池明郎もICUだから、当然のことながら丸山と面識があったにちがいない。
私が丸山と知り合ったのは1980年前後で、彼は清水の西友の書籍売場にいたが、まだリブロという名称にはなっていなかったと思う。当時の西友は静岡の古本屋とコラボし、古本催事を静岡東部で盛んに展開しつつあった。その背景にはいくつかの事情が絡んでいたのだが、それは本稿の目的とずれてしまうこともあり、別の機会に譲ることにする。
丸山はこの時代にその古本屋と親しくしていたので、催事などを通じて、古本のノウハウを学んだはずだ。その後丸山は西友を退社して東京に戻り、祐天寺に新しい古本屋をコンセプトとする、「あるご書店」を立ち上げ、そこを中心として、コミューン的グループを目論む「自由フォーラム」を結成に至る。それは80年代半ば頃のことで、特異な古本屋チェーンとして評価され、チェーン化も順調だと伝えられていた。そこまでの丸山の軌跡は知っていたが、その後の消息は聞こえてこなかったし、90年代の動向は不明のままだった。
ところが前世紀も押しせまった1998年に意外なところに丸山を見出したのである。それは『文藝別冊』として出された『追悼特集須賀敦子』においてで、丸山は「須賀さんはパワフルな子供』だった」と題するインタビューに答え、須賀の知られざる「もうひとつの顔」を語っている。そしてそこに描かれた丸山による須賀像は、『同特集』の著者になってから交流した人々とは異なるもので、まさにサブタイトルの「霧のむこうに」潜んでいる彼女の実像を浮かび上がらせている。
私も御多分にもれず、1990年刊行の『ミラノ霧の風景』(白水社)を読み、その記憶と想起の綾なす素晴しい文章に魅せられた読者の一人だった。しかしその一方で、こうした「美文」は須賀の本質をカモフラージュするように機能していくのではないか、また彼女の経歴とその時代状況ゆえに、文芸ジャーナリズムのスターとなり、消費されていく対象となるのではないかとも思われた。後者については前書で、91年に女流文学賞と講談社エッセイ賞を受賞し、そのような道を歩み出していく。やはり同年に翻訳もタブッキ『インド夜想曲』(白水社)などの3冊を刊行し、92年には『コルシア書店の仲間たち』(文藝春秋)を上梓する。同書の読後感も前書と変わらなかったし、それに加え、これから「書店」のイメージも女性誌などを始めとして、従来と異なった方向に転換されていくのではないかと予感させられた。そのような須賀体験ゆえに、もはや私が読者に加わる必要もないだろうと考え、それ以後の彼女の著書を読んでいない。
やはり須賀は予想どおり、60歳を過ぎた遅咲きのデビューだったにもかかわらず、エッセイスト、イタリア文学者として注目を浴びた。そして98年に死去という短い文学活動だったが、没後に河出書房新社によって『須賀敦子全集』全8巻が編まれ、彼女に関する特集や読本類の出版も多くを見ている。そうした意味において、彼女はエッセイスト、イタリア文学者として栄光に包まれ死去し、死後もまたオマージュを捧げられる存在であり続けているといえよう。
しかし丸山が語る須賀の姿はそれらとまったく隔たっている。彼が彼女と知り合った頃、彼女はイタリアから帰ったばかりで、まだ安定した職にもついておらず、『同特集』にも3編の記事と自らの紹介が収録されている「エマウス運動」に携わっていた。「エマウス運動」については、彼女の「エマウス・ワーク・キャンプ」の記述を引いておこう。
エマウス運動というのは、一九四九年、第二次世界大戦が終ったばかりのパリで、通称アベ・ピエールとよばれる神父さんが、当時、巷に溢れていた浮浪者の救済、更生対策として、かれらと共に廃品回収をはじめたのに端を発している。なにかの理由で社会の歩みからはみ出してしまった人たちが集まって、廃品回収をしながら共同生活を営み、その労働から得た収益の一部を、自分たちよりも更に貧しい人たちの役に立てようと努力しているのが、この運動の主体となっているエマウス・コミュニティーである。
このワーク・キャンプが73年に清瀬で1ヶ月間開かれ、彼女はそれに参加している。
須賀は丸山の店に客としてやってきて、色々と話をするようになったという。丸山は戦後の混乱の中でスポイルされた子供たちを支援する「子供会」にかかわり、その「子供会」グループが須賀の友人たちだったことにもよっている。後の「自由フォーラム」の社員は、この「子供会」出身者が中心メンバーとなっている。
丸山へのインタビューを抽出しながら、彼から見た須賀敦子の生活者のイメージを追ってみる。
たぶん、コルシア書店のイメージとだぶらしていたんじゃないかとぼくは思っています。うちの会社は、運命共同体というかコミューンみたいなかたちで運営しているんです。あの人は生活者としての原点みたいなものを常に持ち合わせていた人ですが、それをぼくらに見ていたのじゃないかと思います。
そして彼女は丸山の古本屋のコミューン的グループに接近し、ずっとその近傍にいた。入院後の世話や連絡係もそれらのメンバーが担ったようだ。
須賀さんとも約束していたんです。あの人がもしすごく長生きして、書けなくなったら、うちのグループにおいでよって。株主にしてあげるから全財産出せい、と(笑)。「たくさんあるよ」っていうから、「知ってるよ」って(笑)。
あの人は惜しげもなく、たぶんほんとうに出したと思います。ぼくたちのコミューンを成功させたいと、そういうふうに彼女自身は思っていました。けっこうお気に入りでした。
丸山の視線は絶えず彼女の生活者の側面に向けられていた。
須賀さんの、文学者と生活者の両方の顔を、ぼくは見ていましたが、ぼくらといるときは生活者のかわいい面を見せていました。
そういう中で彼女がかわいらしくしていられるというんですか、安心していられる。逆にいうと、文学者のほうですと、やはりつらそうだなというのが見えました。
また生活者としての須賀は「うろうろする人」で、「自信のない人」だった。それがデビューしたことで変わり始める。
作家デビューというか、世の中に認められはじめたころの彼女は、満足感というんですか、ちょうど変わり目、巣立っていくなという感じがありました。
少しは自信がついてきたんでしょうね。賞をもらったり、まわりの方たちの扱いとかで。その変わり目というのが、人格が二つできちゃったような感じがしましたね。
だから、彼女はちがう二つの世界に分かれている。どっちが本当かぼくにはわからないですけれども、ふつうの文学者とはちがって、五十歳ぐらいまでは生活者でいたわけですからね。
このような丸山の語りは、「子供がそのまま大きくなったような人」須賀敦子の核心にふれていく。少し長くなってしまうが、これは須賀の内面に深くふれ、また丸山と彼女の関係を物語っていると思われるので、省略しないで引用しておく。
あの人は、自分の自由を抑えるものは何者も許さないというような、自分の美意識がはっきりありましたね。美意識の鋭い子供。そしてパワフルであるから、人に被害を与えることもある。
ただ、あの人はおそろしく悲しい人だなと思ったのは、そのような自分を、よく知っているんですよね。常にぼくにこぼしていたのは、「友だち少ないんだよ」という言い方で、「そうだよな、あなたの性格だとね」というと、「そうなんだよ」と。結局、自分のおそろしいほどのわがままとか、そういうのをよく知っているんですよね。孤独というんですか、ものすごくありましたね。それから、老後に向かっていくときの女一人の頼りなさとか。でも、あの人はそういうことを対外的には口が裂けてもいわない。自分で立っていくんだ、と。強過ぎる人ですからね。
しかし日本のコルシア書店と出会えたことで、彼女の「孤独」も多少なりとも癒されたのではないだろうか。書店からも古本屋からも様々な物語が消え去ろうとしていた90年代にあって、須賀敦子と丸山猛たちが演じていた未公開のドラマは、彼女たち固有のものであったにしても、出版史の記憶にとどめられる出来事だったのではないだろうか。
これは『同特集』で知ったのだが、須賀は祐天寺に住んでいたことから、「あるご書店」の客となり、丸山とそのグループに接近していったのだろう。丸山の証言にもあるように、須賀にとって、イタリアのコルシア書店ばかりでなく、古本屋チェーン「自由フォーラム」を体験することによって、『コルシア書店の仲間たち』も書かれるにいたったのではないだろうか。いや、きっとそうにちがいない。そしてコルシア書店がそうだったように、丸山の「自由フォーラム」も須賀亡き後、「霧のむこうに」消えてしまったのだろう。冒頭に紹介した丸山が行方不明というのも、そのことを告げているのように思われる。
なお最後にひとつだけ私の後日譚を付け加えておけば、今世紀に入って、リサイクル店でオリベッティのタイプライターを見つけ、それを買った。もちろんタイプライターなど打てはしないのだが、『ミラノ霧の風景』がオリベッティの『SPAZIO』に連載されたことを記憶していたからである。須賀もこれを使っていただろうか。
—(第21回、2017年11月15日予定)—
バックナンバーはこちら➡︎『本を読む』
《筆者ブログはこちら》➡️http://d.hatena.ne.jp/OdaMitsuo/