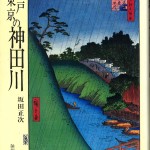- 2020-4-21
- 論創通信, 矢口英佑のナナメ読み
No.25 『昭和の作曲家20人100曲』『昭和の作詞家20人100曲』
矢口英佑〈2020.4.20〉
著者の塩澤実信は『週刊大衆』編集長、双葉社取締役編集局長などを歴任し、日本レコード大賞審査員なども務めたことがある。論創社からもこれまでに『愛唱歌でつづる日本の四季』『ベストセラー感覚』『活字メディアの最前線』などを刊行していて、出版界や歌謡曲界については詳しく、それに関わる著作も多数著している。その意味で、この2冊は著者の得意分野の姉妹本である。
それにしても歌謡曲界の裏表を知り尽くしているだけに、それぞれ20人の作曲家、作詞家を選び出すのは、難業だったようである。『昭和の作詞家20人100曲』の「はじめに」で、
生涯に多い人なら三千から五千曲は作っている作詞の世界で、「二十人と五曲」とは、いかにも些少であるが、小冊子故、多くは望むべくもなく、五曲で収めることはむずかしかった。選考にあたって、売上枚数はもちろん、「紅白」で歌われた曲、「レコード大賞」の受賞曲など各種の資料は基準にはしたが、私の独断と偏見のそしりは覚悟の上である
と著者自身が吐露している。これは『昭和の作曲家20人100曲』でも同様であったのは、やはり「はじめに」で、
一暼すればおわかりのように、「リンゴの唄」などを作曲した万城目正、ラジオ歌謡でお馴染みの八洲秀章、「リンゴ追分」の米山正夫、「東京の花売娘」の上原げんと、「骨まで愛して」の北原じゅん、「天使の誘惑」の鈴木邦彦等々……。歌謡曲通であったら、たちどころに思い浮かぶ作曲家の項がないことに、不服・不満を持たれることは覚悟の上である
と同様の言葉を記していることからもわかる。
この2冊には「歌謡曲が輝いていた時」という副題がつけられている。言い換えれば、昭和という時代こそ、日本人が流行歌に親近感を覚え、ふと口ずさみ、記憶に刻んでいった歌が数多くあるということにほかならない。
それにしても、歌謡曲は今でも歌われ続けているにもかかわらず、なぜ「昭和」なのだろうか。この「昭和」という時代は、1926年12月25日から1989年1月7日までの64年間である。ただし昭和元年は7日間、昭和64年も7日間だけで、実質的には62年間ともいえる。もちろんこのような数字が示す厳密さで本書の「昭和」が区切られているわけではない。ただ確実に言えることは、「昭和」という時代は、1945年8月15日を境に国の形がまったく変わってしまったのである。それまで正当とされていた思想や価値観が否定され、政治、経済、文化、制度等々が想像を超えて、一気に変容していく姿を多くの日本人が茫然自失のなかで見つめ、受け入れていくしかなかった。「昭和」は「昭和」でありながら、2つの「昭和」があったと言っていいだろう。
それにもかかわらず、いや、だからこそ歌謡曲が輝いていたのは、この「昭和」が激動という言葉では表現しきれないほど激動の時代だったからにほかならない。激動であればあるほど、不安、苦悩、悲哀、孤独、人恋しさなどでぽっかり空いた、埋めきれない心の隙間を埋めようと、人びとは心の拠り所を知らずに求めていったのである。その時々の人びとの心を写し取るように歌詞が生み出され、メロディーが付けられ、それをみごとに歌い上げる歌手という三者一体の歌謡曲は、まさに〝流行する歌〟として人びとから迎え入れられていったのである。
私自身、この2冊の目次に並んでいる作曲家や作詞家、そして曲名をざっと見渡しただけで、いくつもの歌詞やメロディーが思い浮かび、いつの間にか口ずさんでいる自分に我ながら驚かされた。もちろん歌手の顔も、その曲の歌い方までも思い出され、作曲家や作詞家の名前に懐かしさを覚えた。その理由は簡単である。私が過ぎ越してきたその時々の私なりのできごとと、その時代とが鮮明に思い浮かんでいたからである。
この姉妹本は〝人に歴史あり〟と言われるように、まず取り上げた作曲家、作詞家の来歴が記されている。簡単な略伝と言っていいだろう。ただし、一般的な人物伝と異なるのは、当然と言えば当然だが、作曲や作詞にかかわる人物伝になっていることだろう。そのため作曲家、作詞家各20名、曲各100曲についてだけでなく、その他の曲や歌手、作曲家、作詞家などもしばしば登場し、彼らの人生やエピソードも合わせて触れられていて、百花繚乱の観がある。さらに加えて著者の塩澤が直接、会っている人物について、著者だけが知っている内実や印象記も織り込まれていて、説得力があり、読み手を飽きさせない。
一例として、2020年4月からNHKの朝のドラマ「エール」の主人公のモデルとなっている古関裕而の項を紹介すれば十分だろう。
リムスキー=コルサコフの「シェヘラザード」ストラヴィンスキーの「火の鳥」、ドビュッシー、ムソグルスキー等の曲が与えた衝撃は大きく、古関裕而作曲の通奏低音になった
と古関の音楽の原点を指摘しつつ、音丸によって歌われた「船頭可愛や」が大ヒットすると、
古関が天賦の才能を発揮しはじめるのは、この後からだった。クラシック調の格調高いメロディーに、哀調をおびたせつない旋律を融合させた古関メロディーの誕生だった
とこの作曲家の音楽的特質をきちんと指摘している。
その一方で、かつて週刊誌の編集長であったことを彷彿とさせるように、若くして管弦楽での国際的作曲コンクールで入賞した古関に触れたあと、
この入賞の報を新聞で読んだ愛知県豊橋市の内山金子は、福島の古関にファンレターを送ったことから、熱烈な文通を経て恋が実り、昭和五年、裕而二十歳、金子十八歳の若さで結ばれ、生涯のおしどり夫婦になった
とゴシップ的な文章もさりげなく挟んでいる。そして著者との関わりでは、「私が、古関裕而に会ったのは最晩年であった。歩くのも大儀のようで、両足をひきずるようにして応接室に入って来たことを記憶している。応答は実に謙虚で丁寧であった。私は古関メロディーファンで、少なからずの曲を知っていて、それらの曲の挿話を問うと、「よく存じていらっしゃる、よく存じていらっしゃる」とのつぶやきを繰り返していたことを、三十年後のいまでも忘れられない」
このように作曲家、作詞家の略伝が記されたあと、選び出された5曲の歌詞が題名とともに紹介されるのだが、その前段として、その曲や詞についての裏話や誕生の経緯、関連するエピソードが綴られている。
この構成も読者を惹きつけ、飽きさせないという意味では巧みである。その曲や歌詞の誕生の背景を知ることで、その歌との親近感を促し、歌詞の味わいをより深めてくれるからである。
この2冊は作曲家、作詞家が生み出した歌謡曲とそれを歌った歌手にスポットを当てた昭和歌謡史とも言える。しかし、著者が触れる歌謡史には「昭和」という時代に日本が、そして、日本人がたどらざるを得なかった政治、経済、外交、文化、生活等々への言及も少なくない。
その意味では著者がどれだけ意識していたのかわからないが、この2冊は、「昭和史」が学べるテキストにもなっているのである。
(やぐち・えいすけ)
バックナンバー→矢口英佑のナナメ読み
〈次回、2020.5月下旬予定『愛・自由・平等 心やさしき闘士たち』〉
『歌謡曲が輝いていた時 昭和の作詞家20人100曲』 四六判並製336頁 定価:本体2,000円+税
『歌謡曲が輝いていた時 昭和の作曲家20人100曲』 四六判並製336頁 定価:本体2,000円+税