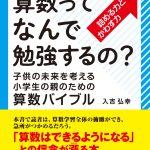- 2021-8-6
- お知らせ, 論創通信, 矢口英佑のナナメ読み
No.41 『道祖神の口笛』
矢口英佑〈2021.7.29〉
「作家は処女作に還る」とはよく言われる言葉。その意味するところは、おぼろげな言い方なら「作品世界の風合い」といったものだろう。もう少し具体的に言えば、作者が作品化する「問題意識」「視点」「作品構成」「執筆姿勢」「描写方法」「題材」等々であったりすると考えられる。
その意味では、本書は「処女作に還る」を実証していると言えそうである。作者にとって二冊目の小説集であり、一冊目の『埋もれた波濤』(表題作のほかに「鳩憑」「地図の中に吹く」「風迷」の三短編小説を収める 論創社 2018年)を知る私には、大雑把に言うなら、作者は〝生きる意味の追究〟と〝執筆姿勢〟を作品世界を紡ぎ出す作家的肉体として備えているように見える。
書名にもなっている一冊目の『埋もれた波濤』は、1983年にサハリン上空で269人を乗せた韓国の大韓航空機がソ連(当時)の戦闘機によって撃墜された事件が描かれている。事件当時、新聞記者だった作者の実体験が存分に生かされ、実証に基づいた記述は「報告文学」と言える作品世界を築いている。
その意味では、本書の「漂流船」と「ボートは沈みぬ」はその範疇に入る作品だろう。
「漂流船」は、秋田県庄内海岸に漂着した北朝鮮からの漂着船の写真を撮りたいという東京在住の定年退職している大学時代の友人からの申し出で、秋田市内に住む「私」がそれにつきあう一日が描かれている。ただこの作品では、秋田のテレビ局在職中に起きた「私」とは旧知の間柄である元県知事のうやむやに終わった汚職事件が濃厚に絡んで描かれていて、二つの異なる事象が一つとなって作者の思いが表出されている。
また「ボートは沈みぬ」は、1910年1月に逗子開成中学校の生徒12人と小学生1人、計13人が乗ったボートが七里ヶ浜沖で転覆、沈没し全員が水死した事故とそれを取り巻く人びとの人生模様が描かれている。現在でも歌われている「真白き富士の嶺」はこの事故で亡くなった生徒たちの葬儀当日に発表、歌われた哀悼歌であることから「私」の語りが始まる。
この二作品は、いずれも実際に起きた事件、事故あるいは事象が取り上げられている。しかし、作者はそれらを膨らませ、限りなく想像の世界に読み手をいざなおうとはしない。その描写姿勢は徹底的に実証的であろうとしており、小説とは荒唐無稽な世界も許されるはずだが、それからは遠く隔たっている。
それは否応なしに染みついているにちがいない新聞記者だったというこの作者だからこその作品の色合いを可能にさせたのだろう。色濃く染みついたこの記者魂が足で、目で確かめた事実の積み重ねによる作品世界を作り上げていると言っていいだろう。
ただし、この二作品にもう一つの〝生きる意味の追究〟がないわけではない。たとえば「漂流船」には元知事から連絡を受けた老人が漂流船の現場に現れ、この人物の人生、知事との繋がりなどが明らかにされていく。脇役にちがいない人物に一定のスペースを割いて人間観察が綴られるのはいかにもこの作者らしいのだが、元知事の汚職疑惑事件に迫る脇役としての重みを感じさせている。また「ボートは沈みぬ」は作者の「あとがき」から一部引用しておく。
心づもりとしては、青少年の抑えられぬ冒険心と破綻を書いてみたかったのだが、この事件で人生が狂った男性教師、一躍名を挙げた女性教師、事後責任を全うした校長の運命を比較することになった
これら3人の人物はすべて実在していたわけで、それぞれの事件後の人生を丹念に追いかける作者の手法は微塵もブレない。そして事故を背負った三者三様の生き方にさまざまな陰影を投げかけ、生への道行に苦悩する姿が浮かび上がってくる。こうして、巷間流布していたことと、調査を進めるにしたがって鮮明になってきた「事実」を前にして、しかし、それがかえって「真実」から遠ざかることにもなり得る可能性を示唆することにもなっている。その意味ではこの小説は作者が新たな小説世界を構築する入り口に再度、立ったとも言えそうである。
以上、二つの作品は『埋もれた波濤』と同じく実証に基づいた「報告文学」と言えるものだが、あと二つの小説「ミャンマーの放生」と「道祖神の口笛」は〝生きる意味を追究〟することに重きが置かれた作品である。
「ミャンマーの放生」の「放生」とは仏教信仰世界で行なわれる功徳を示す行為である。現在の日本でも亀や魚を川などに放す「放生」が行なわれている地域があるのではないだろうか。この作品では捕らえられた鳥の命を買い取り、それを放して命を救うのである。 仏教国としての歴史、日本が侵略した歴史、そして、現在のミャンマーの情緒風情、社会の動きがここでは外国人であり、この土地を蹂躙した国からの旅行者の目を通して語られている。しかし主な登場人物である男と女にはそれぞれ、病気と事故で死の淵を覗いたという経験があり、自分探しの旅にもなっているのである。
明るい太陽が降り注ぐ大地と人々とが描かれながら、人間一人ひとりの心のひだに入り込み、その心奥を覗いた時、名状しがたい暗闇が広がっているような感覚に陥る。それは功徳を施し小鳥をカゴから放してやったにも関わらず、
自由の空が頭の上に広がったのに、小鳥たちは動こうとしない。やがて、ツバメに似た一羽が逡巡するように舞い上がり、他の鳥たちもふらふらと翼を動かした。(中略)それはいかにも頼りない姿であり、自分の拾った命の重さにうろたえているかのようにも見えた
からかもしれない。
ここには作者の、そして主人公の「生」への思いが重なっているからであろうし、この国の現状への思いが込められているからだろう。それはこの旅で通訳として登場する人物の「自由を得たものの、行くべき方向を見定められぬ小鳥たちの困惑の中に、自分自身の姿もあるように思えた」との感慨からも窺える。
この小説は「放生」という作品名の重さを読み手は小説の最後になって知ることになるにちがいない。
本書の表題となっている「道祖神の口笛」は、「戦時中の大学生が、出征を目前にして思想形成に焦る様子を描いた創作である。前進するために観念の〝虚構〟が必要であり、これにすがって真理をつかもうとする青年の葛藤を描いてみたかった」という作者の言葉(「あとがき」)はさすがに簡にして要を得ている。
舞台は昭和19年6月、日本が全面降伏するおおよそ1年ほど前の仙台であり、主人公は4年越しの肺浸潤症を患う東北帝国大学法文学部文科の学生である。当時の時代状況、大学の様子、仙台という地方都市とそこで生きている人びと、そして戦争、いずれについてもこの作者らしい丁寧な資料の読み込みとそれに基づいた描写がいかんなく発揮されている。
この小説は、祖父母の家を訪ねるために乗車した列車で言葉を交わすことになった男との出会いが、いかに生きるか思い悩んでいる主人公に大きな足掛かりを与える。この人物(太宰治を想起させる人物)は松尾芭蕉の『奥の細道』は半分は創作だと言い、998年に道祖神社を馬に乗って通過したときに祭神に対して無礼な言動があって、たたりで落馬、愛馬の下敷きとなって死んだという藤原実方の評価などを主人公に語る。
それをきっかけに主人公は『奥の細道』、曾良の『随行記』、尾崎雅嘉の『百人一首一夕話』などの書物に興味を抱き、彼なりの理解を深めていく。主人公に思想的苦悶を繰り返させるのは、「「公」の大義とは「個」の不自由の集積によって実現するのか」「国家に強制されない自分の使命は何か」であり、「戦争を遂行する「公」と、自身の成長を願う「個」との包括関係を納得したかった」からである。
そのようなときに芭蕉終焉の真相に迫る弟子たちとのやりとりを記録した『花屋日記』を手にする。正岡子規が感動のあまり大泣きしたという書物である。しかし、この書物に記された書簡や日記までが創作で、実録ではなかったのである。
だが、主人公は「事実と虚構の絶対的な相違と、真相を記録することの表裏一体性について考え」させられ、「虚構であるがゆえに、真実に最も近い世界が描かれることの意味の重大」さに思い至るのである。
こうして作者は主人公に「自分が生きている時代は虚構に支配されている」と認識させていくのである。小説というものに許される事実と虚構の混沌性、そして虚構が紡ぎだす真実という創作の力を現実世界に当てはめて生きようとする主人公……。
この小説は遠い昔のもはやあり得ない時代の物語ではない。
私たちは個として生きている人間だが、国家、社会という枠組みの中でも生きなければならない。枠組みに縛られるかぎり、決して個としての自由を完全に手にすることはできない。ではどのように折り合いをつけ、納得させて生きていくのか。決して生きやすいとは思えない現今の社会にあって、避けて通れない問題が潜んでいることをこの小説は我々に教えている。
(やぐち・えいすけ)
バックナンバー→矢口英佑のナナメ読み




![矢口英佑のナナメ読み #031〈『歴史に学ぶ自己再生の理論[新装版]』〉](https://ronso.co.jp/wp-content/uploads/2020/06/9b4700a2fd66beeb81bc6fe61cc90451-150x150.jpg)