- 2022-3-2
- お知らせ, 論創通信, 矢口英佑のナナメ読み
No.47『ヒューマニズムとフェミニズムの後に来るもの』
矢口英佑〈2022.3.2〉
これからの社会はどのように変わっていくのか、自分はどのように生きていくのか、誰もがふと思う事柄だろう。そして当然のことだが、みずからが立つ現在を私たちは個人的にも、社会的にも断ち切れない。現在から繋がる未来に対する問いかけは、見えないからこそ不安でもあり、可能ならば知りたいという欲求は常にどこかに潜んでいる。
本書はその意味では、見えない未来の形を示した予測の書と言える。ただし、書名に「ヒューマニズム」「フェミニズム」とあることからもわかるように、国の形がどのようになるのかを政治的に真正面から論じてはいない。人間の生き方、あるいは社会の動きの中での身の処し方などへの思考方法や精神のありように焦点が当てられている。
それらがこれまでの人類の歩みの中でどのように変化して、人間の生き方に反映されてきたのかを分析し、どのような社会となるのかを予測し、どのような社会を作り出していくべきかを示している。
本書について、著者は「まえがき」で次のように記している。
本書は神様の死と、人が神様からはなれて人間として自立する物語である。と同時に、二十世紀末から今日にかけて本格化した、女性による社会的台頭の真の原因を解き明かすものである。そして、今後は未成年者など若者が、成人の男性や女性と同じ社会的存在になることを予言する(中略)人類の歴史上、労働の対象は土地→物→情報と変わってきたが、人間の身体構造は変わらない。だから、男と女がいて子どもが生まれるのも変わらない。しかし、子どもの作り方は変わるかも知れない。そして、育て方は確実に変わるだろう。なにしろ労働対象が、煙よりも軽い情報なのだから。
本書にはかなり刺激的な言葉がいくつも現われる。上記の「まえがき」に見える「神様の死」もそうだが、目次にも「産業革命に先行する神殺し」「市民革命は神殺し父殺しだった」(第Ⅰ章)、「神殺しの犯人は男だった」(第Ⅱ章)、「母殺しの意味するもの」(第Ⅲ章)といった見出しが並んでいる。
著者の大きな関心は「家族」である。そして、その「家族」を構成する「父」「母」「子ども」のありようである。大きな集団を構成する基本的なこの集合体が何によって、どのように変容してきたのかを解き明かす過程で上記に示した刺激的な言葉が現われてきたと言える。
では家族の姿はどのように変容してきたのだろうか。著者は人類が歩んできた社会の生産構造を農耕社会(伝統社会)、工業社会、情報社会と大きく3つに区分する。この3つの社会構造の変化によって「男・父親」「女・母親」「子ども」の家庭での立場や社会的な位置、言い換えれば存在価値が変容してきたと捉えるのである。
これに関連して、著者はさらに根源的な事実の指摘も忘れない。それは人類が存続するためには「人々が健康な身体を維持していく」ことと「子孫を残すこと」が必要で、この二つが満たされない限り人類は生き延びられないというものである。
では人類は生き延びるために何をしてきたのか。著者は次のように分析している。
人類の歴史で長期間、維持されてきたのは農耕社会であった。この社会では、食糧生産として土を相手にする農業が営まれ、男女ともに農業に従事していた。ただし、肉体的には男が女より重労働に優れていたため、社会的な序列では男が優位に立った。この社会では自然現象はすべて神が支配し、人間も神によって守られ生きていると捉えられていた。男女の結びつきは生き延びるために結婚し、生産組織としての家族を作るためで「愛」は不要だった。
工業社会では土を相手にした農業から物を相手にした工業に変わり、人々の思考方法や行動も変化し、何よりも読み書きのできる労働者が出現してきた。天動説から地動説に転換したことからもわかるように自然法則の発見、科学的な思考は神の存在の疑義へと変化していく。それは自然と人々の考えの不合一へと繋がり、人は自分の頭で思考するようになり、神の縛りから解放され人間となった。科学は神を不要とし、神を殺した。そして家族における神の代理人だった父=家父長も殺される(不必要)に至った。封建社会や絶対王政が否定され、それに代わって人間が中心=ヒューマニズムとなり、基本的人権という概念が誕生した。
生産力の向上は個人収入の増大をもたらし、工業社会は豊かになった。女の生活水準も向上した。ただし神を殺し、人間になれたのは男だけだった。女は神が作った子産み・子育てに従事して、男とともに個体維持=生産活動に加わらず、種族保存を担ってきたからである。生産活動をせずに専業主婦となった女たちは男支配の社会を支え、性別役割分業が明確になった。
工業社会が進む中で、厳しい肉体労働に替わって機械が登場したが、やがてコンピューターという頭脳の代替物によってデジタル機械文明の時代=情報社会が出現した。その結果、男の頑健な肉体は不要となり、頭脳の働きの優劣が問われ、知力だけが求められる社会となって、体力的に劣る女が同じ労働に就くことが可能になった。生産活動に男と同等に加われるようになった女は種族保存に専従し、妊娠・出産・子育てを存在証明とする必要がなくなってきた。この神が与えた女だけの属性に依存しなくてもよくなった女は女性という人間になり、母という立場の放棄が可能となった。
情報社会では男性と対等に生産活動に従事できるようになり、かくして女は母を殺して女性となった。生産活動が肉体労働から頭脳労働へと転換することで男女の肉体的な違いは意味を持たなくなって、男女の社会的立場は同じとなり、女性と男性は同質の人間となった。
著者が区分する伝統社会、工業社会、情報社会を大雑把にまとめれば、以上のようになるだろうか。
著者の分析は小気味いいほど明快である。しかもこれらの分析を通して見えるのは、「まえがき」でも触れられていたように、著者の大きな関心は「女性」が一人の人間となりつつある中で、社会は今後、どのようになり、女性がどのように生きていくべきかを示そうとしていることである。
しかし、女性だけでこの社会が構成されているわけではない。著者の言を借りれば、工業社会になって、女性より早く神を殺し、父を殺した男性は人間中心主義=ヒューマニズムを獲得し、人間になった。情報社会となった現在、生産活動の第一線に立とうとすることから子育てを男女が平等に担うものとするのがフェミニズムであり、母を殺した女性も人間となったのである。ヒューマニズムもフェミニズムも人間解放の思想だが、フェミニズムは男からの解放も含まれていた。
こうして男女ともに社会的動物となった現在、来るべき社会はどう変えなければならないのだろうか。
まず大前提としてあるのは、著者が指摘していたように、人類が存続するためには「人々が健康な身体を維持していく」ことと「子孫を残すこと」が必要だということである。少子化が問題となっている日本(だけではないが)だが、しかし「子孫を残す」方策となると、これといった打開策を見いだせていないのが現状である。その理由は簡単である。妊娠・出産ができるのは女性であり、男性にはできないからである。産む、産まないの決定権は女性にあるからである。
ではどうすればよいのだろうか。著者は次のように回答している。
女性しか子供を産めない以上、妊娠・出産までは女性にお願いする以外にない。子供を産むことは引き受けるが、男性とのセックスが嫌だという女性には、社会が費用を負担して体外受精で子供を産んで貰うしかない。妊娠・出産で女性の身体は約一年は拘束される。その一年間は社会が女性の身体と生活を支える必要がある。そして、産まれた子供は社会が育てるのだ。
我が国の人口を絶やさないようにするために、取り得る選択肢はこの一つしかないと著者は断言している。しかも、さらに刺激的な言葉が続く。
男性が子育ての担当者になってもいい。もちろん女性が望めば、産んだ女性が子育てをしていいが、子育てに専従して専業主婦になることは否定すべきである。
女性は一人の人間として、男性と同等に生産活動に参加することが主流となる社会を予測する著者ならではの主張だろう。こうして著者の来るべき社会とは「工業社会までの核家族的な考えでは、子供は減っていくばかりだろう。単家族化が不可避なのだ。
著者は3年前に情報社会化の中で家族の形態が核家族から一人親と子どもを家族とする単家族を標準世帯とするべきだとした『核家族の解体と単家族の誕生』(論創社)を刊行している。そして今回、本書で男女ともに人間として同等の生産活動を担う者となる社会の行く末を見つめた時、前著との主張と見事に一体化されていることが見て取れるのである。本書を手にされた読者は是非、前著にも目を通していただきたいところである。
情報社会での子育てについて、日本ではまだ提示されていないだけに、著者の主張がどこまで実現されていくのかわからない。しかし、決して実現不可能な主張ではないだけに今後の日本にとって極めて重要な提言になっていることはまちがいない。
(やぐち・えいすけ)
バックナンバー→矢口英佑のナナメ読み



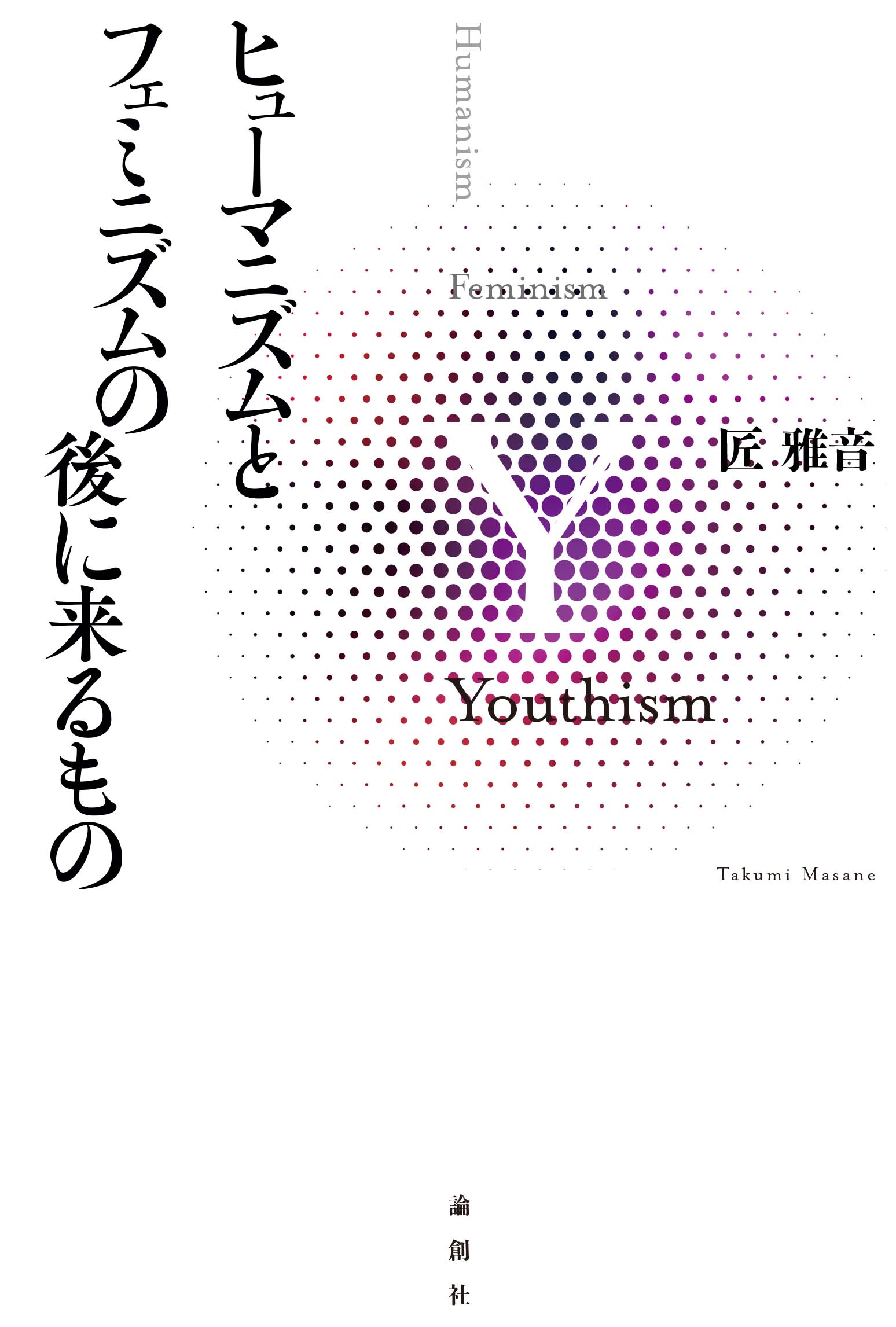



![矢口英佑のナナメ読み #066〈 『[完全版]悪霊の館』〉](https://ronso.co.jp/wp-content/uploads/2019/02/5db823fb210a483918738d776acc0fb5-150x150.jpg)














