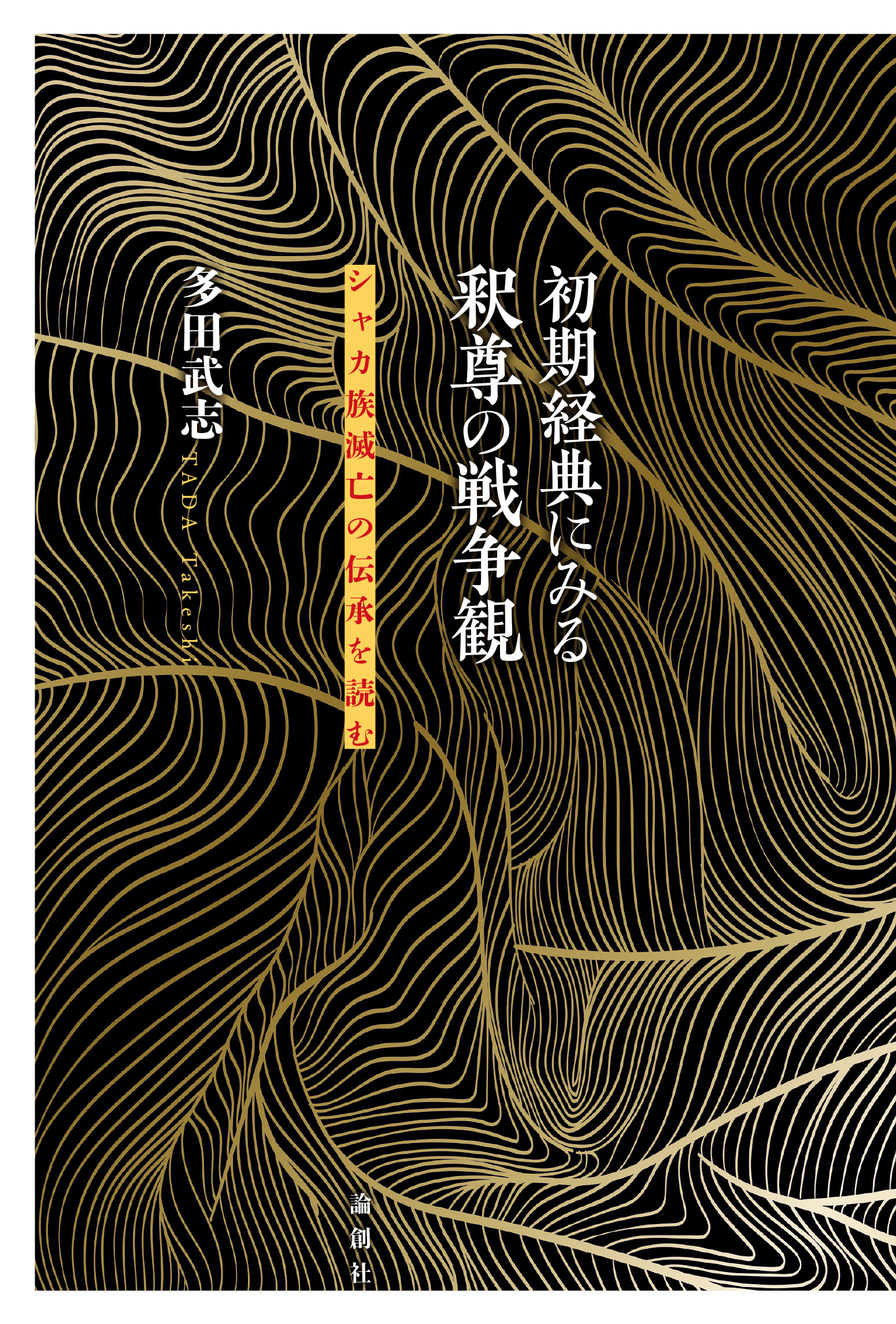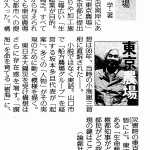- 2023-6-26
- お知らせ, 論創通信, 矢口英佑のナナメ読み
No.72『初期経典にみる釈尊の戦争観——シャカ族滅亡の伝承を読む』
「釈尊」とは、仏教の開祖である釈迦のことであり、釈迦牟尼世尊(尊称)の略である。著者も「凡例」で「仏教の開祖ブッダの呼称は多様にあるが、ここではシャカムニ(釈迦牟尼)=シャカ族出身のムニ(聖者)の意義をもつ漢訳表記「釈尊」を用いた」としている。
釈迦の生没年は不詳だが、80歳での死去は定説化していて、本書でも80歳生涯説に立っている。このように釈迦は歴史的に実在した人物なのだが、日常的に私たちが広く認識していると思われるのは、悟りを開いた釈迦の姿であり、一枚の衣だけを身につけ、装飾品もない仏像としてのそれである。
それだけに、本書では生身の釈迦について論じられているうえに書名に見える「釈尊の戦争観」には意外感を覚え、サブタイトルの「シャカ族滅亡」からは、釈迦が属したシャカ族は戦争によって滅ぼされ、その顛末と釈迦の戦争論が本書では展開されていると思う向きもあるかもしれない。
確かに本書には、シャカ族滅亡の伝承と釈尊の戦争観が記述されている。だが「シャカ族滅亡」の伝承には誇張が見られると著者は言い、また「戦争観」としているが「戦争論」とはしていないのである。
なにしろ紀元前4~500年前後のことで、残された資料も伝承の域を出ない。それだけに著者は多くの伝承記録を手がかりに実態に近づく作業を丁寧に積み重ねていて、仏典への目配りにも抜かりはない。こうした丹念な資料への接近を試みながら釈尊の入滅後、現在まで語り継がれ、記述され、実践されてきている仏教の教えや歴史、事象に反照させて釈尊を捉えようとしているのは当然の執筆姿勢と言えるだろう。
たとえば、釈迦がまだ布教活動をしていた時期だからと推察できるが、著者は現在、広く認知された「仏教」ではなく「釈尊の教団」としている。そして、この教団は「「乞食」を基本理念とし」、「世俗社会との友好かつ相互不可侵の関係を維持することによって成り立っていた」ため、当時の大国であった「マガダ国」をはじめ多くの国は「釈尊に帰依し、仏教僧団を保護した」という。そのため「刑法の適用を控え、税金を免除」し、「自由な活動を容認」するだけでなく、「土地や建物を寄進し、財物や労働力を提供する」こともしていたとしている。
それにも関わらずシャカ族が滅亡の道を進み始めたのは、釈尊が率いる仏教教団ではなく、世俗社会に生きるシャカ族が敵とされたからであった。つまり在家信徒たちと出家集団の両者には明確な違いがあったことになる。
こうした区別は現在の日本にも存在する僧侶と仏教の信者との関係に通じるもので、檀家として僧侶や寺院を経済的に一部は支える役目を果たしている。ましてや「乞食」を基本理念とした釈尊の教団は金銭的、財産的には無物であり、すべて在家信徒に支えられていたのである。
シャカ族を滅亡させたとしているコーサラ国との戦争の原因、経過、終焉について、著者は多様な伝承記録を集積して一つの物語を提示している。コーサラ国王のシャカ族への復讐心が戦争のきっかけだったが、その物語の展開には起伏があり、またシャカ族の戦争での戦闘方法も明らかにされていて、極めて興味深い。
では、シャカ族の戦闘方法とは何か。著者は次のように記している。
「彼らは有能な戦士として戦場に臨みながら、殺されても殺さない戦いを戦った。仏教徒として不殺生戒に殉じたのである。なかでもマハーナーマ(シャカ族の族長―引用者注)は自らの命を犠牲にして多くの同胞を救ったとされる」と。
一方、そうした戦いの状況を目にしていた釈尊とその教団は何をしていたのか。著者はこう記している。
「集団虐殺という大惨事を眼前にしながら、終始、傍観者的態度を崩すことはなかった。そこには、出家と在家の際立った違いが読み取れる」と。
仏教の平和思想の実践といえばその通りだが、これでは滅亡に追い込まれていくはずである。だからこそ著者も「仏教の平和思想の限界がしばしば指摘されてきたのも事実である」としている。
それにもかかわらず、著者は仏教徒種族であるシャカ族の滅亡についての伝承がなぜ語り継がれてきたのか、その理由を探ろうとするのである。著者はみずからの執筆動機を次のように記している。
「国家権力の行使としての戦争、そしてそれにまつわる生命破壊という不殺生戒への挑戦。その脅威にさらされた仏教教団はどのような対応を成し得たのか。それが釈尊の在世中の大惨事として扱われている以上、釈尊の生涯や教団の形成史を考えるうえで、是非とも闡明しておく必要がある」
著者がこのシャカ族滅亡に至る戦闘の物語を本書の冒頭部分に置いた理由が上記の引用から理解できるだろう。
シャカ族の戦いぶりと釈尊が戦争に直面した際に示した行動から、仏教の真髄を見ようとしているからであり、釈尊が人びとに伝えたかった教えとは何かを明らかにすることが本書の目的だからである。
著者が言うように、平和思想が実効性を発揮できるのは戦争前までである。戦争勃発後は侵攻国に戦争を放棄させるしかない。伝承によれば、釈尊はコーサラ国にそれを三度試み、いずれもいったんは戦いを止めることができたという。だが、四度めの侵攻が起きたとき釈尊は「シャカ族の宿業は熟した」と捉えるのである。
これは究極の戦い方と言えるのかもしれない。つまり、シャカ族の自業自得という自覚をシャカ族に促すことで、報復の意思を放棄させ、耐え忍び、争いの連鎖を根絶させるというのである。著者が言うように、それはまさに「至難の倫理的生き方」だった。だが、釈尊は侵略の犠牲者にほかならないシャカ族にそれを教えたという。
この「至難の倫理的生き方」こそが「釈尊の戦争観であり、平和学の骨格であった」と著者は結論づけている。だがその一方で「釈尊の教えを、シャカ族の人々が在家の信仰者として受け入れたかどうかは、別の問題である」とも記している。釈尊の教えがいかに困難を極める対応を強いていたのかが理解できるだろう。
だからこそ人々に救済の手を差し伸べる釈尊の教え、すなわち仏教の教えを著者は本書の末尾に置いているのである。それは仏教を信仰する者の悟りへの道程にほかならない。
(やぐち・えいすけ)
バックナンバー→矢口英佑のナナメ読み