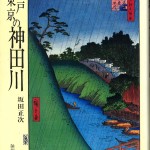- 2023-3-25
- お知らせ, 論創通信, 矢口英佑のナナメ読み
No.67『新まよけの民俗誌』
矢口英佑〈2023.3.25〉
著者の斎藤たまにとって本書は『まよけの民俗誌』に続く第2弾である。ただし、一般的には「はじめに」や「おわりに」が置かれ、著者の声を聴くことができるのだが、それが本書ではできない。著者が2017年にすでに鬼籍に入っており、書き残された原稿の整理、編集作業はご遺族や論創社編集部に委ねられたからである。
本書が2010年に刊行された『まよけの民俗誌』と軌を一にしているのは言うまでもない。したがって著者の「まよけ」に向けられた視点にブレはなく、一貫している。それは、日本全国を巡り歩き、その地域で行われてきている「まよけ」の実相を自分の目で確かめ、記録として書き残そうとしている姿勢にほかならない。
そもそも〝まよけ〟とは何か。漢字では〝魔除け〟である。魔物を排除するという意味で、これほど科学が進歩し、奇怪な現象も科学的に説明がつくという時代になっても、この地球上のどこでも、人間の住むところには魔物が潜んでいて、虎視眈々と災害や病、そのほかのありとあらゆる災厄を及ぼそうとしていると人間は考えるものらしい。だからこそ、その魔物が繰り出す攻撃を阻止しようとさまざまな防御手段を、それぞれの民族や地域の人びとは駆使してきたのである。
日本ももちろん例外ではない。むしろ「まよけ」の伝統、風俗は現在までも日本各地に色濃く残されている。著者は前著『まよけの民俗誌』で軽妙な筆致で次のように記している。
「まものがどんな姿をしているのか、これはまだ誰も見たことがないのでわからない。目に見えない、これがまものの一大特徴なのである。けれども性格ならよく知られている。やたらと人の平安をうらやむのである。人の幸せ、喜びが妬ましくて堪らない。うの目たかの目、邪悪な目で人々の間を漁り歩くのだ」
しかも、このまものは著者によれば、喜びの中にいる人間だけを攻撃するばかりでなく、苦しめ甲斐のあるものならなんにでも攻撃するため、天変地異なども引き起こすとしている。だが、こうしたまものの攻撃に対して人間は「敢然として戦いを挑んだ。大事な子どもを取られないために、家族をその手から守るために」。
ところが、
「しかし何としても人間の方に分が悪いのは相手が目に見えないことである。切っ先鋭く槍を突き出し、剣で薙ぎ払おうが、相手に当たっているのか、当たらないのかさっぱり手応えがないのではどうにもなしようがない」
そこで人間は魔物を撃退できると考えられるあらゆる方策を「数を頼んで、回を重ねて」反撃するようになったという。その結果、
「自分たちにとっても脅威である猛々しいものを盾とし、角や刺のあるものを前面に持ち出し、臭いものや汚いもので辟易させ、叩き音や爆発音を立て、光る物で驚かせ、火と紛う赤色で身を包み、目を惑わせる形象を掲げ、果ては足払いのごときペテンにかける」
著者のこうした魔物と人間との長い関わりを、食うか食われるかの攻防戦として捉え
ているのはどこかユーモラスである。
ところで著者によれば、かつて人間は子どもの誕生に対して半分は鬼の子(まもの)ではないのかという疑心暗鬼があったという。「魂と一つ世界に生きる人たちにとって、生れ出た子は果たして自分の子かどうかわからない。他の魂(神といってもいい)の入りこんだものではないと、確信が持てない」のだという。現在と違って子どもの生存率が低かった時代だったからこそ、成長以前に死んでいく子どもが多い事実を前にして、鬼の子だから奪われていくと恐れを抱いたとしても不思議ではない。
そのため、奪い取られない防御手段として生まれてからしばらくは湯あみをさせず、汚く、汚れた垢で体を覆い、子どもの周りを囲うことが日本各地で広く行われてきていたのである。そのため著者は「赤ちゃん」という呼称も広辞苑などが言うように、体が赤みがかっているからではなく、「あか(垢)子」「あか(垢)ちゃん」だったかもしれないとしている。
また、幼児時期を無事に乗り越えられても、人間はその生を維持し続ける困難さを日々の生活の中で思い知らされ、家族や共同体の生活でも常に生存が脅かされ、苦しめられる事象と直面することが日常茶飯であった。〝なぜ苦しめられるのか〟という理由がわからない苦悩の集積が人間の平穏を阻害するものとしてのまものの存在をさらに信じ込ませることにつながったのだろう。
本書には「一 赤ちゃん」「二 泣く」「三 目籠」「四 小豆餅」「五 生ぐさ」「六 正月」「七 衣」「八 口つけて飲まぬ」の8小題で構成されている。
そして、多くの小題で人間の生と死に関わる〝まよけ〟が登場してくる。人間にとって古来より生と死こそが最大の人生の大きな節目であり、まものを排除する戦いがそれだけ熾烈だったことを教えている。
赤ちゃんについては上述したような例があるが、さらに蕗根などの苦い汁を飲ませたり、塩を舐めさせたり、ぼろ布に包んで荷物のようにくくって置いたり、まよけに効果があるとされる米や小豆を枕元に置いたり、赤い布にくるんだり、額に赤い紅や鍋墨を塗りつけたり、まよけの石を身近に置いたりと、生まれた子をまものから守るために実に多彩な防御手段が日本の各地で取られてきたのである。
一方、多様な〝いわい〟事が各地で行われるが、吉事だけでなく凶事にも〝いわい〟は行われるとして、その際の漢字は「斎」だろうと著者は指摘している。「斎」には穢れを祓うという意味があり、正鵠を射ていると思われる。
死者に関わって使われる箒は「魔祓いの一代長老格」と著者は言う。人が亡くなったときには地方によって、死人の上に乗せる、近所の家では門に横に置いて人が通らないようにし、葬列に箒持ちがつき、埋葬した塚上に逆さに立てられ、お棺が家を出るとすぐに掃き出し、戸を閉めたりするという。
このような人の死と箒の関係について著者は、
「おそらく、箒の機能の掃き出すところから、有難くないものを追い立てるお祓いの具として用いられているのだろう」
と記している。
さらに箒と並んで使われるのが鎌で、こちらは人が生まれたときにも死んだときにも使われる。子どもが誕生すると、かまを吊り下げたり、寝床のそばに置いたり、布団の下に敷いたりする。一方、人の死に対しては死者の体の上に乗せる、墓穴を掘る前に鎌で祓う、墓穴に吊るす、埋葬後の塚上に鎌の刃を上にして立てる等々が行われていた。
これも箒と同じように鎌の機能を考えれば、まものを切る道具として用いられ、生まれた子どもを守り、死者に取りつかないようにしたのにちがいない。
死者に関わる道具には針や鎌や刃物を棺に入れるほか、山椒の実や唐辛子なども入れる地域があるが、辛いものや臭いものによってまものをたじろがせる目的があったことも容易に想像できる。
このように見てくると、まものに対抗する武器は人間の生活に密着した食べ物や道具が使われ、しかも、人間にとって忌避したり脅威であったりするものが多く使われていることがわかる。それだけに、まものに対抗する武器として、なぜ使われたのか、現代人にもおおよそ見当がつくものが少なくない。
しかし、〝目から鱗〟的な武器もある。一例を挙げよう。胴上げである。野球や駅伝などでよく見るあの胴上げを、まものを追い払うのに叫び声や泣く、笑う、喚くは有効だがとしたうえで、著者はこう記している。
「突飛な行動、宙を飛んだり、ひっくり返ったりも、生きた人間ばかりでなく、誰をも仰天、飛びしさらすのである。今も野球選手が、日本一になった場合など胴上げされるが、もちろん負けた側の方は必要ない。勝って絶頂にいる者こそ、災いの元はつきやすいのであり、いわい(斎い)が必要なのである」
胴上げは〝祝い〟ではなく〝斎い〟であり、まものを追い払う儀式だったという。
著者が日本全国を巡り歩き、数々のまよけを集めた本書からは、意味がわからないままに私たちが行っている習慣や行為で〝目から鱗が落ちる〟快感が味わえるような〝まよけ〟に出会うことができるかもしれない。