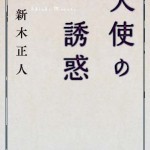- 2019-6-15
- お知らせ, 論創通信, 矢口英佑のナナメ読み
No.12『古本屋散策』
矢口英佑〈2019.6.10〉
書名を見て、本書が全国各地に点在している古本屋について、店の規模、店内の様子、客筋、取り揃えている古書のジャンル、店名の由来、店主のこと、街の様子等々を足で稼いだ、著者ならではの情報満載のガイド本と思った人もいたのではないだろうか。正直に言うと私がそうだった。
出版界の不況は目を覆うばかりで、新刊本を扱う街の書店が次々に消えていっている現在、古書店だけは例外、とはいかない。古書店街として知られた神田神保町交差点界隈、特に靖国通り沿いや一本引っ込んだ「すずらん通り」などを歩けば、一目瞭然である。櫛の歯が欠けるように、あったはずの古書店がなくなり、なぜかほとんどが飲食店に様変わりしてしまっている。
「以前は昼間、この界隈を歩いていれば、一人や二人、知った顔の編集者とすれ違い、声を掛け合ったものだったが、今じゃそんな人とほとんど出くわさなくなってしまった」とベテランの編集者が言っていたことが思い出される。
本書の書名から私が誤解したのには、著者が出版界事情に明るく、論創社からだけでも『古本探求Ⅰ~Ⅲ』『古雑誌探求』『出版業界の危機と社会構造』といった書籍を出していたからである。それだけに消えゆく古書店について著者による、謂わば〝墓碑銘〟が刻まれたものと勝手に思ってしまい、あまり意気があがらない気分で本書を広げた。
ところが、四六版で600頁に及ぶ大冊は、片手で持ち続けるには苦痛が伴うほど。そして、目次に並んだ200項目の表題を見渡せば、〝百花繚乱〟状況。私のような狭い領域に閉じこもっている者には、頭がくらくらするほど。本と、執筆者と、出版社にかかわる著者の語りが広角的な視野から展開されているのである。本書の各項の下に小さな数字が入っている。それは『日本古書通信』に2002年4月号から2018年11月まで連載した発表時期を示しているのだが、実に16年間に渡ったことがわかる。
本書は各地の「古本屋」を「散策」して、あるいは送られてきた古書店の出版目録を見て手に入れた本について語られた、著者の読書雑感集にほかならない。ただし〝雑感〟とはいえ、取り上げた書籍の内容はもちろん、執筆者や出版社、それに関わる他の書籍や人物、版元など、たぐり寄せた事象に至るまでの著者の知識は奥深い。そして、著者は「あとがき」で、次のように書いている。
「本書に収録した二百編は、意図せずして私個人の営みとしての読書史を形成している(中略)だがいささかなりとも、それが近代出版史や文学史へとリンクさせる試みであることは付記しておきたい。またこれらの一冊であっても、読者を喚起させ、読むという行為に誘うことができれば、それだけで幸いに思う」
この著者の思いは、本書に目を通した読者であれば十分に通じるのではないだろうか。近代出版史や文学史への理解も間違いなく進むだろう。なにせこれまで資料的にも掘り起こされておらず、時の流れに埋もれてしまっていた書籍や出版界の流れに分け入って、明らかにされた事実は一つや二つではない。
たとえば、「31 関根康喜=関根喜太郎=荒川畔村」では、
2004年4月に出版された『日本アナキズム運動人名事典』から書き始められ、関根康喜の『出版の研究』(成史書院)に及び、著者がこの書物を手にした経緯とその内容が記され、成史書院の発行者である関根喜太郎なる人物が書いた「発行者より」の関根康喜紹介が示されていく。こうして著者は関根康喜について、「国家規模で注目されるようになった、いわゆるリサイクル運動の推進者で、成史書院もまた国家と何らかのつながりのある外郭団体的性格を備えた出版社ではないかと思われた。だが関根康喜の「出版に関係して二十数年の経験」とは何か。また発行者の関根喜太郎は同一人物ではないかという疑問が残されたままであった」と疑問や疑いを残して、いったん引き下がる。ところが『日本アナキズム運動人名事典』を手にしたことで、その謎が解けていく。この事典では関根喜太郎、関根康喜では項目は立てられておらず、荒川畔村で「本名・関根喜太郎、別名・康喜」とあるのを知る。つまりこの3人は同一人物で、しかも大正13年に宮澤賢治の『春と修羅』を刊行した人物だったことが判明。著者は「『春と修羅』の発行が関根書店であるのは知っていたが、まさか『出版の研究』の著者によっていたとは思いもよらなかった」
とみずからの驚きを記している。
人物や本をたぐり寄せ、その実態に迫っていく記述には、まるで犯人探しのような面白さがあり、読む者もその醍醐味を味わうことになる。そればかりか、昭和10年代の日本の出版界の一端が明らかにされていて、どうやら著者の「近代出版史や文学史へとリンクさせる試み」は成功しているようである。
もう一例を挙げよう。「164 藤沢周平と『読切劇場』」である。
藤沢周平没後に見つかった無名時代の作品が平成18年に文芸春秋社から『藤沢周平未刊行初期短篇』として刊行されたことから書き始められるが、著者が触れたいのは『読切劇場』についてである。そして「編集者にしても、作家にしても、マイナーな存在で、出版業界や文学の世界の底辺を形成していたと考えられる。つまり藤沢もそのような倶楽部雑誌を足掛かりにしてデビューし、昭和三十九年から『オール読み物』新人賞に応募し始め、四十六年に「溟い海」で同賞、四十八年に「暗殺の年輪」で直木賞を受賞している。その後の藤沢の栄光からしても、それらの作品を封印していたのは習作であることに加え、倶楽部雑誌が発表の場だったことを自覚していたからだろう」
と記している。
著者にこのように書かれれば、『読切劇場』という雑誌を見てみたいとも思うし、藤沢周平の初期作品を読んでみたいとも思うのではないだろうか。著者がどこまでこうした読者心理を計算していたのかわからないが、実に巧みと言わざるを得ない。
「読者を喚起させ、読むという行為に誘う」著者の狙いは間違いなく果たされているようである。
本書の「1 近代古書業界の誕生」の冒頭で、著者は1990年初頭のバブル崩壊以降の出版業界の不況が相次ぐ出版社の倒産となって現れたと記し、「現在の出版不況は、出版業界の全領域に及んでいる。かつてとは比較にならないほど日常茶飯事のように起きている出版社の危機と倒産。これまでは潰れることのないとされていた取次の破産、無数の書店の閉店、廃業、それらの事実は書物の生産者としての出版社ばかりでなく、取次、書店といった書物の流通、販売のインフラの解体を告げている」とすでに17年前に書いていたのである。
著者の言葉は大げさでもなんでもなく、2019年の現在、出版業界の状況がさらに悪化しているのは言うまでもない。こうした出版界を知り尽くした著者が、それでも飽くなき古書店巡りと、古書との出会いを記録してきたのである。
本書から滲み出てくるのは、著者の出版物と出版に携わる人びとへの無限の愛おしさにほかならない。危機的な状況にある出版界への励まし、応援の証がここにはある。
(やぐち・えいすけ)
バックナンバー→矢口英佑のナナメ読み
〈次回『推理SFドラマの六〇年』2019.6.下旬予定〉
『古本屋散策』 四六判上製616頁 定価:本体4,800円+税