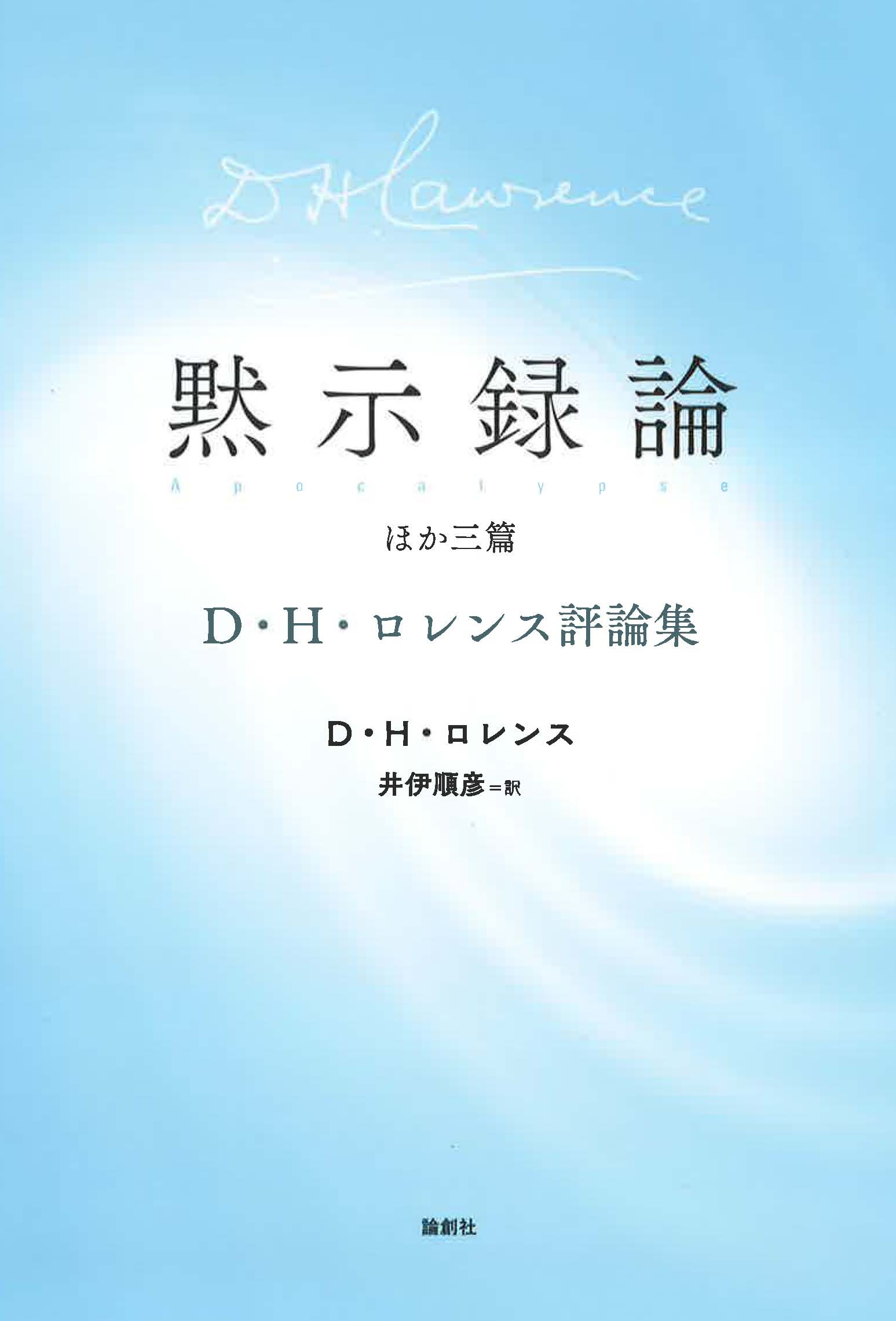- 2019-9-2
- お知らせ, 論創通信, 矢口英佑のナナメ読み
No.16『黙示録論 ほか三篇』
矢口英佑〈2019.9.2〉
本書の著者は書名にもあるようにイギリスの作家D・H・ロレンスである。この名前(デーヴィッド・ハーバート・ロレンス)から、年配の日本人なら、たとえ英文学などに親しんでいない人でも『チャタレー夫人の恋人』を思い浮かべる人がそれなりにいるのではないだろうか。それというのも、伊藤整が無修正版を1950年に出版すると、わいせつ物頒布罪として2カ月後に摘発、発禁処分を受け、1957年に最高裁判所で伊藤整と出版社側が敗訴という結果になった「チャタレー事件」として、一時期マスコミをにぎわせたからである。
そのロレンスが『新約聖書』の巻末に収められている「黙示録」を読み込み、これに基づいて持論を開陳しているのが本書の署名にもなっている「黙示録論」である。本書にはその他に「力ある者どもは幸いなり」「ドストエフスキー「大審問官」への序文」「民主精神」の3編が収められているが、ここでは主に「黙示録論」について書くことにする。
アポカリプスと呼ばれる「ヨハネの黙示録」には意味解読が難しい記述がそこかしこに現れ、それだけにその内容については、異論がいくつもある書物で、解釈が難しいと言われてきた。しかも使徒ヨハネではないヨハネが書いたとする説もあり、教会の歴史の中で排斥されたり、受け入れられたりしてきた厄介な書物とも言える。事実、ロレンスはこの「黙示録論」の冒頭で、
この一篇はあっさり片づけられる代物ではない。過剰なほど神秘の衣をまとった記述に、実のところ何が黙示されているのか、人は二千年近くも頭を悩ませてきた
と述べている。さらに私が戸惑ってしまうのは、ロレンスが続けて、聖書の言葉が体内に染み込んで、自分の感じ方や考え方に大きな力を与え、聖書の中身は忘れたはずなのに
ほんの一章でも読み始めると、腹立たしいほどしっかり〝憶えている〟ことを思い知らされる。しかも正直なところ真っ先に湧いてくる感情は、反発であり嫌悪であり憤懣でさえある。わが本能は聖書に憤っている
聖書への嫌悪感はさらに「黙示録」に転じられて、次のように表明される。
聖書全篇のうちもっともいまわしい一篇は、ふつうに読む限り黙示録だ
黙示録は、ごく幼いころから今にいたるまで、私の性には合わない。まず第一に、あの目もくらむばかりの心像表現は、とことんわざとらしく不愉快だ
これほど聖書に憤り、性に合わない黙示録にもかかわらず、ロレンスは死の3カ月前に「黙示録論」を完成させているのである。なぜなのだろうか、と思わずにいられない。それほど嫌悪感にとらわれる書物なら読まなければよさそうだが、彼はいかにも小説家らしく興味深いことを言っている。
一冊の書は測りがたい存在である限り命脈を保つ。測りつくされるや命脈を絶たれる。同じ本でも、五年後に読み直してみるといかに趣が異なるか、それは驚くばかりだ。(中略)受け手の心を動かす力を、しかも違ったかたちで動かす力を有するあいだは、生きていられるのだ——読むたびに受け手の目に違ったものに映る限りは
書物が書物として存在し得る価値について触れているのだが、なるほど、このあたりに嫌悪する「黙示録」に目を向けるロレンスの心情が透けて見えてくるようである。さらに彼はこうも言っている。「本とは貴重なもの、宝石や美しい絵のように貴重なものであり、その秘奥を見極めようと努めるたびに、ますます感慨深い経験をするのも可能だ」と。
これらの言葉とすでに引用した「黙示録」について触れた「この一篇はあっさり片づけられる代物ではない。過剰なほど神秘の衣をまとった記述に、実のところ何が黙示されているのか、人は二千年近くも頭を悩ませてきた」という記述に目を注げば、ロレンスによって「黙示録論」が書かれたのは、むしろあまりにも必然だったのである。
「黙示録論」は「黙示録」の注釈本ではない。「黙示録」の〝頭を悩ませる〟〝神秘の衣をまとった記述〟から導き出したロレンスの人間観、社会観、人生観にほかならない。しかもこの「黙示録論」が重要な意味を持っていると私に思えるのは、彼が語っている言葉の数々が聖書の世界のことでもなく、90年も前の世界のことでもなく、われわれが生きている「今」が直面している人類の危機に対する警告の書となっていることだろう。
わたしたちと有機宇宙(コスモス)は一体だ。有機宇宙は広大な生体(リビングボディ)であり、わたしたちはいまだその一部だ。太陽は一大心臓として、人の微細な血管にまで鼓動を伝える。月は微光を放つ一大神経中枢であり、その指令で人は永久に心身を震わせる
ロレンスの「わたしたち」とは、言うまでもないが、地球という球体とそこに身を置く人間たちを指している。有機宇宙に一つの星として存在した地球とそこに生きていたかつての人間に、彼は強い〝郷愁〟を抱いている。文明開化されていない世界、小さく狭苦しい機械のような〝無機世界〟からの解放、弱々しい暮らしのつまらない個人的なしがらみからの解放を求めている。つまりロレンスはキリスト教、個人主義、機械至上主義といった彼が生きていた時代を取り巻く状況を否定し、人間が人間として生き生きとした生存が可能となるのは、太陽や月などの宇宙の一部、大地の一部となって生きようとする自覚だというのである。
ロレンスはなぜこのように個人の自由や主義・主張を重んじた近代社会の精神のありようを否定したのか。彼はこう言う。
キリスト教と私たちの理想とする文明とは、長く続く逃避の一形態だった。こうした宗教と文明が際限なき虚偽と貧困を、物質の欠乏ではなくそれよりずっと危険な生命力の欠乏、すなわち今日わたしたちが経験している貧困を生んできた。生命を欠くよりパンを欠くほうがましだ。長く逃避を続け、そうして得られた唯一の成果が機械とは!
もうおわかりのように、ロレンスには科学や機械を重んじる近代性指向への懐疑というより、それも飛び越えて敵視さえ窺える。物理的な力と機械的な秩序を持つ非生命的な無機世界の重視は、人間存在の長くゆるやかな死の始まりと断じるのである。
だからこそ現代人は有機宇宙を取り戻せとロレンスは声高に言うのだ。どのように取り戻すのか。「一種の崇拝という手段を用いてこそ」太陽も月も取り戻せると。
宗教を超越した自然への崇拝と一体化こそが人間の至高の生き方へと導くという捉え方がロレンスの黙示録論のすべてと言っていいのではないだろうか。
人間の生と死も、愛も、孤独も、強者と弱者も、個人と集団、自由と拘束などへの言及もすべて、〝自然への崇拝と一体化〟が発想の根源になっている。
「黙示録論」の最後に置かれたロレンスの言葉は、21世紀に生きる地球丸の乗組員であるわれわれに重大な、そして象徴的なメッセージを残している。
私たちが欲するのは、自身の虚偽にして有機性を欠く縁、なかんずく金銭にまつわる縁を打ち破り、宇宙や太陽、大地、人類、民族、家族との命ある有機的な縁を再び定めることだ。まずは太陽とともに事を始めよ。あとは次第次第に生じるだろう
現在、われわれを取り巻く世界の状況は、ロレンスが言うように、人類は長くゆるやかな死に向かっていることを確信させるほど、国家間の政治的衝突、民族紛争、宗教上の対立、経済戦争、差別、抑圧、弾圧、さらには地球規模の環境破壊が絶え間なく起きている。しかも、それらはどれもエスカレートしてきているようにさえ映る。
あらゆる繋がり、関係において「命ある有機的な縁を結べ」というロレンスの一種の〝遺言〟は「ヨハネの黙示録」以上に21世紀に生きるわれわれに恐ろしいほどの予言を残しているのである。
最後に『黙示録論』の邦訳は、本書(論創社 2019)の井伊順彦訳を除けば、『アポカリプス 黙示録』(荒川龍彦・塘雅男訳 昭和書房 1934)と『現代人は愛しうるか(アポカリプス論)』(福田恒存訳 白水社、1951)があるだけだった。ただし福田恒存訳はその後、筑摩書房(〈筑摩叢書〉1965)、中公文庫((改訳版)1982)、「黙示録論」(ちくま学芸文庫 2004)といくつかの出版社から時を置きつつ出版されてきた。それだけ福田恒存訳が『黙示録論』の邦訳としては信頼されてきたのだろう。
本書の訳者である井伊順彦訳も訳出するにあたって福田恒存訳を参照したと「訳者あとがき」に書いている。ただし福田恒存訳のかなり重大な誤訳(あるいは翻訳上での解釈の誤り)も指摘していて、「先人の業績には敬意を表しつつ、今後の『黙示録論』研究の一助たればという思いで述べておく」と記している。
翻訳には多くの場合、誤訳は避けられない。それを正すのが後人の責務で、今回の『黙示録論』もそうだろう。ただ、どの研究領域でも同様のようだが、英文学の研究世界でも例外ではなかったようで、福田恒存訳『黙示録論』に大きな信頼が置かれてきていたようで、これまで誤訳の指摘はなかったようである。
本書の訳者・井伊順彦は戦前に昭和書房から出版された荒川龍彦・塘雅男訳にも触れながら井伊が指摘した福田恒存訳の誤訳部分の英語原文を「訳者あとがき」1頁の半分近くを埋めて示している。
『黙示録論』の解釈にも影響するかもしれない誤訳だけに井伊の訳者としての誠実な姿勢に敬意を表しつつ、今回、新たな訳文によって15年ぶりに『黙示録論』が論創社から刊行されたことを大いに喜びたい。
バックナンバー→矢口英佑のナナメ読み
〈次回『半径50メートルの世界』2019.10月上旬予定〉
『黙示録論 ほか三篇』 四六判上製256頁 定価:本体2,500円+税