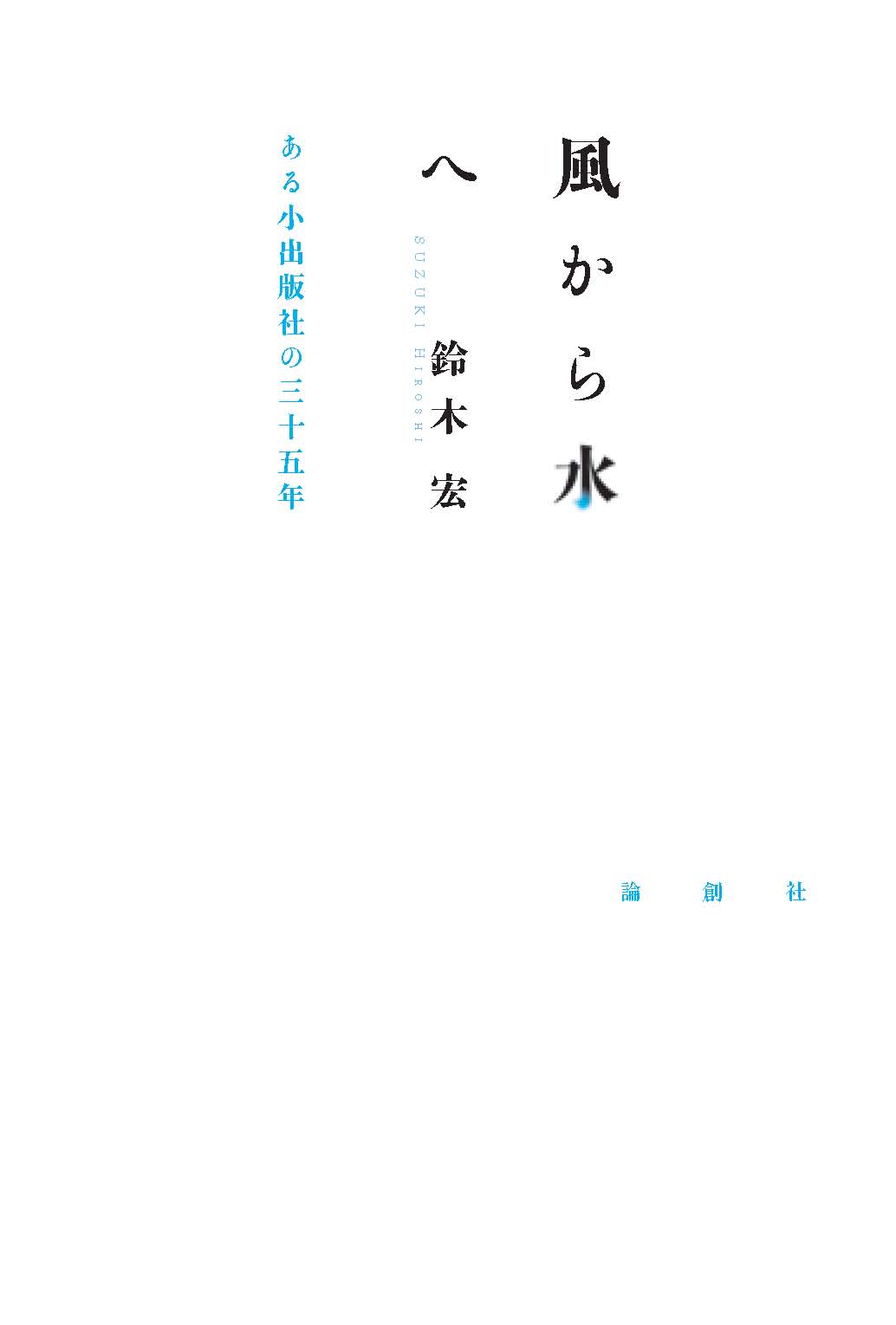㉚ 中野幹隆、『現代思想』、『エピステーメー』
小田光雄
前回の安原顕が企画し、創刊した特集主義の季刊雑誌『パイディア』は、彼も『決定版「編集者」の仕事』で述べているように、多くのスタッフや協力者たちに支えられていた。例えば、第6号までは編集者が安原となっていたけれど、第8号は鈴木道子、第11号は中野幹隆の名前が掲載されている。鈴木道子も安原が竹内書店を退社後、ほどなく辞めたようだ。それからどこへ移ったかは不明である。
中野幹隆は井出彰『書評紙と共に歩んだ五〇年』(出版人に聞く」9)に出てくる『日本読書新聞』編集長で、第11号の「特集 ミシェル・フーコー」を手がけたのである。鈴木宏の『風から水へ』においても、弓立社の宮下和夫、中央公論社の安原顕と並んで、三人の先輩編集者の一人として登場している。宮下に関して、すでに宮下和夫『弓立社という出版思想』(「出版人に聞く」19)が刊行されているので、ここでは言及しない。
鈴木にとって中野が先の二人と異なるのは、彼が駆け出しの「研究者」として出会ったことである。当時中野は『現代思想』編集長で、鈴木は大学院生だった。その修士論文の指導教官の三宅徳嘉から、鈴木が言語学とデリダの両方を「やっている」こともあり、『現代思想』がルソーの特集をするので、その『言語起源論』について書いてみないかと勧められたのである。デリダのことを中心とし、ルソーは『言語起源論』だけを読めばいいという提案だった。それで鈴木は引き受けることにした。
これを補足しておくと、東京都立大に赴任してきた足立和浩がデリダの『グラマトロジーについて』(現代思潮社)を翻訳し、これはルソーの『言語起源論』を論じていて、こちらも現代思潮社の小林善彦訳で、「古典文庫」の一冊として刊行されたばかりだったはずだ。
鈴木は原稿を仕上げ、締切の当日に中野を訪ねた。初対面で、原稿を差し出した。すると中野はその場で読み始め、それが終わると、いくつかの質問が出されたが、その時間が「試験」を受けたているような気分だったと鈴木は述べている。そして原稿は書き直しを要求されず、『現代思想』(1974年5月号)に掲載されたのである。そのこととは別に、鈴木は中野が亡くなった時に、ほとんど誰もいわなかったけれど、「エピステーメーが交換した」「日本の一九七〇年代以降の哲学・思想の動向に非常におおきな影響を与えた編集者だ」と語っている。
これは私見だが、その中野の転回点になったのは、先述の『パイディア』の「特集 ミシェル・フーコー」の企画編集だったのではないだろうか。実際にフーコーから送られてきたタイプ原稿の写真も収録した「デリダへの回答」も含めて、この特集に添えられた「〈思想史を超えて〉」というコピーは、これからの中野の向かう地平を告げているようにも思われるし、1980年代のニューアカデミズムへの回路の扉を開いたとも考えられる。この企画には豊崎光一と清水徹が深く協力したようで、前者は巻頭にフーコー論として、「砂の顔―アルシーヴと文学」を寄せている。その経緯と事情は不明だが、この論稿は本連載㉖で見たように、エディション・エパーヴから単行本化される。この「叢書エパーヴ」は豊崎と清水の他に宮川淳も加わっていたことから、後に鈴木もそこに誘われていく。
そして中野もこの一冊で竹内書店を去り、青土社へ移り、『パイディア』と同じ特集主義の『現代思想』を73年に創刊し、翌年に鈴木のデリダとルソーに関する論稿を掲載するのである。それからさらに中野は朝日出版社で、75年に『エピステーメー』の創刊に至る。その創刊準備号が手元にある。確かこの一冊は映画を見にいき、まだ時間があったので、書店に立ち因ると、これが見つかり、〇号ゆえか280円だったこともあり、買い求めたことを記憶している。
しかしこれは表紙からして、ミシェル・フーコー特集だとわかり、すでに何年か経っていたけれど、たちどころに『パイディア』のそれを想起させた。それに判型は一回り大きくなっていたが、デザインはともに杉浦康平が担当していたし、同じ編集者によると思われた。奥付を見ると、中野幹隆とあり、当時は『ユリイカ』のほうを読んでいたことから、彼が『現代思想』を経てきたことは認識せずにいた。内容はフーコーの「エピステーメーとアルケオロジー」(白井健三郎訳)、『言葉と物』を読むと付された、蓮実重彦による「ディスクールの廃墟と分身」で、同じフーコー特集でも「〈思想史〉を超えて」が「エピステーメーからアルケオロジー」へと移行していることが想像された。だが私にはこの雑誌が肌に合わず、時々関心のある号を買っただけで、終刊となった感が強い。
それは鈴木と中野の関係も同様だったようで、これは中野が哲学書房を創業してからだと推測されるが、二回ほど何の連洛もなく、鈴木を訪ねてきて、飲んだことが『風から水へ』の中で語られている。鈴木は自らを、中野における「特別な利害関係のない、適当な距離にある友人」と定義し、中野も「たわいのない話をする」ことを必要としていたのかもしれないと述べている。その時期に中野は独立して経営の問題で苦しんでいたと仄聞している。きっとそんな時に、中野は鈴木を訪ねていたにちがいない。
—(第30回、2018年8月15日予定)—
バックナンバーはこちら➡︎『本を読む』
《筆者ブログはこちら》➡️http://d.hatena.ne.jp/OdaMitsuo/