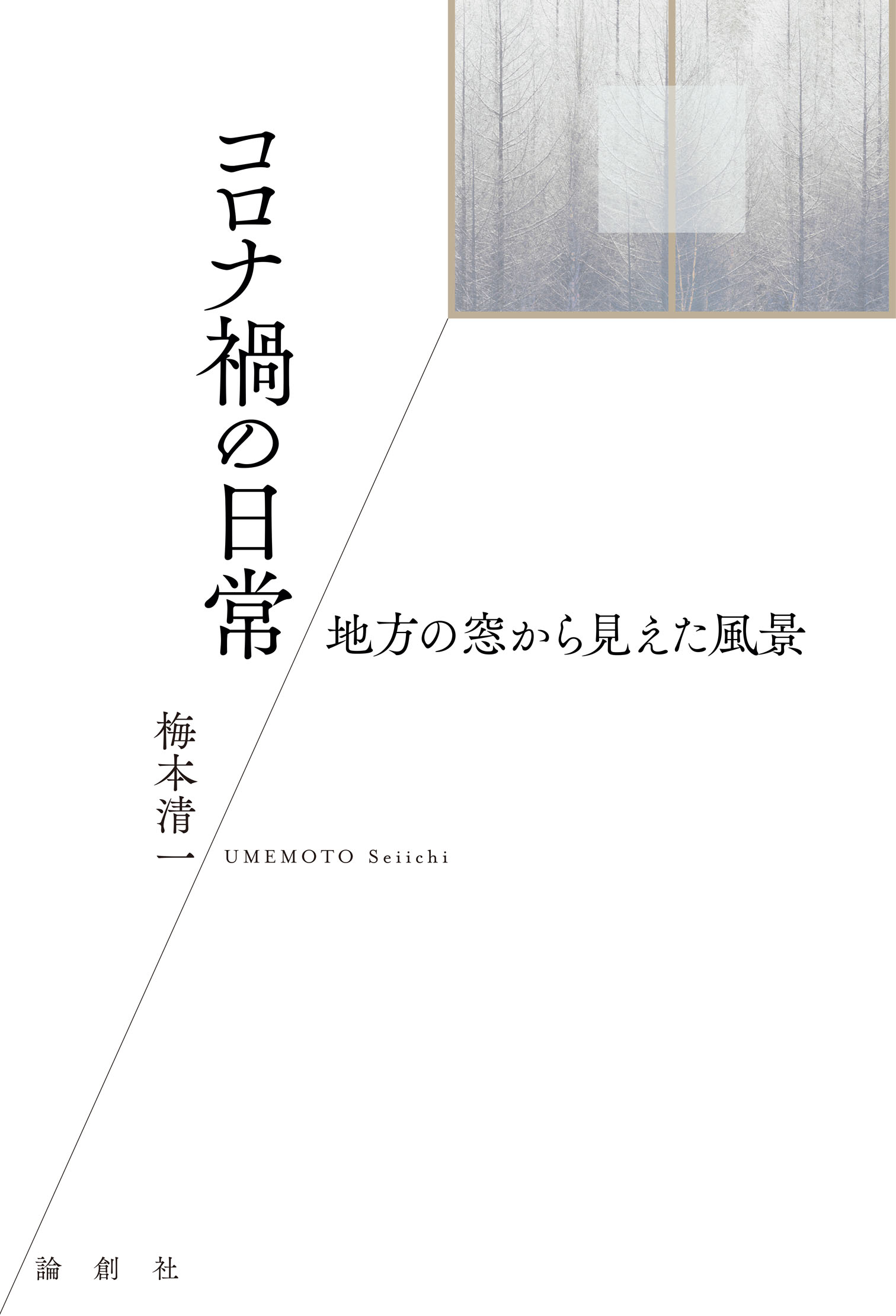- 2021-1-18
- お知らせ, 論創通信, 矢口英佑のナナメ読み
No.36 『コロナ禍の日常』
矢口英佑〈2021.1.18〉
コロナに襲われて誰もが苦しんでいる日本、そのコロナ感染列島を本書は富山という地方都市からの日常を通して発信している。ここには大都市圏に住む者には見えなかったさまざまな著者の目に映った富山地域の状況が伝えられていて、それだけにコロナに襲われた「地方に住む者」の思いが強くにじみ出ている。
著者の梅本清一は本書を〝コロナ禍日記〟と位置づけているが、「はじめに」で記すように「日々の私生活を綴ったものではなく、視点はあくまでも地域社会の中で見た風景」で、「今、目の前に広がる地域の日常の風景や地域から見えた日本、自身の思うことを綴ることに徹した」という。
現在、日本はコロナ第3波に襲われていて、予想を遥かに超えて感染者数が激増している。この間にコロナに関する書物がどれくらい出版されたのかその正確な数を知らないが、切り口は多様だと思われる。しかし、管見するところ、本書のように地方からコロナ襲来とその影響、その地域に住む人びとの生活についてさまざまな事象を取り上げ、切り込んだ一書はないように思う。
大手マスコミ、メディアは大都市圏での生活者に的を絞ったようにニュースを取り上げる傾向が強い。そのため、それらの情報がすべてと思いがちな人びとが多いだけに、コロナ禍の地方の現状を伝えている本書はきわめて貴重である。かく言う私などもコロナに襲われている地方にまで思いを寄せて現状を見ていなかったわけで、我が視点の欠如を本書によって教えられた。
当然のことだが、コロナは大都市圏の人びとだけに襲いかかるわけではない。人間が生活する場所であれば人種、宗教、地域、主義・思想、経済力の有無、産業活動の違い等々になんら関係なく、皮肉な言い方をすれば差別や区別など存在しない。
だからこそ、「地方の窓から見えた」コロナが大都市圏と変わらない災厄を地域の人びとの生活にも及ぼし、暗く覆いかぶさっているのである。その意味では、本書は〝富山発コロナ観測ドキュメント〟と言っていいだろう。
本書は昨年3月から8月までの「日記」と著者が位置づけているため、すべて執筆された日にちが記入されている。しかも、どれも新聞のコラム記事のようで、ちょっと目を引きそうな見出しが付けられている。そして、それらがそのまま目次となっている。したがってこれらの目次を追えば、読んでみたいと思う項目が一つや二つに止まらないのではないだろうか。たとえば、私の関心に照らせば、
4月:「激震の日――県内初の感染者」、「哀れ旬の幸――タケノコよ、海の幸よ」、「地域医療の崩壊――マンパワー不足心配」、「首長よ――政治家か、行政のトップか」
5月:「デマ、中傷――隣人を思いやる心を」、「世界と富山――アフターコロナのリーダー」、「首都機能――再び移転論議を」、「10万円給付や支援策――自治体に権限、任せよ」、「民生委員――会えなくても、支え合う」
6月:「本当に困っている人――相談や調査の意欲もなく」、「観光地――地元を大切にしたい」、「九月入学――地域の声を聞いたか」、「就農――逆風にめげず求む若者」、「酒米――越中に美酒あり」
7月:「暗い7月スタート――しわ寄せは弱い者に」、「「東京問題」と都道府県――国と地方自治体の責任」、「「GoTo」は一律「No」――地方大権の時代だ」、「改めてコロナの怖さ――「自分さえ無症状ならいい」」、「底なしの生活苦難民――社福協に殺到、外国人も」
8月:「経路不明者が増加――県境越えの往来伴い」、「コロナ禍のお墓掃除――増える墓守の不在」、「安心と不安な店――県の判断で「見える化」」、「コロナ後に何が生まれる?――ペストの時代は?」、「首相辞任――地域・地方はどうなる」
といった項目になるだろうか。
いずれもが新聞のコラム欄を思わせるのは、著者が北日本新聞社記者から取締役編集局長、論説委員など、長く新聞人として社会を見つめ続けてきたからだろう。
「目の前に広がる地域の日常の風景や地域から見えた日本、自身の思うことを綴る」視点にブレはなく、常に弱者への温かな眼差しは読むものの心を和ませてくれる。たとえ取りあげている話題が暗かったり、怒りを覚えたりする内容であっても……。
たとえば、弱者への眼差しとして「介護報酬引き上げ——コロナで負担は利用者に」では、ケアマネージャーの世話になっている自分の母親のことから説き起こす。特別養護老人ホームやデイケアサービス事業を行なう事業所(法人)はコロナの感染対策で経費が増加したため、国に経営支援を求めた。すると国は介護報酬の引き上げ導入を認めたというものである。
これはまさに金を支出する側の「受益者負担」という常套用語、手段とも言えるもので、著者が「実に変な話だ」と憤るのは真っ当すぎるほど真っ当だろう。「病院はコロナ対策費で大変だから、診療費アップ。飲食店は料金を上げていいよ、と通達するようなものだ」と言うのもその通りで、弱者へのしわ寄せ、差別を国が目立たないように行なっているのである。つまり通院する国民は多いだろうし、飲食店へは言うまでもない。現在のコロナ禍で、これらの機関や商業店にこのような「受益者負担」論理を持ち出したなら、政権が持たないことを国は十二分に承知しているのだ。
結局、この通達に当事者たちはどう対応しているのか。
「同じ地域の包括支援センター内でも、アップする事業所とサービス維持、高齢者に負担をかけられない、と現状のままの施設も」というのが現状のようである。だからこそ著者は、「コロナ禍は災厄、ここは一時的だ。国が負担すべきである」と内にやりきれない怒りを秘めながら結ぶのである。
また国と地方自治体との関係にも著者は強い関心を抱き続けていて、それは新聞人として過ごすなかで培われた信念に裏打ちされたものだろう。それが現在のコロナ禍で、著者には更に鮮明に見え始め、今後の日本という国の形はどうあるべきかを語らせているようである。
たとえば、「「Go To」は一律「NO」——地方大権の時代だ」では、かつて「地方分権」の要求が地方から沸き上がったが、「今は昔」となってしまったことから説き起こし、政府の経済活性化政策の「Go Toトラベル」に切り込んでいく。
全国一斉スタートをもくろんだ安倍政権だったが、感染者多数から東京都を除外した時期に富山県内では、先ずは隣県同士での「Go Toトラベル」から順次始め、全国一律にする必要はないとの考え方が主流だったという。
富山県と言えば、それなりに観光資源もあり、遠方からの観光客の来県は観光業関係者には歓迎すべきことだったはずである。にもかかわらず「安全性や市民感情に配慮した」からこその結果だった。著者は言う。「観光地の旅館やレストランの社長は、東京からのお客に期待する。だが、従業員や市民を守る観点からして、国の姿勢には懐疑的なのだろう」と。
地方の経済活性化を推進したい国は「Go Toトラベル」は、当然、全国一律、一斉実施の方向だった。しかし、地方の住民たちはそうは考えなかった。つまり経済より〝身の安全〟を優先させていたのである。
著者が言うように確かに「国の政策の大部分が「国民=住民」へのサービスである。そうだとすれば、その地域の住民の要望や思い、感情を身近に捉えられるのは国ではなく、地方自治体にほかならない。「霞が関や政府には、遠い地方が見えない」という著者の言葉に国がどう反応するのか是非とも聞いてみたいものである。
2021年1月、猛烈なコロナ第3波襲来のなかで、政府はようやく緊急事態宣言を発出した。しかも一都三県の知事たちからの強い要請で。さらに東海、関西地域の知事たちからの要請にも。
いみじくも「霞が関や政府には、遠い地方が見えない」という著者の言葉がはっきりと証明されてしまった。そして今の日本は、国の形として「ポストコロナは「地方集権」、もっと言えば、「地方大権」だと確信する」著者の言葉が現実化しつつあるようだ。
(やぐち・えいすけ)
バックナンバー→矢口英佑のナナメ読み