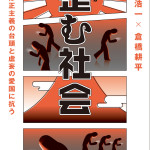- 2020-5-1
- お知らせ, 論創通信, オイル・オン・タウンスケープ
浮浪する根拠地───町屋風景 第一号(前半)
中島晴矢
《町屋風景》2020|カンヴァスに油彩|410 × 318 mm
初めて油絵を描いたのは、高校の美術の授業だった。
友人の顔を描くという課題で、私は美術室でたまたま席が近かった寺田くんの横顔を描くことにした。寺田くんは「金正日」というあだ名の持ち主だった。ルックスがよく似ていたからである。ややずんぐりとした背格好にメタルフレームの眼鏡、何よりチリチリの毛髪に、件の総書記の面影が刻印されていた。北朝鮮が耳目を集めていた当時、無遠慮な中高一貫の男子校で、寺田くんは入学直後から必然的に「正日」、なんなら「ジョン」と親しげに呼ばれていたのだ。
そんな正日の横顔を見つめながら、気の向くままに筆を走らせていく。そういえば、私に初めてほんものの「セックス」を教えてくれたのも彼だった。
同じクラスだった中一の時、学校帰りに正日の家へ寄ったことがある。共働きの両親が出払った自由が丘の瀟洒なマンションの一室で、その大人びた風貌通りなのか何なのか、パソコンと性にやたら精通していた彼は、海外のポルノサイトを見せてくれたのだ。
「これが女性器で、こうやって挿入するんだぜ」
正日はしたり顔で、画面いっぱいに映し出された無修正の結合部を指差す。いきなりの洋モノである。むき出しの性器とあからさまな嬌声に面食らう。そのあまりに動物的な媚態から、どこか別世界の儀式のようなものを連想しながら、しかし性的好奇心に駆られて青白く発光するディスプレイをぼんやりと眺める私たちは、むろん二人とも童貞だった。
そんなくだらない雑念が浮かび上がる彼の相貌を、授業時間内でなんとかカンヴァスに写し取る。これまでに私が描いた油絵は、その一枚きりである。
*
油絵を描いてみよう、と思った。
私は油絵に関して全くの素人だ。アーティストという肩書きだが、専らつくってきたのはいわゆる現代美術であり、絵画や彫刻をアカデミックに学んだ経験はない。大学も美術系ではなく文学部だった。唯一芸術を学んだのは美学校だが、その極めて私塾的な教場で、基礎的な技法を教わったことはない。だから私は、ろくにデッサンすらとれないのである。
それでも美術なるものに携わっているのは、少なくとも私にとって、それが最も懐の深いジャンルに感じられるからだ。自分がその都度やりたい表現を行い、それらが一つひとつ積み上がっていった先に、「様々なる意匠」を受け入れてくれる器としての〈アート〉があった。
主につくってきたのはコンセプトを軸に置いた作品だ。映像や写真、オブジェ、平面、パフォーマンスなど、要するにメディウムは問わない。現代美術の始祖がマルセル・デュシャンであるとすれば、そのテーゼの一つには、レディメイドに代表される「手癖の排除」がある。工業製品である便器にサインを施しただけで、そのまま展示台に乗せてしまうこと。そうした手つきを念頭に、多様なコンテクストをサンプリングしながら作品を編んできた。ただ、その手法にある種の硬直を感じ始めていたのも事実だ。そんな折に、油絵を描いてみたいと思ったのである。
引用に目配せせず、手癖を残したまま、カンヴァスに絵具を乗せていく。それが裸を見られるような羞恥を伴うことは容易に想像できた。だが、裸を晒すことこそあらゆる芸の根幹ではなかったか、と自分に言い聞かせる。モチーフは風景と決めていた。それは決して自然の情景ではない。市街の風景だ。そもそも「風景」とは、〈風景画=ランドスケープ〉を起源とし、そこから内的な眼差しによって、徐々に獲得されてきた概念である。その道程を遡るようにして、風景画、とりわけ〈町並みの風景=タウンスケープ〉を描く。それも、ほとんど丸裸の画力で。
頭の片隅にいるのは、大正から昭和を生きた画家・長谷川利行だ。日暮里の寺や浅草の木賃宿を根城に、放浪しながら下町の風景を描いた。もともと短歌を詠み、齢三十にして上京。そこから独学で画家を志すようになった利行の筆致は、文人画家の系譜に連なっている。文人画とは、職業画家ではない文人が余技で描いた絵画を指す。恥ずかしげもなく言えば、非専門家が自らの娯しみのために制作するという点において、私が描きだそうとしているのもまた、いわば文人画みたいなものなのかもしれなかった。
*
真っ先に頭に浮かんだのは、油彩道具の詰まった木箱のセットだ。
だが、調べてみると思った以上に値が張る。であれば、逆に最安値でいいと高を括り、アマゾンで「油絵具ファースターセット」なるものを注文してみた。翌日に届いたのは、予備校生が持つような安っぽいプラスチックのキャリングケース。そこに、12色セットの油絵具、ペーパーパレット、透明な液体の入った数本の小瓶、ペインティングナイフ、そして大中小の絵筆が詰め込まれていた。
浪人時代に戻ったような心持ちで、プラスチックケースを提げ神保町におもむく。靖国通りを折れて少し、雑居ビルの3階にあるのが美学校である。同世代のアーティスト2人と「現代アートの勝手口」という講座を立ち上げ、講師を務めるようになって初年度、その修了展の日だった。受講生は、「学歴・年齢・国籍 不問」という美学校のコピー通り、年齢もキャリアも様々な人が集まってくれた。彼・彼女らが、1日限りの修了展を自主的に企画したのである。
どういうわけか、授業の流れで講師も新作を出品しなければならなかった。思案した挙句、描こう描こうと思っていた油絵を出すことに決めていたが、会期までにまとまった時間が取れず、描き出すことすらできずじまい。結局、展覧会当日にライブペインティングをしてしまうことにした。もはや投げやりである。でも、講座名の通り、各人がそれぞれ「勝手」にやればいい。私は会場で油絵を描く、それでいいじゃないか。
美学校に着くと、まだ生徒たちが作品の設営中だった。展示初日、オープン前によく見る朝の光景。昨夜は、講師の一人である齋藤恵汰も含め、屋上の掘っ立て小屋に泊まったのだという。徹夜で搬入と設営を済ましてしまうつもりが、一晩中酒盛りをしていたそうだ。まだ作品を持ってきていない生徒もいて、ぽっかりと空いたままの壁面もあるが、寝不足と二日酔いで重い足を引き摺りながら、みんな作業に勤しんでいる。
そんな中、私には部屋の一角があてがわれた。早速、教場の奥から年季入ったイーゼルを引っ張り出して設置し、例のプラスチックケースを足元に、そしてこちらもアマゾンで購入したF6号のカンヴァスをイーゼルに立て掛ける。カンヴァスは角に若干シワが寄っており、張りが弱い気もするが、安物だから文句は言うまい。ライティングをしていた生徒に照明を当ててもらい、継ぎ接ぎだらけの丸椅子に座ると、見世物になったようで悪い気分ではなかった。
なんとか展示空間が完成し、開廊時間を迎える。私は各道具のシュリンク包装を破るところから始めた。油壺もオイルも使い方が全くわからない。「正日」を描いた時の手順など、何一つ覚えていなかった。
受講生の中には美術大学の油画科に通う学生もいるが、ぱらぱらとある来客の対応に忙しそうだ。恵汰は向こうの部屋で、来場者にお茶を淹れて感想を聞き出すというパフォーマンスをしている。そこで、もう一人の講師であるペインターの藤城嘘に油絵の心得を訊ねてみた。
彼は今回、アクリル絵具で描かれた小ぶりな平面をきちんと用意してきていた。マゼンタや紫で構成された地に、曖昧に崩された「現代アート」の文字が散らばる。画面中央には羽の生えた少年(少女?)のキャラクターが据えられ、藤城作品のキーアイコンである〈目〉が灰色に輝いている。四角く縁取られた耳は黒々と塗り潰されており、梯子段のような描線が降りているから、おそらくそこが「勝手口」なのだろう。
「一般的には、初めに薄い黄色や茶色で下描きをして、そこから濃い色を乗せていくイメージですね」
嘘くんはややあきれながらも、一から丁寧に教えてくれる。油壺の使い方、描画油と筆洗油の差異、他にも用意すべきもの。描き出しから仕上げにかけて、オイルの調合を変えていく必要があるらしい。だんだん乾性油の量を増やし、テレピン油の割合を減らしていかねばならないそうだ。
「そうしないと、絵が乾きませんよ」
「え、乾かないの?」
「もちろん美大受験生みたく、速乾性のメディウムを混ぜるなんてやり方もありますが、絵肌が脆くなってしまうのであまりお勧めはできません。少なくとも数日間は置いておいた方がいいですね」
「そうだったのか……今日持って帰ろうと思ってた」
「それは無理ですよ」
と、嘘くんは苦笑する。
「例えば厚塗りだと、油はなかなか揮発しません。だから表面は乾いていたとしても、その内側の絵具は何年も、場合によっては何十年も乾かないものがあるくらいです」
「何十年も……」
ずっと乾かず、皮膜の内部にどろりとあり続ける絵具を想像してみる。当たり前に、油絵とは〈物質〉であり、絶対的な〈他者〉なのだった。
*
嘘くん曰く「道具が充分ではない」ということで、ライブペインティングを放り出し、買い出しに行くことにした。美学校から最寄りの画材屋は、すずらん通りを挟んで三省堂書店の向かいにある明治創業の老舗・文房堂だ。
そういえば、初めて展覧会をしたのも文房堂だった。重厚なファサードを備えた建物の4階にある、広い貸しギャラリー。そこで、通っていた美学校のクラスの修了展があったのだ。二十歳の時である。
出品したのは、白地に黒一色で偏執的に描き込んだ、巨きなペン画だった。その頃かぶれていた『ガロ』的なタッチで、身体や性器をデフォルメしたモチーフが凝集する平面である。タイトルは《マスターベーション曼荼羅》。文字通り、後ろ暗い青年期のリビドーだけで描き上げたような作品だった。
会期終盤、その作品はふらりと立ち寄った男性に、なんと言い値で売れてしまった。背広姿で年配のその人は、学生だった私からすればかなりの大金をその場で支払うと、作品は後日、社の方に持ってきてくれればいいと言う。差し出された名刺を見ると、とある美術系の出版社の社長ということだった。
後々痛感するように、それは言わずもがなビギナーズラックに過ぎなかったが、やはり舞い上がる気持ちはあった。お金云々ではなく、拙いながら自分の表現が学校や仲間内の〈外部〉に届いたように思えたことが、何より嬉しかったのだ。その快感に浸って以来、いよいよ人生の舵をアートに切って、気づけば引き返せないところまで来てしまっているのだけれど。
1階の油彩コーナーで、筆洗器やオイル類を買う。
オイルは、文房堂のオリジナル商品で「描き出し」「描き込み」「仕上げ」とラベリングされたものがあった。テレピンだとか何だとかが、それぞれに程よく調合されているのだろう。多分、これで「充分」なはずだ。
美学校に戻ると、受講生たちの友人を中心とした来客で賑わっていた。彼らに私が講義の中で出したのは、「根拠地を示す」という課題だ。「根拠地」とは、例えば故郷や家庭、性別、あるいは人種など、その人にとって自らの足場になっていると思える要素である。その提示こそが、表現者として出立するにあたっての第一歩だと考えるからだ。
思えば私もまた、「根拠地を示す」ことでアーティストとしてデビューした感がある。田園都市線沿線のニュータウンを出自とする私は、その平穏でつるりとした風景に対し、非日常の祝祭を繰り広げるサブカルチャーとして、プロレスをぶつけた。東京での初個展で発表した《バーリ・トゥード in ニュータウン》という映像作品である。書き割りのような郊外の町並みを背景に、延々とプロレスを続けることで、自身の根拠地を逆説的にリプレゼントしたものだ。
「勝手口」の修了展では、自分が出した課題を回収する形で、現在の根拠地を示すことにした。もちろんニュータウンをはじめ、これまでにもいくつかのルーツを作品化してきたが、おそらく芸術は、その時々に自らの〈いま・ここ〉を記述することができる最良の手段の一つである。浮浪して刻み続ける原風景───そんな私にとっての根拠地は、2年ほど前に引っ越してきた、荒川区の町屋だ。
(なかじま・はるや)