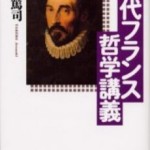- 2021-10-6
- お知らせ, 論創通信, オイル・オン・タウンスケープ
濹東のオルタナティヴ───大川水景 第七号(前半)
中島晴矢
《大川水景》2021|カンヴァスに油彩|1, 000 × 652 mm
スカイツリーラインなる呼称を冠された東武鉄道に揺られ、北千住から牛田、堀切、鐘ヶ淵と、荒川に沿って進んでいく。すぐ反対に流れるのは隅田川で、鳥瞰すれば、二つの河川に挟まれた瓢箪みたいな形の一画。そのくびれた部分を下った先が東向島である。台東区の側からは白鬚橋を渡って真っ直ぐだから、文字通り、隅田川の向こう岸にある島のような場所なのだった。
駅を降りて線路伝いに歩むと、この街の目抜きである大正通りにぶつかる。そこを右に折れて、墨田三丁目交番の脇道に這入れば、いよいよ迷路の始まりだ。鐘ヶ淵駅近辺に至るまで、毛細血管のごとく張り巡らされた路地が、縦横無尽に続くことになる。路傍には、古めかしい飯屋や商店、トタン貼りの木造家屋、空き地、鉄を打つ音の響く町工場等々が並び、庭先では鉢植えの草花が生命力を誇示している。うねうねと曲がりくねった隘路が方向感覚を失わせ、途端に自分がどこにいるのか分からなくなった。
ここはかつての私娼街、寺島町「玉の井」だ。言うまでもなく、永井荷風の小説『濹東綺譚』の舞台であり、荷風はこの陋巷を「迷宮(ラビラント)」と形容した。じじつ、往時の路地口には「ちかみち」や「ぬけられます」といった看板が掲げられ、その奥には“銘酒屋”と呼ばれる売春宿が犇いていたという。吉原とは異なる官未公認の岡場所で、そこら中に溝が流れ、蚊が群がり、「ちょいとちょいと」と袖引く声の溢れる、場末らしい歓楽街だったようだ。
沿革としては、大正の頃、国の取締りが厳しさを増し、さらに関東大震災が決定打となって、”浅草十二階”こと凌雲閣下の銘酒屋が軒並み立ち退く運びとなる。そうして流れ着いたのが、隅田川を越えた「玉の井」だった。当時、東京市外だったそこは、亀戸と共に私娼窟として黙認されたのだ。
むろん、すでに東向島にその面影はない。だいたい、この一帯は東京大空襲で灰燼に帰している。戦災後は街区を少しだけ移し、売春防止法の施行まで、いわゆる赤線地帯として営業が続けられたそうだが、それも今は昔。現在では、そこここに新築の住宅が立ち並ぶ、静かで一般的な下町の風景と相成った。とはいえ、やはり路地の造り自体は変わらない。「ぬけられます」の掲示がなくとも、依然として「迷宮(ラビラント)」はその相貌を湛えている。
*
もともと、私は下町にほとんど縁がなかった。
東京を大雑把に分ければ、山の手と下町の二つになる。横浜郊外のニュータウンに生まれ、山の手に通った私にとって、隅田川はおろか、東京の東側を訪れるのすら稀だった。私の中の下町は、どこか遠くの方にあるイマジナリーな空間でしかなかったのだ。
だが、いつからか下町に惹かれるようになった。現に今も荒川区に住んでいるし、これまで住んだ地域の中で一番しっくりきている。もちろん、そこは自分の地元(フッド)とは言い難い。でも、なぜだか下町は私を慰撫してくれるのである。
おそらく、その感覚の根っこには、西東京に対するここ十年来の諦念がある。再開発が加速し、入れ替え可能な都市になっていく東京の姿を、私は見ていられなかったのだ。それでも、何人かの友人たちみたいに、地方や農村へ引越すことはそう叶わない。あくまで東京の内部に安らげる土地を求め、逃げるようにしてさまよった先に、ようやく下町を〈発見〉したのである。
ただ、私は下町において余所者に過ぎない。勝手な幻想を抱いているだけの、いわば素見客(ひやかし)だ。そこで実地に生きる者は、決してそこを〈発見〉したりしない。その矛盾を自覚した上で、それでもなお、下町を好いてもいいはずだと居直らずにはいられなかった。要するに、私は下町の魅力に気づくのが遅かったのだ。したがって私の知る下町の風景は、東京スカイツリーが建って以降のものに過ぎない。
きっかけをくれたのは、やはりアートだった。東東京にはたくさんのオルタナティヴ・スペースが立地しており、自然と足を運ぶ機会が増えていったからだ。
オルタナティヴ・スペースとは、美術館でも画廊でもない、それら既存の機関から自立したアート・スペースを指す美術用語である。その独立性ゆえに、作家や企画者にとって、実験的な表現の受け皿として機能してきた空間だ。
私もまた、オルタナティヴ・スペースに携わってきた作家の一人だ。初個展からこのかた、本棚の隙間、地下街の一室、取り壊し前の廃ビル、知人宅、空き倉庫、地方の古民家といった場所に、壁を立て、プロジェクターを打ち、安いピンスポを取り付けて、無理やり展示を行ってきた。私の世代のアーティストは、自ら場を開拓し、アトリエやギャラリー、シェアハウスなどを運営する者が少なくない。コマーシャルギャラリーには手が届かず、貸画廊を借りる甲斐性もなかった私たちは、寄り集まり、協力し合って何とかアートを続けてきたのだ。
とにかく、そうして私はイーストサイド、とりわけ墨田区へ通うようになる。墨田は東京の中でも家賃が安く、都心へのアクセスも悪くない。町工場跡や老朽化した長屋など、空き物件が多かった。さらに、1997年にオープンした「現代美術製作所」を先駆けに、数々のスペースやプロジェクトが堆積している。だからこそ他ならぬ「濹東」に、独自の文化が形成されてきたのである。
そんな墨田のスペースへ出かける際、私はしばしば押上駅から歩いて行く。スカイツリーの根元、駅直結の商業施設「東京ソラマチ」を抜けると、周囲には真新しいマンションが立ち並んでいる。だが、住宅街へ一歩足を踏み入れれば、そこはまだまだ下町らしい町並み。駅で言えば、この押上、曳舟、そして小村井に囲まれた辺りが、馴染みのスペースが集合するエリアだ。
北十間川沿いを行き、十間橋通りで左折、さらに路地を進んだ先には「あをば荘」がある。中学校と都営団地に挟まれた、文花という地区の一画。小さな印刷工場の隣にある長屋の一棟で、友人が運営メンバーだったそこには、よく展覧会を見に行く。今は真裏の土間もホワイトキューブに改装されて、複数のスペースが代わる代わる入居する、アートコンプレックス「文華連邦」になっている。
そこから少し足を伸ばせば、プレス工場をリノベーションしたシェアスタジオ「float」や、トタンの壁面にカラフルなグラフィティの描かれた「spiid」、小さな植物園のような温室の長屋「Green thanks supply」など、多彩な場と人に出くわせる。また、キラキラ橘商店街という昔ながらの活気あふれる通りには、絵画の展示を軸とした「gallery TOWED」や、仮面のみを扱う風変わりな店「仮面屋おもて」が立地。商店街の脇道には、シェアカフェ「halaheru」があって、そこを営み、自身も「muu muu coffee」としてカウンターに立つアユムさんは、けん玉がすこぶる上手い。店の前には、いつもけん玉のプレイヤーが集っており、草の根のコミュニティを編んでいる。そういえば、この辺の路地では子どもたちがよく懐かしい遊びに興じており、路面にケンケンパの白い円がチョークで描かれていたりする。都内でなかなか見られなくなったその光景は、車が入り込めないほど狭い路地によって保たれているのだ。
おまけに、墨田にはアート関係の友人が多数住んでいた。だいたいどこかのスペースの展覧会やイベントなんかでみんな集まる。その流れで、焼肉屋「東大門」や居酒屋「かどや」あたりで軽く打ち上げをしてから、誰かの家に上がり込んだ。大抵が木造の長屋で、家賃が破格に安い。風呂がなく、近所の銭湯に通っていたりするが、それなりに広くて、作品制作もできる。そうした一間で、芸談と猥談を肴に夜更けまで酒を飲み、雑魚寝をして、翌朝二日酔いの頭を抱えたまま、よろよろと家路に着くのが常だった。
当然、斯様に挙げたスペースはこの界隈の極一部に過ぎない。本当はもっと多様な生態系があるのだろう。そもそも墨田は、ものづくりが盛んな、職人気質の街だ。それだけに、昔からこの地に住む人々も、若いアーティストやクリエイターを受け入れて、懐の深い共同体を耕すことができたのだと思う。
平成最後の夏には、東東京のオルタナティヴ・スペースを全面的に使って、グループ展を開いた。美学校「アートのレシピ」卒業生有志でつくり上げた、ちょっとしたツアー型の芸術祭。私は三ノ輪にある「space dike」で作品を発表したが、オープニングパーティの会場は、墨田区の京島、明治通り沿いに位置する「sheepstuido」だった。私はその日その土間で、なぜか妻と婚姻届にサインも書いている。
その「sheepstuido」も既になくなった。オルタナティヴ・スペースは、経済的にも運営的にも、まず継続自体が難しい。多くの場合、それは咲いてすぐ散る徒花なのだ。ともあれ、私はこんな風にして、慣れない下町と関係してきたのである。
(なかじま・はるや)