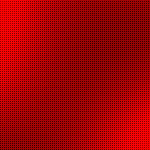- 2021-7-1
- お知らせ, 論創通信, オイル・オン・タウンスケープ
田園都市の憂鬱───港北ニュータウン 第六号(前半)
中島晴矢
 《港北ニュータウン》2021|カンヴァスに油彩|727 × 500 mm
《港北ニュータウン》2021|カンヴァスに油彩|727 × 500 mm
焼かれるような痛みが先刻から断続的に皮膚を襲っていた。高温に熱せられたペンでグリグリと肌を抉られているみたいだ。脳内では火花が散り、左の鎖骨下部はじりじりと疼き続けている。ベッドに仰向けで横たわる私の視界に入るのは、壁に掛かったウォーホル風のマリリン・モンローと、たくさんの図案の下絵、あとは蛍光灯の点る天井だ。針が触れる度に肉がピクリと引き攣るのを抑えることができない。
「痛みますか?」
と、彫師が聞いてくる。
「はい……でも、耐えられないほどではないです。なんというか、こういう感じの痛みなんですね」
私がそう答えると、彼女はハハハと笑った。両腕から胸元にかけて花柄の刺青が入った女性彫師は、医療行為のように淡々と施術を進めていく。
ここは港北ニュータウンのタトゥースタジオだった。センター南にあるショッピングモールから目と鼻の先。一見するとただの民家だが、二階のベランダにはゴシック体で大きく「Tattoo」と書かれた垂幕を掲げている。ウェブで検索して知るまで、こんな住宅街に刺青屋があるなんて思いもよらなかった。
以前に一度、このスタジオへは打ち合わせに来ている。担当の彫師にイメージを伝えて図柄の方向性を決め、その話し合いを踏まえて、メールでやりとりしながらデザインを詰めていくのだ。最終的に、選んだフォントに彼女が線を足し引きし、オリジナルの下絵が完成した。そして今、現にそれを彫られているのである。
手順としては、まず上裸になり、部位に下絵を当ててサイズや位置を微調整する。それらが定まったら、剃毛と消毒を済ませ、ステンシルシートでデザインを肌に転写。そうしていよいよ、マシンのニードル先端から表皮にインクを染み込ませていくことになる。
これが私のファースト・タトゥーだった。彫っているのは、スクリプトと呼ばれる文字のタトゥーで、その文言は “New Town” 。そう、自身の「根拠地」を刻むのだ。
*
港北ニュータウンは私の出身地だ。3歳から12歳まで、横浜市都筑区にあるマンションに住んでいたから、いわゆる故郷ということになる。
生まれたのは、横浜市南部に位置する海沿いの街・金沢区富岡の団地らしいが、ほとんど記憶にない。そこから一家で港北に移り、私が中学1年の時に田園都市線たまプラーザ駅の一軒家に引っ越すまで、横浜市営地下鉄の中川駅周辺で過ごした。だから、幼稚園や小学校といった子供の頃の思い出は、港北ニュータウンに詰まっていることになる。
団地、マンション、一軒家と、東京へ漸近しながら横浜郊外を巡り、住む地域と物件のグレードを上げていった私の実家は、典型的な核家族だった。サラリーマンの父、専業主婦の母、長男の私と3つ下の妹という4人家族。両親は、そんな規範的な家族像を当たり前に営めた、最後の世代だった気もする。
アニメーターを経て、ゲーム会社社員から美術大学の教授に収まった父は、この春ちょうど定年で退官を迎えた。母は妹が中学生になって以降パートに従事していたが、いつからか介護職の正規職員として働いている。妹はどこかの会社に就職して今は川崎市に住んでいるそうだ。未だにフラフラしているのは私だけかもしれない。
新築で入居したらしい港北のマンションは、9棟から成る大規模なもので、私たち家族の住まいはC棟の10階。南向きのベランダからは、出来たばかりのみなとみらいに、ランドマークタワーが小さく見えた。
ニュータウンと言えば、かつては洗練されたライフスタイルの象徴だったはずだ。その一方で、ずっと疎外論的に語られてきた場所でもある。曰く、均質でのっぺりとした、人間性を剥奪する人工的な空間云々。さらに近年では、建物の老朽化や住民の高齢化、人口の減少など、様々な課題が山積している地域も多い。その意味で私にとっても、そこは両義的な空間だった。誰もが自らの地元に対して抱くように、私もまた、ニュータウンへの〈愛憎〉を抱えているのである。
特に、たまプラーザに引越してから、私は地元に対して親しみを持てないばかりか、どこか疎んじてすらいた。毎日バスと電車を乗り継いで麻布に通い、その近辺で遊んでいたから、友人もおらず、溜まる場所もない地元は、いわば私の中で空洞化していたのだ。何より、都内の繁華街と比較した際、思春期の10代にとって、ニュータウンはいかにもつまらなかった。空間に陰影や凹凸が存在しない。事実、東急の開発した「多摩田園都市」の中核であるその街からは、丁寧にノイズが除去されていた。
しかし、幼少期を送った港北ニュータウンには、そうした抵抗感が薄い。それは港北が刺激的だったというより、自身が子供だった部分が大きいだろう。もちろん、その町並みは至極つるりとしてフラットだった。だが、子供ならではの眼差しを通じて、周囲を勝手に読み替え、遊戯的に再構築し、起伏に富んだ空間として経験していたのである。
たとえばマンション棟内での鬼ごっこは、なかなかスリリングな遊びだった。時に住人に注意されることはあったものの、これが楽しい。エレベーターと階段を両方使ってフェイントをかけ合うのだが、とにかく戦略性が高いのだ。また、共同ゴミ捨て場をフィールドとしたケイドロもよくやった。大型のゴミ箱にドンと飛び乗って、ゴミ箱からゴミ箱へ、浮き島を渡るようにぴょんぴょん走る。さながらゲームのダンジョンである。
あるいは、遊びとも言えないが、一階の住宅のベランダ、その出っ張りの下の隙間に猫みたく潜り込む。実際、そこで猫と出会ったりもする。もしくは、しっかりと剪定された茂みと茂みの間にも、小さい身体を滑り込ませた。一見とっかかりのないニュータウンの圏内でも、こうして分け入れば綻びを見出せる。子供はどこであれ、空間の余白を敏感に嗅ぎつけて、そこへ無目的に介入していくのだ。
共に駆け回るのは、同じマンションや近隣に住む同世代の友達だった。多くが幼稚園も小学校も一緒で、気心は知れている。それは恵まれた環境だったに違いないが、誤解を恐れずに言えば、同質的でもあった。ただ、少しの“混住”すら無かったというわけではない。
親友の一人だったナオヤくん一家は、私たち家族のように、ニュータウン建設後に移り住んできた「新住民」と異なり、昔からその地に根を下ろす「旧住民」だった。公園の先の戸建てが並ぶエリアに、どっしり構えた瓦屋根の一軒家。隣地には、おじいさんとおばあさんの耕す畑がある。ご両親は警察官で、お姉ちゃんもいるし、ゴールデンレトリバーも飼っていた。その大家族の雰囲気が、私には珍しくも羨ましくもあったのだ。
そういえば、庭先に建つビニールハウスの中には、なぜか常にエロ本が落ちていた。性の意識に芽生える頃、一緒になってそのガサガサのページを繰った覚えがある。
駅から少し離れたアパートに住むナカちゃんは、小学生ながらに、少し不良の雰囲気を纏っていた。母子家庭で、家に遊びに行くといつも誰もいない。テレビゲームをやっていると、この前お兄ちゃんと酒を飲んだんだ、などと言う。そういうところがどこか格好よく見えたものだ。
床屋の子もいたし、ケーキ屋の子もいた。そのくらいの多様性はあった。が、あくまで友達の多くはサラリーマン家庭だったし、中流と言おうか、世代的・経済的に似たり寄ったりの人たちで構成されていたのは確かだろう。平成の前半、まだバブルの余韻が残る90年代の話である。
こうして子供なりに市街のコードを脱臼させていたのだが、前提として、ニュータウンには生活に必要なものが全て揃っていた。住宅、街路、公園、学校、病院、公民館、スーパーマーケット、レストラン、学習塾、書店……習い事で通ったピアノの先生のお屋敷も、スイミングスクールも、少年サッカークラブも、基本的にその内部で事足りる。私たちは、ニュータウンで何不自由なく生を全うすることができたのだ。
最寄りの公園は、広々とした敷地を持つ山崎公園だった。中心には、巨きなスリバチ型の広場がある。四つ葉のクローバーを探したのも、初めて自転車に乗ったのも、よく父とキャッチボールをしたのもここだ。隣接するのは、屋外型の市民プールと噴水の出る水場。夏休みには、水着とバスタオルを持って、毎日のように通っていた。
笹舟を流しもした細流に沿って坂を下ると、なかなかに立派な池がある。池の端にはフナやブルーギルを狙う釣り人が構えていた。私はブラックバスを釣ろうと、ルアーを投げ込んでいた時期があったが、結局一匹も釣れたことはない。
ただ、池の横に細長いドブがあり、そこではアメリカザリガニが獲れた。丸太と丸太の溝に手を突っ込んで、泥濘を手探りで掬うと、大概ザリガニが眠っている。そこでうまく鋏を避けながら、甲を鷲掴みにして引っ張り出すのだ。季節によっては、バケツ一杯のザリガニが獲れることもある。泥だらけの格好でそれを家に持ち帰り、「こんなにたくさんどうするの」と母を困らせもした。
このように、港北は自然に恵まれている。それもそのはずだろう。山深い丘陵地を切り拓いてできた空白地帯に、計画的に造成されるのがニュータウンだからだ。さりとて、それは決して〈手つかずの自然〉ではあり得ない。いくらワイルドに見えようと、ニュータウンの自然は、敢えて人為的に残された〈再帰的な自然〉に過ぎないのである。
それでも通称「裏山」には、整備されているとはいえ、随分と豊かな自然環境が保全されていた。通学していた小学校の真裏にあって、樹木が鬱蒼と茂っている。生物も多く、カブトムシはいないもののクワガタが採集できた。
一本だけ、小学生男子の間で代々受け継がれている木があった。初夏、「秘密の木」と呼びならわされるそのコナラを訪ねると、溢れ出る樹液を求めて、常にカナブンやスズメバチが集っている。まさに森のレストランだ。その木の根本に重なる枯葉を払い除けたり、腐葉土をちょっと掘り返したりするだけで、コクワガタが3匹も4匹も出てくるのだった。
そんな当時の行動範囲は、中川のみならず、自転車で足を伸ばせるセンター北と南まで及んだ。センター北・南は、その名の通り港北ニュータウンの中心地。横浜市北東部における副都心でもあり、多くの商業施設が集まるエリアである。
センター南はそれ自体がショッピングモールのような街だ。週末にしばしば家族と車で出かける。街の顔である「港北 TOKYU S.C.」には、子供心に何でもあった。オモチャみたいな建物の中、フードコートで食事をして、ゲームセンターで時間を潰し、シネマコンプレックスで『ゴジラ』や『ポケモン』を見る。そこはニューファミリーの休暇に最適化された空間だった。
北と南の間には、ホームセンターや家電量販店に混じって歴史博物館がある。縄文土器や集落跡が展示されており、小学校の社会科見学で行って、火起こし体験などをした。ニュータウンには、こうして発掘品を保管するミュージアムの類が設置されているところが少なくない。開発に際し山林を掘り崩すと、歴史的な遺物が往々にして出土されるからだ。
すぐ側の交差点の一角には、キングコングを思わせる巨大なゴリラの彫像がある。「都筑まもる君」という名を冠されたそれは、右の拳を突き上げ、牙を剥いた状態で、なぜか交通安全を声高に訴えていた。行政が設置したのだろうが、彼の実質的な存在意義は未だ判然としない。ただ、このキャラクターは界隈に知れ渡っており、意外と都筑区民に愛されていたことが伺える。
センター北のシンボルとなっていたのは「モザイクモール港北」だった。そのモール屋上には立派な観覧車が併設されていて、たしかオープン当初に一度だけ乗ったと思う。
実家のマンションからも眺められるその観覧車は、まるで街全体を遊園地に見立てるように、いつもぐるぐると港北の空を回っていた。
いかにも、ニュータウンは遊園地じみていた。書き割り的な町並みを有する虚構の街───そこはディズニーランドみたいな一種のテーマパークなのかもしれなかった。
(なかじま・はるや)