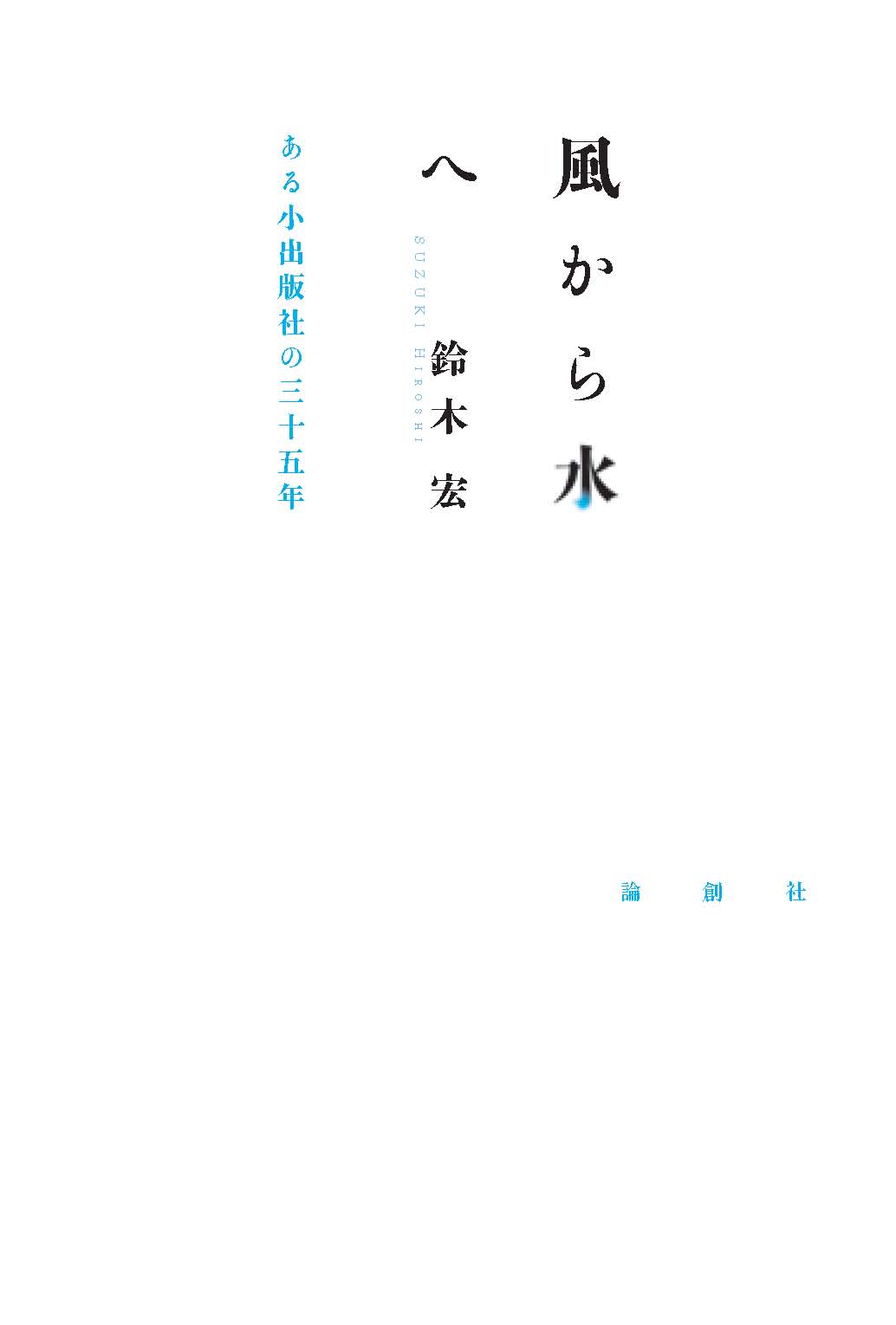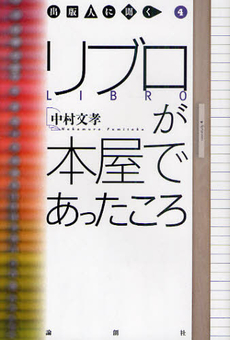㉛ 「二十世紀の文学」としての集英社『世界文学全集』
小田光雄
本連載㉙と㉚で、安原顕と中野幹隆が特集主義の季刊雑誌『パイディア』の編集者だったことを既述しておいた。しかしその後、安原が文芸誌『海』や書評誌『リテレール』に携わり、中野が『現代思想』や『エピステーメー』を創刊していくように、前者は文学系、後者は思想系の編集者に位置づけられるであろう。
こうした出版関係者の分類に関して、中村文孝『リブロが本屋であったころ』(「出版人に聞く」4)で、具体的にふれたことがあり、水声社の鈴木宏、中村と私は安原と同じく文学系、論創社の森下紀夫、『「今泉棚」とリブロの時代』(同1)の今泉は、中野と同様の思想系だという認識だった。それは1970年代の雑誌パラダイムでいえば、青土社の『ユリイカ』と『現代思想』のどちらの読者かという視点へとつながるものであった。
だがそこには読書体験前史が認められ、私たち戦後世代読者の視座からすると、各社の文学全集派と中央公論社の『世界の名著』派に分かれるという構図であった。多くの文学全集に関しては矢口進也の『世界文学全集』(トパーズプレス)やの田坂憲二の『日本文学全集の時代』(慶応義塾大学出版会)に詳しい。それに比べ、思想関連は『世界の名著』の他に、平凡社の『現代人の思想』や河出書房の『世界の大思想』などで、種類が少ないゆえか、まとまった研究と詳細なリストも提出されていないと思われる。
しかし1966年に刊行を始めた『世界の名著』全66巻はベストセラーとなり、確実に多くの思想や哲学の読者を獲得したはずだ。その第一回配本は確か『ニーチェ』だったはずで、中学生の私にしてもそれを購入している。
少しばかり『世界の名著』のことにこだわってしまったけれど、ここで取り上げたいのは世界文学全集についてなのである。鈴木宏の『風から水へ』において、国書刊行会の『世界幻想文学大系』と同様に、集英社の1960年代後半の『世界文学全集』が果たした役割はとても大きなものではなかったかと私は問うている。それは同時に国書刊行会の編集者となる以前の鈴木の世界文学全集体験を語ってもらうつもりだったのだが、彼は集英社の『世界文学全集』の成立に際し、篠田一士の存在が大きかったのではないかと応じ、個人的な世界文学全集観にふれてくれなかった。そのことについて、私の判断を加えれば、彼は私のような一般的な外国文学の読者ではなく、専門的な英文学や仏文学の研究者の道を進んだために、早くから外国文学の雑読から離脱していたのであろう。
それゆえに、馬齢と雑読を重ねてきた私個人の世界文学全集体験を語るしかない。前掲の矢口の『世界文学全集』に挙げられた各社のリストを見てもわかるように、1960年代にはいくつもの様々な世界文学全集が競合するように刊行されていたし、それらは中・高図書館や公共図書館にも必ず置かれていて、読むことを誘っているように思われた。その中のひとつに、1965年から68年にかけて出された集英社の『世界文学全集』があり、そこには「二十世紀の文学」というキャッチコピーが付されていた。それは他の世界文学全集がシェイクスピア、ドストエフスキー、トルストイ、スタンダール、ゲーテなどの古典を中心にすえていることに対し、新しい作家たちをコアとすることを告げていた。
今でもよく覚えているけれども、その巻末には全38巻の明細な作品リストが掲載され、「本邦初訳を原則に20世紀のベストセラーを集めたいま話題の文学全集!」とあり、本邦初訳には☆が付されていた。この見開き2ページを転載すれば、そのすべてが伝わるはずで、その誘惑に駆られるのだが、紙幅のこともあり、断念するしかないのが残念だ。興味のある読者はその一冊でいいから、ぜひ直接見てほしい。私はまだ高校生になったばかりだったので、アメリカ文学の短編のほうから読んでいった。それらは4のフォークナー「エミリーへの薔薇」(高橋正雄訳)、5のヘミングウェイ「殺し屋」(西川正身訳)、6のヘンリー・ミラー「暗い春」(吉田健一訳)、18の「孤独な娘」(丸谷才一訳)などで、従来の世界文学と異なる現代の文学の水脈にふれたように思われた。
だがこの『世界文学全集』の本領ともいうべきものを自覚したのは、大学生になってからであった。それはこの全集が時期尚早だったことも相乗し、どこの古本屋でも特価本として200円ほどで売られていたので、初訳の巻を一冊ずつ買い、読んでいったのである。現在であれば、断裁処分にされてしまうだろうが、そのような時代でなかったことに感謝しよう。
それらの主な巻と作品を示す。
7 ヘルマン・ブロッホ『ウェルギリウスの死』(川村二郎訳)
9 ギュンター・グラス『ブリキの太鼓』(高本研一訳)
10 ドリュ・ラ・ロッシェル『ジル』(若林真訳)
16 フォースター『ハワーズ・エンド』(吉田健一訳)、ゴールディング『蝿の王』(平井正穂訳)
19 ボールドウィン『もう一つの国』(野崎孝訳)、フィリップ・ロス『さようならコロンバス』(佐伯彰一訳)
23 ジロドウ『天使とのたたかい』(中村真一郎訳)、クノー『人生の日曜日』(白井浩司訳)
26 グラック『シルトの岸辺』(安藤元雄訳)、ブランショ『アミナダブ』(清水徹訳)
27 ベケット『モロイ』(三輪秀彦訳)、シモン『ル・パラス』(平岡篤頼訳)
32 ズベーボ『ゼーノの苦悶』(清水三郎治訳)、ホフマンスタール『影のない女』(高橋英夫訳)
34 ボルヘス『伝奇集』(篠田一士訳)
35 『現代詩集』(金関寿夫他訳)
36 『現代評論集』(川村二郎他訳)
もちろん若かりし頃の読書体験で、これらの「本邦初訳」をどこまで理解できたかは心許ないが、ここで新しい文学の息吹きにふれていたと断言していいだろう。
『集英社70年の歴史』によれば、この『世界文学全集』は1962年の『世界短篇文学全集』に端を発し、実質的にその編集に携わった若手学者の川村二郎、菅野昭正、篠田一士、原卓也、丸谷才一、渡辺一民たちとの親交を通じて、企画が成立したようだ。これらの人々のほとんどが訳者として加わっていることはその証明となろう。なおその後の集英社の世界文学関係の企画編集には綜合社が関与していくのだが、それについては拙稿「綜合社、森一祐」(「古本屋散策」77、『日本古書通信』2008年3月号所収)と、井家上隆幸『三一新書の時代』(「出版人に聞く」16)を参照されたい。
—(第31回、2018年9月15日予定)—
バックナンバーはこちら➡︎『本を読む』
《筆者ブログはこちら》➡️http://d.hatena.ne.jp/OdaMitsuo/