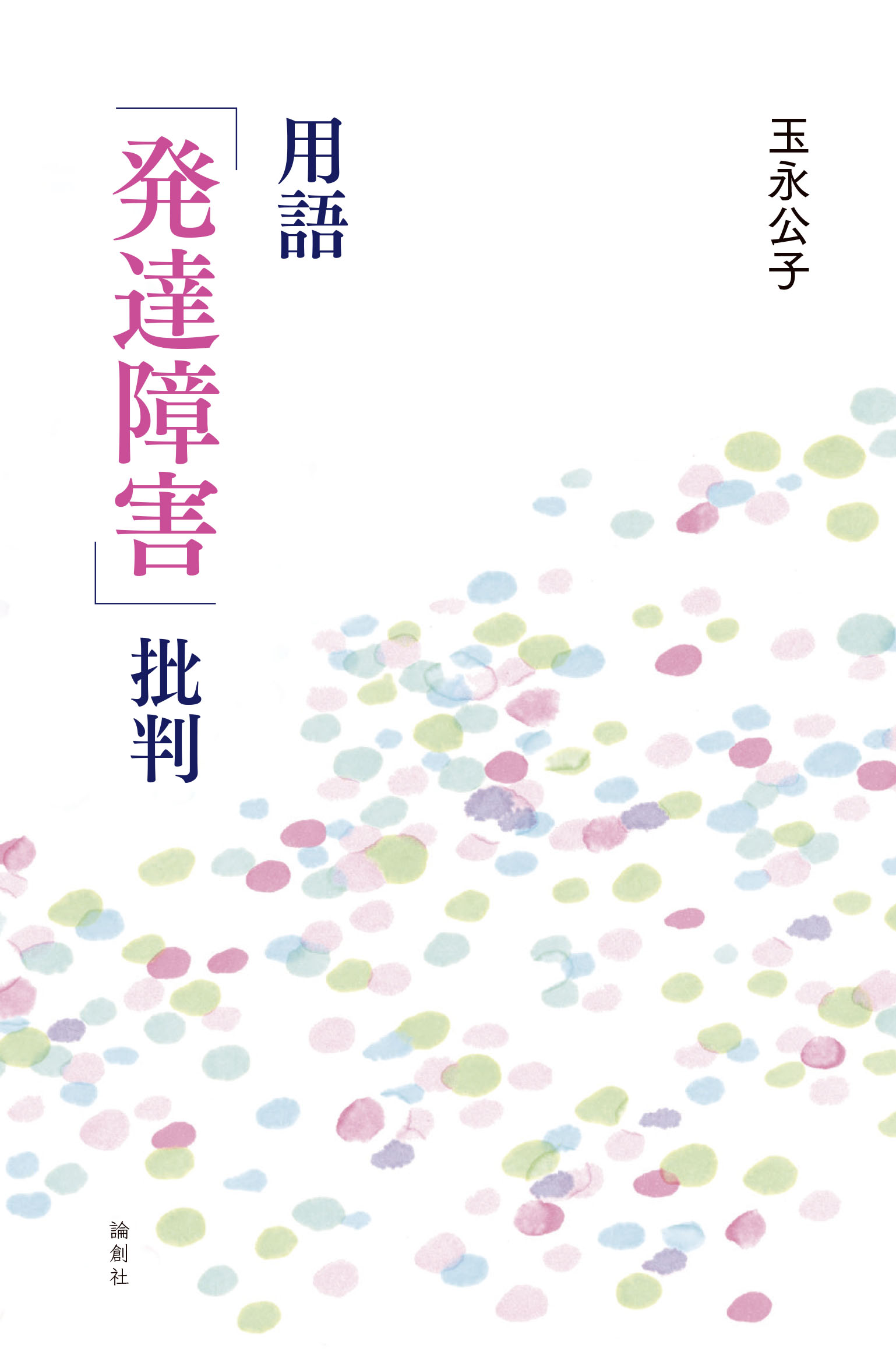- 2019-12-20
- 論創通信, 矢口英佑のナナメ読み
No.19 『用語「発達障害」批判』
矢口英佑〈2019.12.20〉
エディソン、アインシュタイン、ウオルト・ディズニー、アガサ・クリスティー、ベーブ・ルース、すべて外国人だが、これらの名前は日本人でも知らない人の方が少ないだろう。
発明家、科学者、映画制作者、推理作家、野球選手、いずれもその分野で超一流の成果を挙げ、彼らの足跡を讃へこそすれ、批判する者などいないにちがいない。
ところが、恵まれた才能をみごとに花開かせた彼らの子ども時代はどうだったのかと言えば、エディソンは4歳まで話すことができず、多動性、調整能力不足で教師から劣等生扱いされていた。アインシュタインも多動性で協調性がなく、他人のことには無関心で、教室の厄介者だった。ウオルト・ディズニーは読み能力が困難な子どもだった。アガサ・クリスティーは単語を読むことができなかった。ベーブ・ルースは言葉で伝えることや文章化することができなかった。
現在日本では、こうした子どもたちが教室にいれば、その子どもだけの指導に時間を割くことは難しく、結果として厄介者となり、級友たちからは相手にされなくなることが多い。しかもこうした子どもたちには「発達障害」という烙印が押され、それが妥当な判断として、多くの日本人がこの用語そのものに疑いを持たないし、それを受け入れてしまっている。
本書は重度の自閉症、注意欠如・多動症、学習障害者を「発達障害」という用語で呼ばず、それぞれの名称で呼ぶことを提案し、さらに社会で十分に活躍できる、個性的な人びとの状態までもひとまとめにして「発達障害」と括って、なんとなく納得してしまっている現在の日本の状況への異議申し立て書になっている。
著者の主張は実に明解である。
「発達上の障害」と表現すれば、肢体不自由など、発達過程でのさまざまな状態が想起されますが、「発達障害」という四字熟語を聞くと、「発達障害」という一つの障害があると思ってしまう人が出てきます
確かに我々の日常生活でこの言葉を耳にすると、著者の指摘に反論するだけの、確固とした認識を持って、この言葉を受け止めているわけではない。そして、著者はこう断言する。
「発達障害」という障害はありません
「発達障害」という言葉はアメリカの診断書にあった「Developmental Disorder」の日本語訳で、はじめは「知的障害」「自閉症」「学習障害」(Learning Disability)の3つを指したが、その後「注意欠如・多動性」(Attention Deficit Hyperactivity Disorder)が加えられたようである。しかし、アメリカでは診断の分類が変わり、すでにこの言葉は使われていないという。ところが日本では肢体不自由、病虚弱、視聴覚障害、知的障害、ダウン氏症候群、自閉症などの状態には分類できない子どもたちが注目されるようになって、2007年頃から、その子どもたちに「発達障害」という用語が使われるようになったようで、すっかり定着してしまった観がある。
では著者はなぜ「発達障害」という用語の安易な使われ方に激しく異議を申し立てるのか。それは障害の違いによって対処方法や教育、学習方法が異なるからである。エディソンやアインシュタインなどは「学習障害」(Learning Disability)だったのであり、現在、学校で厄介者、落ちこぼれと見られる生徒、あるいはみずから「発達障害」と認めたり、他者から指摘されたりする多くの人がこの範疇に入る。
現在、日本では小学校入学は満6歳を迎えた最初の4月で、それから9年間が義務教育である。年齢による横一線入学だけに、小学校1、2年では早生まれとそうでない児童で、学力に差があることはよく知られている。
考えてみれば、個々の児童や生徒の知的能力や身体機能にはばらつきがあり、決して横一線ではない。本来的にはそれら一人一人の児童に見合った教育が行われてもいいわけで、ましてや「学習障害」(Learning Disability)、「注意欠如・多動性」(Attention Deficit Hyperactivity Disorder)と判断できる者への教育は個別的な指導が必要となるのは、むしろ当然だろう。
残念ながら現在、「学習障害」「注意欠如・多動性」への理解は十分ではなく、本書ではこうした症状について、多くの事例を示しながらどう対応してきたのか詳細に報告されている。いずれの症状にも個別的な観察と状態の把握の重要性、そして適切な対応が必要であると著者は説いている。
たとえば、「学習障害」と言っても、〝話し、読み、書きなど〟〝計算、推理など〟〝手先の技能など〟言語性と非言語性の「学習障害」(LD)があり、さらに言語性LDだけでも「聞く、話す、読む、書く、読解、計算、数学的思考」の7つの状態があるという。しかも、これらは「発達的な遅れではなく、器質的に持っている永続的なもの」、つまり「生まれながらの、脳の構造と機能の違いが原因」で、その様相を持って生まれた人、その人そのもので、発達障害といったものではないとなれば、それぞれに適った対応がされなければならないのは明らかだろう。
だからこそ著者はこれまでこうした状況が一生続くのであるから、「治療する」ものではなく、「対処する」ものであり、結論として弱い面を補償し、強い面を生かすことが最善の方法と捉えてきていたのだった。
ところが2016年にこれまでの著者の捉え方を根本的に覆すカナダのトロント大学の教員で精神科医のノーマン・ドイジが著した『脳はいかに治癒をもたらすか』と出会うことになる。彼はパリ大学の医学部耳鼻咽喉科で学んだアルフレッド・トマティス博士の理論を紹介していて、脳は可塑性を持っており、それを利用して脳の機能を回復させるというのである。具体的には音の聴覚への刺激で皮質下の構造が変化して、それに呼応して、脳の神経細胞が組み立て直されてLD状態が改善されるのだという。
つまりLD状態は生涯引きずり続ける障害ではなく、治せるとなれば、治せる治療を施せばいいわけで、著者がその事実を知ったときの強烈な驚きと衝撃はどれほどのものだったのかは想像にかたくない。
「LD観を根本的に覆すコペルニクス的な転回」を覚った著者は、LD教育はすべて補償教育を主題としてきた自著などは「取り下げなければならない」とまで記すに至るのである。
そして治療可能であるなら、「障害」ではなく「症状」であるとし、「発達障害」などという用語を使わないのは無論のこと、治療できるという前提で対応していくことを訴えていく。
さてこのように見てくると、本書は「発達障害」という用語ですべてを括って、納得してしまっている現在の日本の状況への異議申し立て書であると同時に、これまで「厄介者」「落ちこぼれ」とみなされてきた人びとに一人の社会人として、堂々と生きていくことができる光明と自信を与える書にもなっている。そして、さらに言えば、著者にとって研究者としての新たな方向へ向かい始めた宣言の書にもなっているようである。
(やぐち・えいすけ)
バックナンバー→矢口英佑のナナメ読み
〈次回、2020.1.15予定『ルドルフ・ディットリヒ物語』〉
『用語「発達障害」批判』 四六判上製208頁 定価:本体2,000円+税