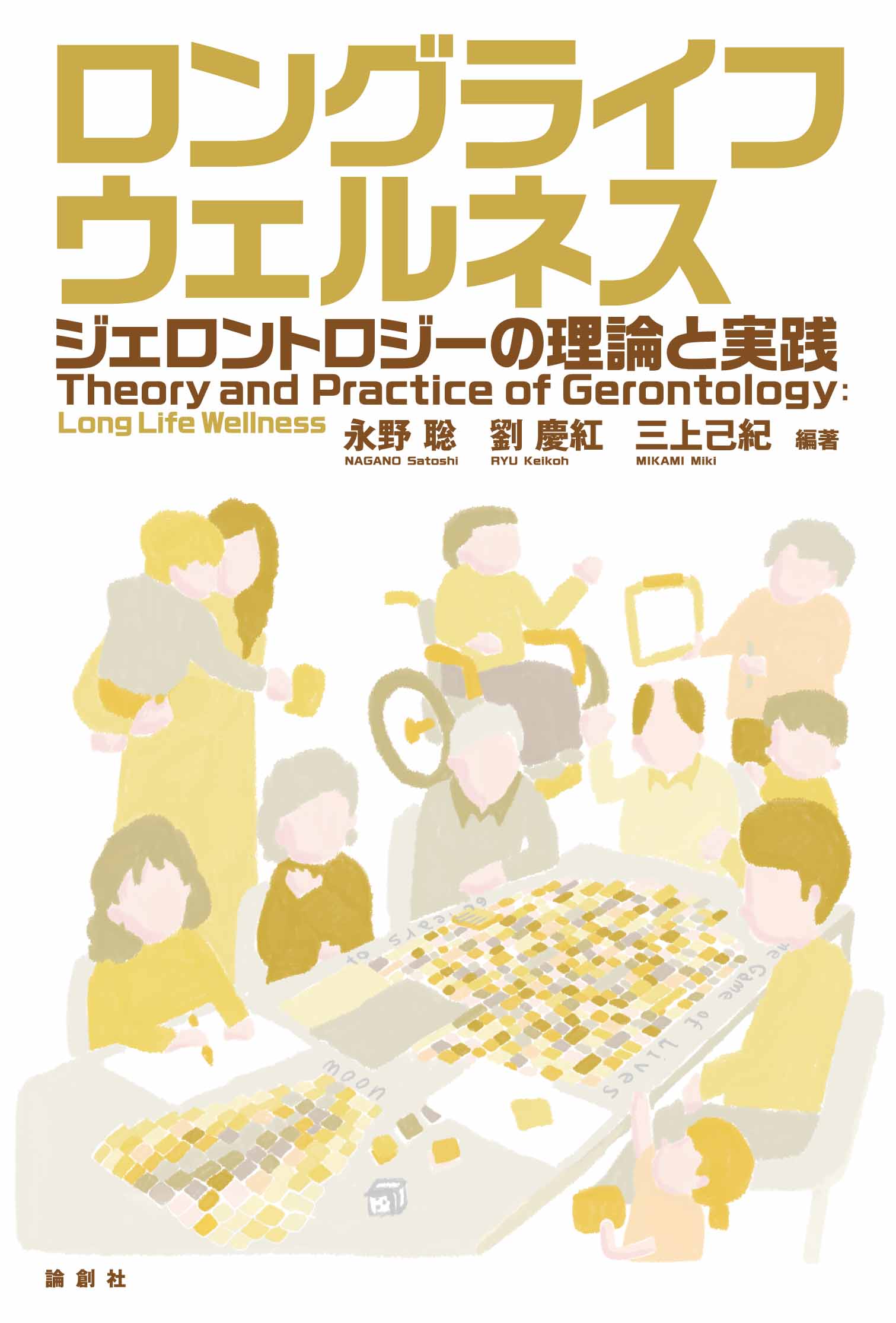- 2022-4-12
- お知らせ, 論創通信, 矢口英佑のナナメ読み
No.50『ロングライフウエルネス——ジェロントロジーの理論と実践』
矢口英佑〈2022.4.12〉
本書の書名を目にするや、その領域に多少とも知識のある人を除くと、少々、戸惑いを覚える向きは多いのではないだろうか。まず大きな「ロングライフウエルネス」というカタカナ文字が目に飛び込み、ついでその下に「ジェロントロジー」と小ぶりのカタカナ文字が並んでいて、頭にすっと入ってこないかもしれないからである。
ただ、本書の帯には「人生100年時代」の文字と、「人生をデザインしよう!」とあることから、「ロングライフウエルネス」を書名にした意図は理解できるという仕掛けになっていると言えそうである。
そして「ジェロントロジー」とは、日本語では「老年学」などと訳されている新しい学問領域で、まだ100年余ほどの歴史しかない。単に高齢者の健康維持などの医学面だけでないことを大きな特色としている。心の問題、社会保障問題、社会参加問題など身体的、経済的、心理的、社会的等々さまざまな側面から高齢化にともなう問題を総合的に考える学問である。
超高齢社会となっている日本は年金、医療、介護などのいわゆる社会保障給付費は増加の一途をたどっている。そのため2022年4月から年金の受給開始年齢の繰り下げを75歳まで延長したばかりである。年金支給額を大きく増額することになっても、年金受給年齢を引き下げるのは社会保障給付費の支出を抑制する施策にほかならない。
団塊世代がすべて 75 歳以上となる 2025 年はもうそこまで来ていて、超高齢社会にどう向き合うのかは、今や日本人の一人ひとりに問いかけられている重要課題と言えるだろう。
本書の「はじめに」で編著者の一人である永野 聡は次のように記している。
「長寿という幸せを安心して享受し、いきいきと暮らせる地域社会をつくりあげることが喫緊の課題となっている。そのためには、個人、家族、地域社会、行政、企業、NPOなど社会全体での取り組みが不可欠であり、さらに、それらを総合した社会経済や都市・地域のあり方、コミュニティや社会システムに関するグランドデザインを描く必要があるだろう」
ジェロントロジー(老年学)は高齢者だけの問題としてではなく、広く社会全体が関わり、世代を越えて課題に取り組み、いかに老後を快適に過ごせるのか、その回答を追究する学問と言える。
本書は立命館大学産業社会学部永野ゼミ、立命館大学の他学部の教員、さらには外部の研究者たちによってまとめられた研究報告、実践活動報告書である。巻末に氏名と経歴が記載されている方が15人に上るほか、永野ゼミの学生さんも加わって総勢20名以上の方が関わっている。
それだけ取り組むべき課題が多岐に渡っているわけだが、この学問と向かい合う者の年齢によっても、当然のことながら取り上げる課題や取り組む姿勢、関心が異なっていることがわかる。
たとえば「4章 未来編」に記録された意見交換会での発言では、各人の年齢、職業、経歴、体験などの違いが発言内容に反映されている。特に未来に向けての発言ということもあって、今後、どのような対処策が創出され、どのようなゴールとなるのか発言者にも明確には見えていない部分もある。それだけに多様な発言となっていて、さまざまな可能性が内包されている。ただ、確かな共通認識があることもまちがいない。それは高齢者問題は社会を構成する一人ひとりが協力し合い、助け合って社会全体でより良い方向性を見いだしていかなければならないという認識だろう。
ところで本書の「2章 理論編」の「3節 ジェロントロジーと脱炭素社会」には2050年の高齢者の生活がフィクションとして描かれている箇所がある。
ここには「バイオハック」という現在、一般的にはあまり浸透していない言葉が使われている。「高齢化する肉体を管理し、投薬及び外科手術等の対策を行ない、肉体的な劣化を回復する方法。「老化治療」とも呼ばれる医療行為」である。そして、もう一つが「地域民生プラットフォーム」。こちらは「日々の安全をアシストする。室内の安全をモニターすることに加え、バイタルチェックなどを行なう。火災及び許可のない侵入者があった場合なども「地域民生システム」に自動通報を行なうセンサーを装備している」という地域社会の姿である。
社会も個人の生活もあらゆるところに人工知能が組み込まれ、介護も人工知能の活用と機械化によるサポートが行なわれ、重病を併発している場合を除き、寝たきりの高齢者はほぼなくなるという超高齢社会である。
筆者の三上己紀はこう記している。「これはSFではない。今、私たちが保有している技術で実現できることばかりである。フィクションにするか、ノンフィクションにするかは私たちの選択によって決まる」
現在、私たちが保持している科学技術で、こうした社会が実現できるならば是非とも私たちの手でノンフィクションにしなければならないだろう。
しかし一方で、同じ「2章 理論編」の「5節 ジェロントロジーと公共政策」では、現在、取り組まれている公共政策というものが「個人や家庭の幸福追求に関わる問題についてほとんど関与すること」がなく、「単身高齢者等の生存権が保障されていれば」どのように生きていくのかは個人に任せられているのが実情なのである。しかし、それでは孤立化を招きかねない。単に「住居や金銭の問題のみを解決する」のではなく、「社会的に孤立」しがちな高齢者や生活困窮者たちにとって有効な公共政策とは「コミュニティーの再生」だと筆者の森裕之は指摘している。
また「3章 実践編」の「1節 ジェロントロジーと地域医療」では、現に老いることに直面している高齢者の生の声が聞こえる。
若い時にはできていたことができなくなり、ついには自分のことすらできなくなって介護が必要なってしまう。家族や周囲の人に迷惑をかけていると常に感じ始め、やがては生きている意味や自分の存在意義を喪失してしまう、というのである。
筆者の江角悠太は「全ての人が徐々に歩けなくなり、徐々に物忘れがひどくなることは当たり前のことである。それが「老いる」ということだ。それを「お荷物だ」と感じさせている原因はなんであろう。「老いたらお荷物」、この風土こそが、「老い」を楽しむことから遠ざけているのではないだろうか?」と記している。
筆者のこうした問いかけへの回答は、「人としての存在意義」や「生きがい」が感じられること、そして、老いることも楽しいと感じられる人間と人間のつながり、関わり合いがあることであり、そうした社会の創出、となるのだろう。
ジェロントロジー(老年学)の目指すところは、誤解を恐れずに言えば、実はよく見えているのかもしれない。しかし、その目指すところに向かってどのように行き着くのかとなると、あまりにも多様な領域とその過程での多くの解決すべき課題が広がっていることは、本書がよく教えてくれている。無論、この学問領域での一定程度の成果が見られていることも本書からはよく理解できる。
しかし、総体としての高齢者問題となると、永野聡が「はじめに」で、
「本書では、超高齢化時代の社会課題を理解し、解決の糸口を探るため、大学、行政、企業など様々なセクターを巻き込んだ、学際的かつ包括的な取り組みを紹介する」
と正直に述べているように、まだ糸口を探る段階であり、大きな山が依然として立ちふさがっている。
中国の列子・湯問篇に「愚公、山を移す」という言葉がある。地道に努力を続ければいずれ成功するという意味である。大きな眼前の山がいつの日か平らになる譬えのように、超高齢社会で誰もが生き生きと暮らせる日が訪れることを願うのは私一人だけではないだろう。しかし、それの実現のためには、ジェロントロジーを研究している人びとだけに任せてはならない。私たち一人ひとりが自分の問題として強く認識し、互いが協力し合い、行政、企業とも協働して人生100年時代に見合った生き方を考えていかなければならない。
それを教えてくれるのが本書である。
(やぐち・えいすけ)
バックナンバー→矢口英佑のナナメ読み