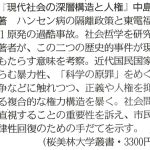- 2022-3-31
- お知らせ, 論創通信, 矢口英佑のナナメ読み
No.49『リプトン自伝』
矢口英佑〈2022.3.31〉
“リプトン”という言葉を耳にした時、どこか身近な響きとして受けとめる人は少なくないだろう。そして、おそらく連想ゲームのように“リプトン紅茶”という紅茶のブランド名と結びつく人が大多数ではないだろうか。
本書はそのリプトン紅茶の生みの親、トーマス・リプトンの自伝である。1848年、イギリス・スコットランドのグラスゴーに生まれ、1931年にロンドンで83歳の生涯を閉じた彼の人生は、自伝からは〝独創性と冒険心に溢れた挑戦者〟だった姿が浮んでくる。
その象徴的な行動は1851年にロンドンで開催された最初の万国博覧会を記念して始まったヨットレース(優勝したアメリカのアメリカ号にちなんでその後はアメリカズカップと呼ばれる)出場だろう。1899年に初めて出場してから30年間に5回挑戦し、最後のレースは死の前年、1930年だった。すべて敗北という結果だったが、「決して諦めない精神」と称えられ、最後のレース終了後、アメリカ市民の募金で作製された純金製のカップがニューヨークで彼に授与されたのだった。
ところで、当たり前のことだが「自伝」は「伝記」と異なり、本人が執筆するか、語ったものである。しかし、その理解からすると本書はジャーナリストのウイリアム・ブラックウッドという伴走者がいなければ、リプトンの自伝は誕生しなかった可能性があった。「私はジャーナリストとして、トーマス・リプトン卿が生きた人生は途方もなく興味深いものであると認識して、彼に自伝を執筆するように繰り返し依頼してきた。だが彼は長年、この類の申し出に頑として聞く耳を持たなかった」(本書「まえがき」)。そのリプトンを説き伏せたのであるから。さらにもう一点、この自伝が陽の目を見なかったかもしれないのは、リプトンが刊行前に鬼籍に入ってしまい、一時は自伝出版を諦めかけたことを、これまたウイリアム・ブラックウッドが「まえがき」に記している。その意味では、「決して諦めない精神」がウイリアム・ブラックウッドにも乗り移っていたのかもしれない。
「自伝」に取りかかるに当たって、リプトンは次のように言っている。
「さてこれから、ごく控えめに語るにしても、私は前述のあらゆる懐古的要素を全て盛り込んだ「ブレンド」を提供できるのではないかと考えている。言えばすべてが極めて私的な話をする中で、どの話を選び、どれを除外するか、どの箇所は率直に語るか、それとも口を慎むか、あるいは実話の中で固有名詞をいかに用いるかといった判断が、私にとって悩みの種である」
この彼の言葉からは〝自分語り〟を記録として残す際、それらがすべて「私的な話」であり、事象の取捨選択、語りくちの濃淡など何もかも自分次第であること。つまりどのような自伝にもなり得る可能性を十二分に理解していたことがわかる。それだけに〝自分語り〟にありがちな偏向した自己正当化や自己顕示、対象者批判といった内容がほとんど記録されていないのは、意図的にそのような表現を避けたにちがいない。この点こそが本書の特色と言えるだろう。極端な誇大も、矮小も、自慢も卑下もない、抑制の効いたリプトンの自伝には嫌味がなく、爽やかさに包まれている。そして、事業を果敢に展開し、飽くなき挑戦を続ける姿は一編の冒険小説を読んでいるような気分にさせられる。
本書がけれん味のない自伝となりえたのは、彼の次のような生き方が大きく作用していたように思える。
「原則的に私は、過去を振り返るのが好きではない。いつでも私は、前を向いていたいのである。私は常に、昨日や一昨日の出来事よりも、来るべき明日のことに心ひかれている。昨日はすでに過ぎ去った日であり、これから迎える明日には可能性が秘められている。(中略)かつてグラスゴーで初めて自分の店を開店させた時の感激をさらに上回る熱情を味わってみたいと心躍らせているのである」
こうした未来志向の性格は過去の苦い経験や体験さえも〝後悔〟といった類いの言葉を乗り越えていく方向舵になったらしいことを自伝は教えてくれる。失敗を恐れず常に積極的に新しい事業に挑戦していった姿勢こそ彼の最大の武器であり、彼が「私が人生行路を笑顔で渡ってこられたのは、私が楽天家だったお陰である。私は常にご機嫌で意気揚々としている」という自己分析も納得がいく。
リプトンが「商い」に目を向けるようになったのは両親がハム、バター、卵などの食料品の小売業を始めた時に始まる。彼は1週間分の商品を船から手押し車で運ぶ手伝いをし、母親から仕事の対価として、初めて週給というものを手にできたのだった。「私は両親が始めたこの事業に強い関心を持った」とリプトンは述懐しているが、この時、みずからがどのような道を歩むのか、おぼろげながらも掴み始めていたのかもしれない。彼は「商い」とはどうあるべきか、両親の店の客との関わり合い方から早くも学んでいたと言えそうである。
「顧客にとって、確かな品をほどよい値段で購入できることはもちろんであるが、それにも増して重要なことは、その品々を扱っている者が、店の近隣地区で何年来よく知られた表も裏もない正直者で顔馴染みの人物」と両親を見ていて、客からの信用がいかに重要であるのかを感じとっていたのである。しかも商売を手伝っていたからこそ気がついたのだろうが、まだ10歳にもならない子どもがある時、
「ねえ、お父さん、卵を売るのはお母さんに任せたらどうかな。お母さんの手はお父さんより小さいから、お母さんの手で売ったほうが卵が大きく見えると思うんだ」
と言ったという。
リプトンが幼くして、すでに購入者の目線に気がつき、購買力を増加させる方策に考えをめぐらせるという才覚を持ち合わせていたらしいことを窺わせるエピソードと言える。
これはやがてリプトンが21歳の誕生日に最初に構えた店につり下げた宣伝用の木製のハムや生きた豚を引き連れて街中を行進したり、人間が広告塔となるサンドイッチマンを考えついたりといった宣伝手法に繋がっていったであろうことは容易に想像できる。
客との距離を縮めるために敢えて方言で話しかけたり、夜になっても店にガス灯をつけ、灯台のように明るくすることで客から注目させたりと宣伝広告の影響力の大きさを掴んでいたことがよくわかる。
現在では宣伝広告の重要さは誰もが認識しているが、当時にあっては「私が、斬新で巧妙な宣伝効果の限りない可能性と利点に気づいて、その恩恵に与った最初の英国人であることは確かな事実である」ことに異議を差し挟む余地はなさそうである。
現在では考えられないが、リプトンには学歴というものがほとんどない。家庭の生活状況を慮ってという理由もあったにせよ、両親に無断で学校を辞め、9歳で文具店で働き始めてしまったからである。商人としての才覚が備わり、学校での学びより実社会で直面する経験から学び取ることを選択した少年には、机上の学問にはあまり魅力を感じられなかったのかもしれない。
自伝の類いはその人物が歩んできた過去を振り返って記されるものであるのはあらためて言うまでもないが、9歳で学校を辞めてしまったときのことをリプトンは次のように誇らしげに記している。
「これから自分でお金を稼いで、自立するのだときっぱり言い切った。するとついに両親のほうが折れて、その晩私は、幼くしてグラスゴー一番の英雄気取りの鼻高々でベッドにもぐりこんだ」
おそらく自分の人生の大きな転回点になったという強烈な思いが人生の終着点に近づいてきたリプトンに、なお少年の日の決断として大きくその脳裏に刻みつけられていたにちがいない。
リプトンは一人の〝食料品を販売する商人〟に過ぎなかった。それが自分の目や手が届かないほどの巨大な事業にまで発展させることができたのは、創業時から彼が「可能な限り良質な品を可能な限り手頃な価格で販売し、顧客の立場を忘れない」を商売の原則としてきたからだった。
〝商い〟にすべてを賭けた男、それがトーマス・リプトンだった。その人生は常に顧客に目が向けられ、休むことを惜しむといった言葉が陳腐に映るほどがむしゃらに働き続け、それが生きがいだったことが自伝からは濃厚に伝わってくる。決して平坦な道でなかったはずで、余人にはまねのできない努力が積み重ねられてきたにちがいない。だが、そうした苦労譚は自伝にはほとんど綴られていない。
それにもかかわらず、彼が困難を乗り越えてきたと私に感じさせるのは、本書の最終章に当たる第二十二章に「私の信条」を置き、
「私は自分の本を締めくくるにあたって、これまで自分の生涯をかけて、とてつもなく懸命に働き続けて、今ではとても年を重ねた人間として、これからその道に踏み出そうとする方々に向けて、ここで何か父親のような助言のひとつふたつを捧げるのがよいと思う」
と述べているからである。
不特定多数の人びとへの〝助言〟というものは、幾多の困難を乗り越えてきた経験者だからこそできるものだろう。「商い」を始めようとする人びとへの助言としてリプトンは位置づけているようだが、それにとどまらない。人が生きていくために、社会や人間に対してどのように対処すべきか、おのずと滲み出ているからである。
リプトンは航海術の経験も持つ者として、自然を相手に海を航行する船の操縦の難しさを例にとりながら人生に重ね合わせて語りかけている。この最終章までの自伝が〝動〟とするなら〝静〟の世界に一変するのである。
功なり名遂げ、波乱万丈の人生を歩んだリプトンが、読者に「父親のような助言」を静かに語る言葉は「とてつもなく懸命に働き続けてきた」彼の人生をすでに知っている読者には、まるで乾いた土に水が勢いよく染み込んでいくように、どの言葉にも首肯するにちがいない。
この自伝を手にされた読者は、おそらく本書から一つは元気を注入され、一つは自分の生き方に大いなるヒントが与えられるはずである。
(やぐち・えいすけ)
バックナンバー→矢口英佑のナナメ読み