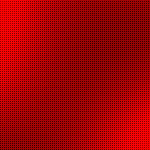『コロナの倫理学』 ⑮自分探しの旅
森田浩之
コロナ禍の自殺
これまで専門外の私が理解した新型コロナウイルス(covid-19)の知識、とくに感染の仕方、感染経路、そしてコロナ禍の生活、とくにその諸影響について見てきた。大半がネガティブな話だったが、音楽(新しいリアル)、テレワーク、ICT(情報通信技術)による新しい教育のあり方については、コロナをきっかけによい方向に進んでいくことが期待される。
ここまで避けてきた最も深刻な話題のひとつが自殺である(最も深刻なことには、ほかに感染による病死そのものがある)。いろいろと引用することで、現状を整理したい。日本経済新聞(2021年1月22日)は「20年の自殺者2万919人 11年ぶり増加、コロナ影響か」1)という見出しで、「警察庁と厚生労働省は[2021年1月]22日、2020年の自殺者数は前年比750人増(3.7%増)の2万919人(速報値)だったと発表した。これまで10年連続で減少していたが、リーマンショック直後の09年以来11年ぶりに増加に転じた。女性や若年層の増加が目立ち、新型コロナウイルスの感染拡大に伴う外出自粛や生活環境の変化が影響した恐れがある」と解説する。
男性は減ったものの、女性が増えており、年代別では40歳代が一番多く、増え方としては20歳代が17%で最も高く、次に19歳以下の未成年の14%だった。小中高校生の自殺者は1980年以降で最も多かったという。1回目の緊急事態宣言を含む2020年4~5月の自殺者は前年以下だったが、2020年下半期は増加して、とくに10月が一番多かったとのことである。
引用のように、この数字は「速報値」で、2021年3月に「確定値」が発表された。日本経済新聞(2021年3月16日)は「警察庁と厚生労働省が16日に発表した2020年の自殺者数(確定値)はリーマンショック後の09年以来、11年ぶりに増加した。女性や若年層の自殺が増えている。新型コロナウイルスの感染拡大を背景に、経済的な苦境に追い込まれたり、孤立に陥ったりする人が増えているとみられる」2)と説明する。
数字に大きな変化はないので理由について引用すると、「遺書や遺族らへの聞き取りをもとに自殺の動機を分析したところ、『健康問題』が全体の48.4%、『経済・生活問題』が15.3%、『家庭問題』が14.8%だった。」
相談窓口を開設したNPOの代表によると「『コロナの影響による雇用環境の悪化が自殺の増加に影響した可能性がある』とみる。『コロナで職を失った』『パート先を解雇された』など、非正規雇用の若い女性からの相談が目立つという。」
日本経済新聞は「[20]20年はコロナ禍で日常生活が一変した。政府は、他人との接点が少なくなって孤独を感じたり、社会的、経済的に孤立したりする人が増えたことが自殺者増の要因の一つになっているとみて対策強化に乗り出している」と続ける。
ひとつめの記事で2020年10月に自殺が急増したと書いてあったが、これについて厚生労働省が分析している。厚生労働大臣指定法人「いのち支える自殺対策推進センター(JSCP)」の代表理事が「コロナ禍における自殺の動向――10月の自殺急増の背景について」というレポートを提出している3)。
このなかで2020年10月に自殺が急増した理由として「新型コロナの影響により、社会全体の自殺リスクが高まっていること(自殺の要因となり得る、雇用、暮らし、人間関係等の問題が悪化していること)」と「相次ぐ有名人の自殺および自殺報道が大きく影響した可能性(ウェルテル効果の可能性)」を挙げている。
「新型コロナの影響で様々な悩みや生活上の問題を抱え、あるいは元々自殺念慮を抱えながらも、『どうにか生きることに留まっていた人たち(4~5月に自殺行動に至らなかった人たちを含む)』に対して、相次ぐ有名人の自殺および自殺報道が多くの人を自殺の方向に後押ししてしまった可能性がある」とのことである。2020年4~5月の自殺者が前年より少なかったことは、上記の日本経済新聞が指摘している。
ちなみに「ウェルテル効果」は「マスコミの自殺報道に影響されて自殺が増える事象」で、ゲーテの『若きウェルテルの悩み』から来ているそうである。
これらの現象を掘り下げたものはないかとネット検索していたら、医学書院の『医学界新聞』に「コロナ禍の自殺問題――今こそ,医療者に求められる視点とは」(週刊医学界新聞 2021年4月5日)と題する対談記事4)を見つけた。対談者は上で紹介した厚生労働大臣指定法人「いのち支える自殺対策推進センター」の別の方(センター長)と「国立精神・神経医療研究センター 精神保健研究所」の所長である。
冒頭「コロナ禍のメンタルヘルス問題は通常の大規模自然災害と異なる点」に言及し、その違いとして「社会不安の増大と雇用環境の悪化」が挙げられ、「感染への不安と経済的困窮がメンタルヘルス上の大きなリスクファクターになり得ます」と指摘され、「2008年のリーマンショックは失業や職業的アイデンティティが崩れた影響によるメンタルヘルスの影響が課題となりました。COVID-19は一部の人々の心理的・社会的結びつきを脆弱なものにした上に、雇用環境の悪化をももたらしている。それによってメンタルヘルス上のハンディを抱えていた人々の心理的負担が増大し、最悪の場合自殺に至ってしまうと考えられます。過去にない影響の広がり方と深刻さに強い危機感を持っています」と概括される。
上で述べたように、緊急事態宣言を含む2020年4~5月には、自殺者は前年以下だった。両対談者はそれぞれ「この時期、完全失業率が増加したにもかかわらず自殺者数が減少した理由に、社会的不安の増大と社会的努力の可視化が影響した」という見方と、「大規模災害の直後、社会的不安が急激に増大すると一時的にストレスが減じ,自殺者が減少するとされます。阪神・淡路大震災や東日本大震災でも発災直後に同様の現象が認められました。コロナ禍の今回も同様の現象が見られた」という視点を提示している。
女性の自殺者が増えたことについて、片方の対談者の「女性の自殺の背景には一般に、雇用の問題の他、家庭内暴力(DV)被害や、育児・介護の悩みなどさまざまな問題が関連します。コロナ禍の雇用環境の悪化も男女差が見られますか」という質問に対し、相手方は「2020年4月には、非正規雇用の女性約108万人が職を失っています。コロナ禍の雇用への影響は女性に顕著に表れました。そして、女性の非正規雇用労働者数が減少した時期に遅れて自殺者数が増加している。この強い相関も明らかになっています」と解説する。
「非正規雇用者の解雇と女性の自殺、両者の関連を念頭に置いた対策が必要になるでしょう。女性の自殺者数の増加は、有名人の自殺報道の影響もあったとみてよいでしょうか」との問いかけには、「7月下旬の男性俳優の自殺によるウェルテル効果は1週間、9月下旬の女優の自殺報道後は1~3週間程度,統計学的に有意な増加が認められました」という返答。
これも上で紹介したが、2020年10月に自殺者が急増した要因として「10月に増加した自殺者数に占める女性の割合も高く出ています。ウェルテル効果には不況や雇用環境の悪化といった背景要因効果(background effect)があり、雇用問題で自殺のハイリスク集団となった女性が、有名人の自殺報道にさらされたことで自殺が誘発されたと考えられます」と分析される。
このように見ていくと、自殺を引き起こす原因は複雑である。不安が起点だが(今回の場合は感染の恐怖)、これに雇用環境の悪化が加わると自殺傾向が高まるが、これに女性の場合はDVや育児など家庭の事情が重なる。そして自殺に追い込む最後の要因が有名人の自殺による「ウェルテル効果」と図式化できるだろう。おそらく背景には孤独という悩みを増幅する下地があるような気がする。
コロナによる自省
感染対策は孤独を求める。人間は社会的動物であり、群れる習性がある。「群れる」は以前も述べたように、ネガティブな意味ではない。むしろ人と接して集団を形成し、働きかけ合って、ひとりではできないことを共につくりあげていくという点では、「群れる」ことは人間にとって不可欠であるから、ポジティブに捉えられるべきであろう。
人間は群れることで、ひとりではできないことを実現するから、本性として群れる傾向にある。というより、群れる人のほうが社会で成功していると言ってもいい。その点、私は敗者だ。ただし平時では不利に働いた性格が、有事にはプラスになることもある。自殺報道と分析を精読した後、改めてこの1年の自分を振り返ってみたい。
自分の人生で自殺を考えたことはあるか、と質問されたら、「わからない」としか答えようがない。若い頃はいろいろなことを考え、悩んできたからである。この年齢になったら、もうその心理を憶えていない。だから上で紹介した報道と分析については、切実な課題として取り組むべきだとは思うが、個人的に自分も似たような状況だったかと顧みると、「そうではなかった」となる。
辛かったかと訊かれても、深層心理に押し込めているだけかもしれないから、自信をもって「そうだ」と言い切れるかどうかはわからないが、意識にのぼる表層的な面だけで考えれば、「まったく辛いとも思わなかった」という答え。これは生来、人とのつき合いが得意でなく、ひとりで居るほうが気楽という奇妙な性格によるもので、「これが自分だ」と片づけるしかない。
というよりも、自殺の話をこんなにしておいて、こんな言い方をするのは不謹慎だということは承知しているが、私は「コロナによって蘇った」とまで思っている。そもそもが、それほど忙しい生活でないから、自分について考える時間はあった。しかし外出して人と会う機会が減り、一時的に金銭的にロスがあり、行きつけのカフェには通い続けたが、基本的に外出しなければ、私の意識は自然に自分に向かう。
要するに、私にとってコロナは自分を振り返るきっかけになり、それまでの数十年間の積み残しを一部とはいえ整理してくれた貴重な機会になった。
現実世界の話をすると、私は些少とはいえ、執筆と講演で収入を得ていた。フリーでやるには知名度はないから、まったく豊かではないが、ひどく貧乏というわけでもない。生活水準を落とせば、それなりに生き抜いていける所得だった。コロナ禍でも書くことはできるが、講演はなくなる。2020年2月を最後に、いっさい話が来なくなる。それまではICT(情報通信技術)の話と、政治の話が講演テーマとして半々だったが、一時は両方の依頼が消えた。
2020年9月にICT関連の講演(リモート学習会)が戻ってきたので、収入は安定したが、それまでの半年は早朝の散歩と行きつけのカフェ以外はまったく外に出ず、ただただ家で読書して、たまに文章を書いていた。ただし、行きつけのカフェも2020年4~5月初旬は1か月以上閉めていたので、この間はゴーストタウンと化した街を、マスクをつけながらウォーキングすることだけが唯一の外出であった。
日々、同じことをくり返し、五感で捉える風景にまったく変化がないと、私の場合は、意識のベクトルは自分の内部に向かう。それは講演がなくなるという外的世界からの影響も含んでいる。私はいままでの人生「どう生きるべきか」という問いに固執していた。「立派な人間にならなければならない。そのためには自分の使命を果たさなければならない。だから、すべきことをしなければならない」と。
コロナによってこれが大きく変わったわけではないが、「どう生きたいのか」という問いも加わった。私には自殺願望はなかったが、感染拡大による閉塞感のなか、自殺報道を見続けて、「死ぬなら生きよう」「死を最低ラインと捉えるならば、『どう生きるべきか』という硬い態度は捨てて、『どう生きたいか』でいいではないか。死ぬよりは生きるほうがいいのだから」と。
そう思うと気が楽になる。「使命を果たす人生」のほうが「生きたい人生」より上だが、「生きたい人生」のほうが「死」より上だ。平時なら「使命」を優先すべきだが、「死」についての報道を見るにつけ、「死ぬよりは楽しく生きたほうがいい」と思うようになる。
私の学歴から、多くの人は私を「政治の人間」と見る。自分も大学院に進む際、政治学専攻を選んだのだから、政治の世界で生きていくつもりであった。学部は文学部で、いまは消滅したが「人間科学専攻」に所属していた。それは科学哲学・社会学・社会心理学・文化人類学を包摂した、新領域を開拓したいという運動であった。私は科学哲学に没頭し、その勉強を続けたかったが、大学院に人間科学専攻はない。ゼミの先生につくならば社会学研究科になるが、問題がふたつあった。ひとつは第二外国語を疎かにしていた。もうひとつは「やりたいこと」と「やるべきこと」に引き裂かれていた。
ほんの昨年初めまで、私は「役に立つ」学問と「役に立たない」学問の真ん中で、どっちつかずの不安定な位置にいた。「役に立つ」の厳密な定義は別にして、社会に資する学問か、暇つぶしにしかならず、それを追求しても、人びとの暮らしを改善することのない学問という分裂である。前者が「政治」で、後者が「哲学」だ。
大学院に入る際、社会学研究科ならドイツ語を勉強し直さなければならない。しかしそのために文学部哲学科の原書購読の授業に出たら、なんと出席者は4人。いきなり予告もなく、私に「訳せ」と。予習せず出たものだから、沈黙していると、別の人が訳し始めてくれた。しかしそれが終わると「二度と出てくるな!」と教員に怒鳴られてしまった。これで社会学研究科への進学は断念。
しかし「拾う神あり」で、私が進学する年度から、法学研究科は第二外国語が必修でなくなった。私は少しは英語はできたから、英語と専門科目(政治理論と日本政治史)で高得点を得られ、晴れて合格。
同時に、これで「役に立たない」学問から「役に立つ」学問に移行できた。政治は世の中を善くする営みだから、それを勉強すれば、社会の役に立てる、と。以来、自分でも、他人にも、私は「政治の人間」になった。
幸運なことに、博士課程までは行けたが、博士論文を提出することなく、単位取得後の行先を見つけられずにいると、偶然、留学できることになった。それまでの専門とは関係なく、ゼロからの出発だったので、迷わず哲学部を探した。「自分は政治の人間。一生、役に立つことをしなければならない。だから数年は『役に立たない』哲学をやっても許されるだろう。必ず戻ってくるから」と言い聞かせて、哲学ではイギリスで第2位のユニバーティ・カレッジ・ロンドンに受け入れてもらった(1位はオックスフォード)。
しかし最初からへこたれる。単純に、英語が理解できない。いまになって思えば、発音が聞き取れない上に、哲学に関しては素人だったから中身もわからず、二重苦だった。わからないまま無益に2年間過ごして、学位など何も形にできないまま出てしまう。イギリスは狡猾で外国人には、国内人の3倍の学費を請求する。1年間150万円、2年で300万が消え、貯金が尽きた。
これで「役に立つ」学問である政治に戻り、それから22年間も自分を偽り続けた。いつからか政治は食うための手段として、自分の生活に不可欠な存在になり、自分でも政治の世界で一生過ごすものと言い聞かせてきた。しかしきっかけは政治講演がなくなり、食う手段でなくなったことだが、政治で食えるわけでなければ、「なんでやっているの?」という問いが自然にわく。
食えない、報道レベルとはいえ「死」がつきまとう、自分が感染するという恐怖はないとはいえ、閉塞感から世間の雰囲気は重苦しい。「生きる」という最低ラインに立って、みずからを顧みて、これからの人生をどう生きるのかと自分に問いかけると、返ってくる答えは「政治は好きではない。」そう、私は政治に興味がなかったのだ。「嫌い」というほど大きな存在だとも思わない。ただ気が弱いから、政治について人に期待されると、その期待に応えたい、というよりも応えなければならない、と思ってしまい、それが20年以上積み重なり、自分を偽ってきた。単純に「関心がない」だけだった。
最後の雄叫びが2020年春のロックダウンを正当化するための政治哲学的な考察だった。もうこの時点で現実政治、私の言うところの「政局」には興味がなくなっていた。しかし「役に立たねば」という偽りの執念が民主主義理論に向かう。「民主主義下でロックダウンは哲学的に正当化できるのか」という問いである。そして何も見つけられないまま、この問いにも興味をなくし、秋までに文献をすべて捨てる。
ここから「自分は哲学だ」の第一段階。自分が仕事としていることに「役立つ」なら、哲学を勉強してもよい、というところまで進む。ICTについて学習会の講師をしているから、情報化の哲学的考察ならば許されるだろう。しかしあまりにもマイナーな学問だから、エキサイティングでも、チャレンジングでもない。売れない本だから高価なのに、2回ずつ読んだだけで、電子書籍から削除してしまう。そして2020年秋に、長年の懸案だったヘーゲル『精神の現象学』に取り組む。
とはいえ、これまでの人生で、邦訳は何回か読んでいたが、身についたという感じがしてなかったので、どうせ仕事がないなら、と英語版に挑戦する。そこから2か月、それしか読まなかった。結果として、ヘーゲルは自分向きでないということがやっとわかり、これもキンドルから削除。もう私のタブレットに読む物はない。ここまですべてを捨て去ると、残るものは、心から湧き上がる情熱のみ。
私が本当に探究したいことはなんだったのか。自分が外の世界を知るって、どういうことだろう――この単純な問いこそ、私が追い求めてきた。この問いにダイレクトに答えてくれる本はないだろう。過度な期待はせず、役に立たない本を楽しんで読もう、そんな気持ちにまで辿り着くと、重荷がとれて、生きる意欲がわいてくる。
学歴は一生つきまとうが、私の心のなかでは、私はもう政治の人間ではない。私にとって政治は終わった。そう思うと、コロナ以外のニュースに関心がなくなる。日本だけでなく、アメリカやイギリスの政治を這うように追跡してきた人生とはお別れ。
しかしこれは数年前から周囲に働きかけてきたことで、コロナで加速されただけでもある。講演はせいぜい1時間しゃべるだけだから、自分を偽れる。おカネにもなるし。しかし私にとって書くことは人生である。書くことが好きだ。だから政治については書きたくない。そんなことに「書く」という私にとって神聖な行為を汚されたくない。
だから数年前から、わがままを言って、いくつかある連載をすべて政治以外のテーマにしてもらった。ひとつはICTについて、もうひとつは人工知能の哲学について、さらに別のところでは、情報通信の真面目な政策論議について。学習会もICT関連しか来ないから、コロナでこの流れが完全に定着した。
不謹慎だが、私はコロナ禍を、自分を振り返る機会として活用して欲しいと思ってきた。自殺という悲しいニュースに触れるたびに、なんとかできなかったのか、と憤るとともに、生きてさえいれば、嫌いな過去を捨てることもできたのに、と悔やまれる。
私にとってコロナの15か月は「自分探しの旅」だった。そして結論は「たぶん、このままではないだろう。」それまでの自分の欠点は「これを(たとえば政治を)永遠に続けるぞ」と思い込むことだった。いまは「自分は気まぐれだから、すぐに変わる」と肩から力を抜くことにした。来年のいま頃、また政治哲学の本を読んでいるかもしれない。でも、もう日米英のニュースを見なくなって2年近くになるから、現実の政治つまり「政局」に戻ることはないだろう。そう思えただけでも、自分にとってコロナは転機であった。
1)https://www.nikkei.com/article/DGXZQODG05BX30V00C21A1000000/
2)https://www.nikkei.com/article/DGXZQODG141IM0U1A310C2000000/
3)https://www.mhlw.go.jp/content/12201000/000707293.pdf
4)https://www.igaku-shoin.co.jp/paper/archive/y2021/3415_01
森田浩之(モリタ・ヒロユキ)
東日本国際大学客員教授
1966年生まれ。
1991年、慶應義塾大学文学部卒業。
1996年、同法学研究科政治学専攻博士課程単位取得。
1996~1998年、University College London哲学部留学。
著書
『情報社会のコスモロジー』(日本評論社 1994年)
『社会の形而上学』(日本評論社 1998年)
『小さな大国イギリス』(東洋経済新報社 1999年)
『ロールズ正義論入門』(論創社 2019年)