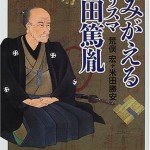- 2020-9-1
- お知らせ, 論創通信, オイル・オン・タウンスケープ
谷の底の〈悪所〉───MIYASHITA PARK 第三号(前編)
中島晴矢
 《MIYASHITA PARK》2020|カンヴァスに油彩|606 × 500 mm
《MIYASHITA PARK》2020|カンヴァスに油彩|606 × 500 mm
私は新国立競技場の前でシャトルランをしていた。
東京五輪開会式が行われるはずだった日の夕方、競技場を背景にして走っては引き返し、また走っては引き返す。辺りには無機質なドレミの音階が反響している。オクターヴが1セット鳴り終わるまでに、とにかく20メートル間を走り抜けなければならない。徐々にBPMが上がっていくのに伴って、鼓動も早まり、呼吸は荒くなる。息苦しい、マスクをつけたままランニングをするのは自殺行為だ。勢いよくマスクを振り払うと、道路を挟んだ向かいの舗道に溜まるギャラリーから笑い声が漏れた。競技場の向こうからは、オリンピック反対を掲げているらしいデモ隊の怒声が微かに聞こえてくる。
競技場の周囲はぐるりとフェンスに囲まれて、敷地内に立ち入ることは禁じられていた。さらにその周辺を、テロやデモへの警戒だろう、たくさんの警察車両が取り巻いている。むろん競技場は既に落成していたが、しかし未だスタジアムとして機能しておらず、建築というよりも巨きな楕円形の物体として空間を占拠している。神宮の杜に出来た最新の墳墓───それはあたかも祝祭の後に廃墟化する〈未来のレガシー〉を先取しているかのようだ。そんな予見性を胚胎したオリンピックの聖地に、規則的な機械音が虚しく木霊している。
ここでシャトルランをするのは三度目だった。最初は赤いクレーンが群居する普請中の2017年。二度目はひとまず建物が完成した2019年。それらは映像作品として公開したが、今回は観客を迎えたパフォーマンスとして実践している。もちろんシャトルランはオリンピック種目ではなく、小・中学校で実施される単なる持久力測定テストである。
私は子供の頃からシャトルランが苦手だった。同じところを行ったり来たりするだけで、どこにも辿り着けず風景は変化しない。加速度的に早まる音が焦燥感を掻き立てるばかりで、走者はただただ疲弊し、やがて体力の限界と共に一人また一人と脱落していく───もしかすると、それはオリンピックへと邁進する東京ないし日本のアナロジーではないかと思えた。どこへも前進することなく右往左往し、心身を摩耗する徒労感ばかり溜め込んで、やがてばったりと倒れ込むシャトルランナーとしての現代日本……そうしたコンセプトで始めたアクションだったが、まさか2020年8月、オリンピック自体が延期される運びになるとは思いもよらなかった。文字通りどこにも行けず、何の景色も見ることができなくなるなんて。レーンを降りることすら許されず、息もたえだえに持久走は来年度まで継続される。
Bluetoothスピーカーから鳴る教育委員会的な声音の女性によるアナウンスで、カウントはゆうに70回を超えていると気づいた。もうとっくに困憊し、気力だけでみっともなく身体を動かしている状態だ。ふだん全く運動をしないのだから当たり前だろう、サングラスをこれ見よがしに投げ捨てる。見物客から声援が飛ぶものの、80回を過ぎたあたりで合図音についていくことができなくなり、憔悴しきって歩道の真ん中に倒れ込んだ。
と、リレーのバトンを円滑に受け取るように、すぐ秋山佑太が動き出す。そう、これは三名の作家によるイヴェントなのだ。外苑前にあるヴィンテージビルの一室、「FL田SH」というアートスペースで開催している展覧会と連動している。以前から東京五輪の開催時期に被せて企画を練り、かつて正式に採用されていたオリンピック種目「芸術競技」を概念として召喚して、三者三様の身体性を競い合うことにしていた。もちろん、近代五輪に対する拭い切れない不信に貫かれた、アイロニカルな営為として。
しかし世界的なパンデミックによって、オリンピックの方が地滑りを起こし流れ去ってしまった。日々変化する状況に振り回されながら、それでも手探りで開くことにした展覧会の最終日、わざわざ移植された内実を伴わぬ「スポーツの日」に、言うまでもなく非公式で開催しているのがこの「オープニングセレモニー」だ。「オープニング」というタイトルの逆説は、展示最終日であることと、FL田SHの入るビルそのものがオリンピックを機とする再開発によって、本展を最後に解体されることに拠っていた。そうしたコンテクストの末に敢行したセレモニーは、自粛ムードの中でなかなかの観客を集め、FL田SHから競技場までぶらぶらとツアーし、特別な許可も取らず、しかし〈公道〉における所与の権利の当然の行使として、競技場外周の路上に皆でたむろしている。
アーティストで建築家でもある秋山さんは、おもむろに背後の街路樹に登り始めた。何やら白い小さな物質を木の幹や枝に貼り付けたり、根元の植え込みに撒いたりしている。そうした儀式的な振る舞いを一通り終えると、今度は道路を渡って競技場の真ん前に胡座をかいた。ジップロックから灰色の粉末を取り出し、ペットボトルの水と共に口に含んで咀嚼する───口内でコンクリートを捏ねているのだ。
一連の行為は出品作に対応していた。展示では、口腔で生成されたコンクリ塊を数台の3Dプリンタで出力し量産。街路樹に散種していたのは、このバイオプラスチックからなるオブジェだった。また、空間中央に腐葉土の詰まったコンテナボックスを重ねて配置し、壁面には強烈な匂いを発するぬか床や、そこで発酵させた野菜の漬物などが、ある種の彫刻としてインストールされている。土からは雑草が生い茂り、ミミズや芋虫がもそもそと動く。こうした作品群は、コロナ禍に秩父へ遁世したという彼が、建築家あるいは現場作業員として、自然環境と直に接触しながら生きていくことの表明であった。また、それは都市における〈生産ー消費〉のサイクルとは別種の、ヴァナキュラーな〈循環〉に身を委ねる宣誓でもあったろう。その決意のようなものは、先述の口内でのコンクリート生成が記録されたディスプレイに映し出される、憤怒とも悲哀とも取れる涙ぐんだ瞳に宿っているように思えた。
捏ね上げたコンクリートを路上にベチャッと吐き出して立ち上がる。行方を見守っていた観客の喝采と共に、こうして秋山さんらしい重厚なパフォーマンスが終了すると、リレーのバトンはアンカーへと渡る。すぐに背後からぬっとトモトシが現れた。
「TOKYO2020」のTシャツ姿のトモトシくんは、引いているリヤカーの荷台から、丸々とした生魚を一尾とりあげる。そして魚体を自身の腹の辺りで抱えると、人形使いの黒子のようにして、ストリートをゆらゆらと泳がせ始めた。サバだろうか、あたかも潮の流れのままに舗道を遊泳する青魚は、徐々に競技場の仮設壁に近づいていく。すると突如、魚は踊るように身を翻し、ぱしゃぱしゃっとその壁の向こうに飛び込んでいってしまったのだ。
観衆から「きゃっ」とも「ひゃっ」ともつかぬ悲鳴が洩れ、集団はある異様な興奮にじんわりと包まれた。トモトシくんは何食わぬ顔で平然とリヤカーに戻っていく。次に取り出したのは立派なタイだ。観客を引き連れて再び競技場沿いを揺蕩い、道路の中洲にあるオレンジ色のラバーポールを水草を食むようについばむ。そうした優雅な時の過ぎゆくままフェンスに近づくと、タイはまたぱしゃりと跳ねて向こう側に消えていってしまった。
私たちが目撃しているのは、紛れもない〈規範の侵犯〉だ。身一つで都市に介入することを信条とするアーティストである彼は、人々がふだん自明視している境界線を軽やかに越えていく。今回、魚を媒介として決行されているのは、幻と化した2020年のオリンピックに対する、トモトシならではの孤独なテロリズムだった。
最後に登場したのはヒラメだった。路面と平行に、低いところをひらひらと這うように泳いでいく。競技場の楕円の角を曲がり外苑西通りに出ると、私服も含めた警官が増えてきた。さっきから明らかに私たちの観客ではない人間がずっとカメラを回している。おそらく公安だろう。展示ディレクターの吉田くんが警戒しているのがわかった。トンネルの先からはシュプレヒコールが地鳴りのように轟いてくる。そんな物々しい雰囲気の中、ヒラメは熱源の方向へと潮の流れに身を任せる。日は暮れかかっていた。日没と歩みを合わせるように喧騒へと吸い込まれていくトモトシの背中が、徐々に小さくなる。やがて人混みに紛れて見えなくなったかと思うと、すぐ引き返してきた。彼の手にはもう何もない。ヒラメもまた壁の向こうに潜り込んで、既に競技場の陰で身体を休めているに違いなかった。
こうして「オープニング・セレモニー」は終幕した。私たちは来た道を戻っていく。泳ぐように、一群れの魚影になって。
*
新しくなった銀座線渋谷駅のホームは、天井に湾曲したアーチが連なって、まるでクジラの腹の中だ。呑み込まれた小魚の気分になる。左右の改札口どちらを出ても商業施設に直結するつくり。咽喉か肛門か───どっちもどっちだと尻の穴を抜け渋谷スクランブルスクエアへ。流れるような動線で、目に入るもの全てが商品だと言っていい。ここは大海原というより流れるプールだ。ブティックやカフェに囲繞された水路を縫って、ようやく陸地に身を投げ出す。
東口は悉く工事中だが、駅周辺に跨がる歩行者デッキはある程度完成しているようだった。広々とした立体的な歩道が、スクランブルスクエア、ストリーム、そして警察署へと伸びている。この通路は着々と整備されつつあり、9つの再開発プロジェクトは既にいくつも開業を迎えていた。計画的に配された施設間は滑らかに繋がっている。もちろん、そこから零れ落ちるものをノイズ・キャンセリングするようにして。
アミダクジみたいなファサードを有する渋谷ストリームの最上部には、「Google」のロゴが掲げられていた。世界最大の検索エンジンに見下ろされているのだから、もはやこの街に〈外部〉は存在しないのだろう。デッキからスムーズに接続されたエスカレーターを伝って、チェーンの飲食店や雑貨屋を抜ける。大階段を降りた広場は「水辺空間」と唱われていた。わざわざ地面に丸く縁取られた「ビュースポット」が明示され、そのサークルの内側に立つと、ちょうど電飾に覆われた渋谷川の全容が眺められる。ほとんど暗渠化し、雑居ビルを背にちょろちょろと護岸を流れる渋谷川の無骨さが、過剰に飾り立てられたその「再生」によって、むしろ酷薄なほど浮き彫りになっているように思えてならないのは、私だけだろうか。
西口へは、まだ開発途上なのだろう、カマボコ屋根のなくなった旧東横線のホームをくぐって行かねばならない。その高架下の246通りは、かつて、ホームレスを追い出すために描かれた壁画を巡る議論が起きたエリアでもある。都市空間における「排除アート」問題の先駆だったように思えるそこは、現在ホームレスも壁画もなく、ただ工事中の仮囲いに塞がれていた。
そんな246に沿って左手に広がっていた桜丘町一帯は、もう跡形もなく消失している。2023年の竣工を目処とした再開発によって、町そのものが更地になってしまったのだ。区画内には所狭しと特大の重機が並んでいて、ここにもむろん複合商業施設ができる。その桜丘への入口を除き、西口周辺にも件の歩行者デッキは大方出来上がっていた。駅方面と、東急プラザ跡地に建った渋谷フクラス、そしてセルリアンタワーの面する坂の麓が、やはりぬかりなく結ばれ、その一層上には首都高速道路が変わらず被さって空を貫いている。
そう、言うまでもなく渋谷は再開発の真っ只中にある。東京における〈スクラップ・アンド・ビルド〉の中心地だ。2020年の東京オリンピックを契機として、五輪が延期されようとも、当然その開発は止まることなく進行している。
そもそも、渋谷は1964年の東京オリンピックに際して大きく変化した地域だ。首都高や新幹線の開通といった東京全体の開発に加えて、特に主要会場となった神宮外苑地区と駒沢公園地区、そしてその2地点を結ぶ渋谷地区は、大規模な改造が施されている。そうした国家的な事業を境に、代々木や原宿を含めた渋谷周辺のエリアは、巨大な盛り場へと飛躍的な成長を遂げたのだ。
それゆえ、2度目の東京五輪に端を発するこの再開発もある意味で妥当と言えよう。オリンピックは、何より都市改造の最大の方便なのだから。……
そういえば高校時代、東口の歩道橋から駅の方を望むのが好きだった。
歩道橋の足元には山下書店があった。24時間営業で重宝しており、よく軒先の雑誌コーナーで立ち読みをしていた。特に通い詰めていたのは、高校2、3年の頃だ。
その時分、私はとにかく勉強ができなかった。中高一貫の私立校に入学して以来、全くと言っていいほど勉強せず、ひたすら遊び倒していた私は、無為な生活の必然的な帰結として、丸腰で受験の準備を始めるしかなかった。ツケが回ってきただけ、自業自得である。周囲の友人たちは、一緒に遊び呆けているように見えながら、その実、陰に陽に周到な努力を積み重ねており、高2の夏の終わりには自然と受験生へとモードを切り替えていた。しかし私はその転身に完全に乗り遅れる。要するに、おそろしく要領が悪かったのだ。模試を受けても箸にも棒にもかからず、英語など何を聞かれているのかすら理解できない有様。なにしろ、その時点でbe動詞と一般動詞の区別もロクにつかなかったのである。
山手線の新南口付近にある雑居ビル、その一室に入った英語塾へ苦し紛れに通った。明治通りを少し行って曲がったところ。せめて英語だけは基礎から立て直さねばと思ってはいたものの、出席してもちんぷんかんぷんの授業に通うのが苦痛で、塾をサボっては近くのドトールかベローチェで時間を潰す。ただカフェの座席を温めていることにも飽きると、明治通りを引き返し、山下書店へ駆け込んでは、現実逃避のためだけに片っ端から本を手に取って貪り読んでいた。そうして塾が終わる時間まで適当に油を売り、親へのアリバイをでっち上げてから這々の体で帰宅する。長い人生の中で大したことじゃない、と今なら笑い飛ばせるのだけど、振り返れば当時は随分ナイーヴで、受験に失敗しつつあることが苦痛で仕方なかった。
帰り道、山下書店から歩道橋を登って駅方面に目をやると、渋谷の街並みが一望できる。
街の喧騒はそのままに、所々でネオンが瞬いている。地下鉄であるはずの銀座線が、ビルの合間から地上に出てわずかに走り、またすぐビルの合間に吸い込まれていった。眼下に広がるのは、谷底の風景だ。
その名の通り、渋谷は明確な谷地である。5つの台地に挟まれた、すり鉢型の地形に位置する〈悪所〉。国木田独歩が『武蔵野』で描いたように、東京の郊外として鬱蒼たる林に覆われていたこの田舎町は、ターミナル駅の盛り場として発展し、戦火を経てなお闇市の活気をもって復興した。さらに先述した64年の大改造、80年代の東急や西武といった企業戦略による広告空間化、90年代のストリート化やゼロ年代の再郊外化を経て、2020年現在、またぞろ街全体が蠢動している。
歩道橋の上から見渡す渋谷は、自らの矮小さとは無関係に、ただそこに横たわっていた。それに私は何か救われるようなものを感じながら、しかし自分だけが置いてきぼりを食ったみたいに悲しくもなって、しばし涙ぐむ。
ぼんやりと滲んだ渋谷の景色は、なぜかいつも転倒して見えた。
足早に歩道橋を降りていく。その歩道橋もなくなって、歩行者デッキに取って代わった。周囲にはいくつも高層ビルが建ち、駅構内とヒカリエを結ぶ空中回廊で銀座線は隠れている。背中の奥に広がるのはコンクリートの更地だ。そして、山下書店は潰れ、コンビニになった。
こんな風に渋谷を生きてきた私には、私自身のリアリティで今の渋谷を眼差すことしかできない。それがあくまで個人的な郷愁であろうと。この街の底から。
(なかじま・はるや)
過去掲載号はこちら