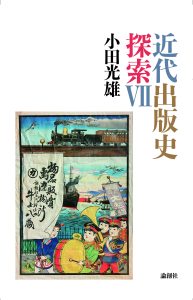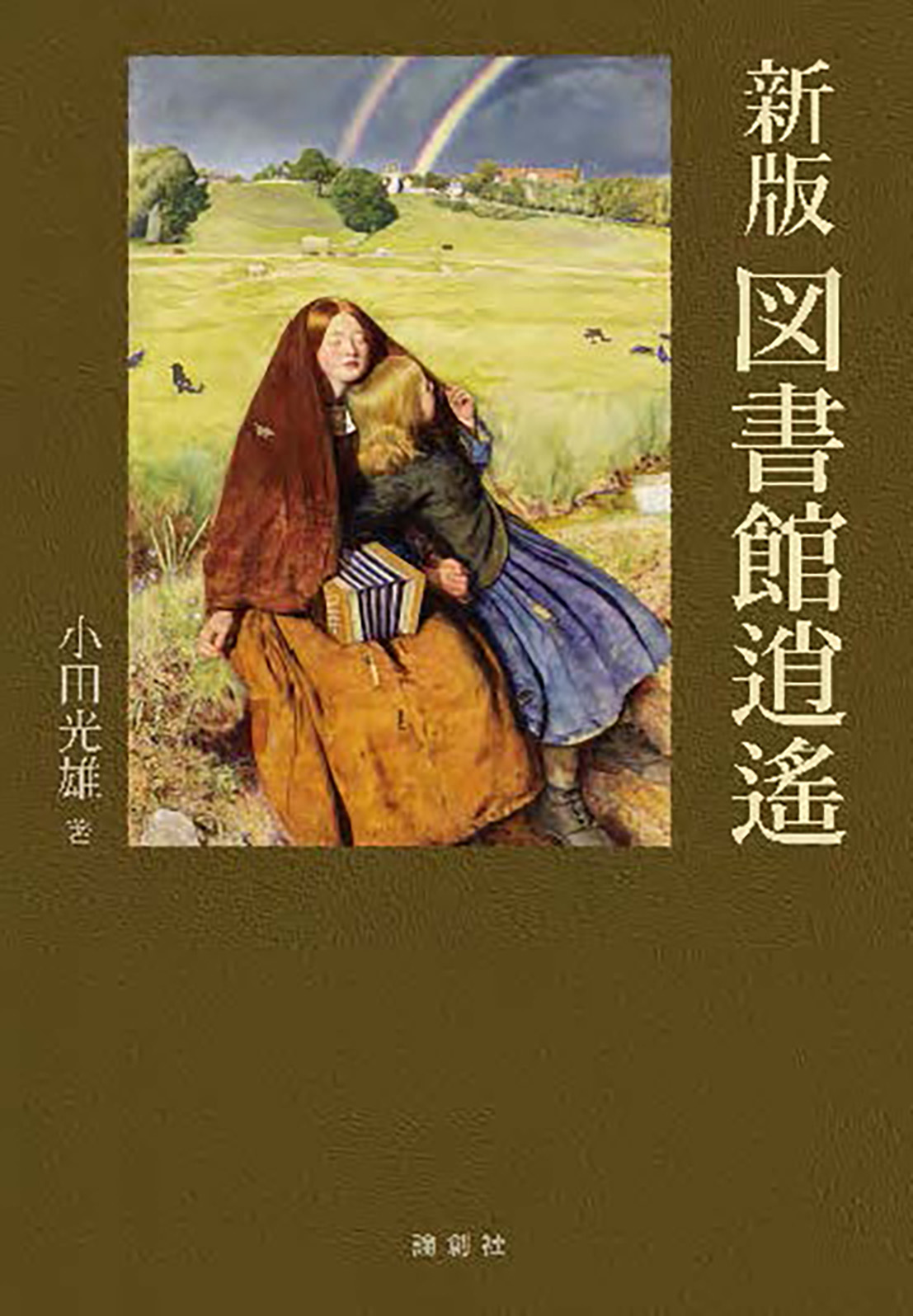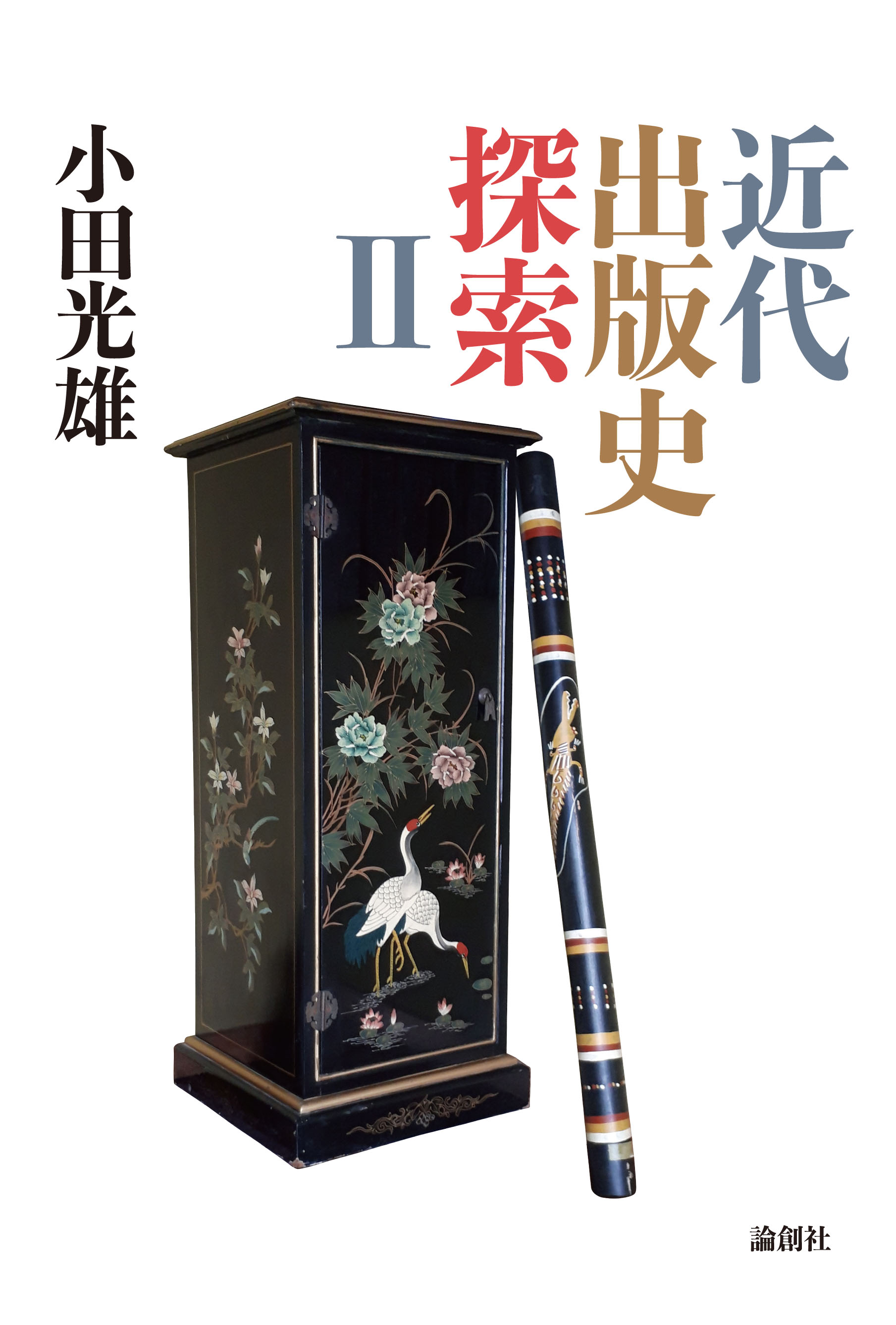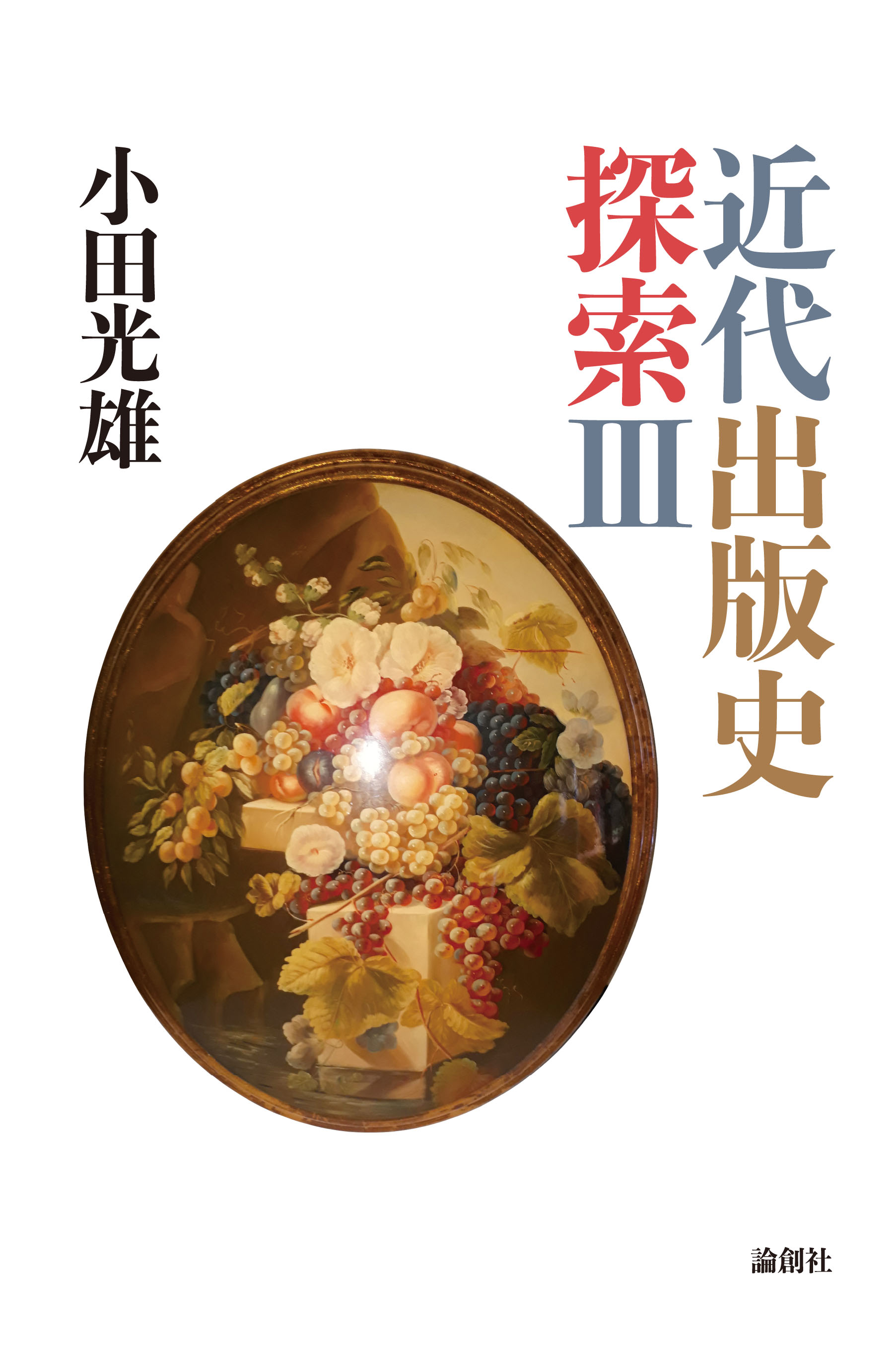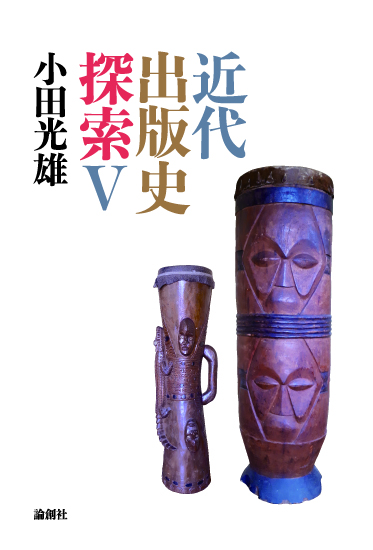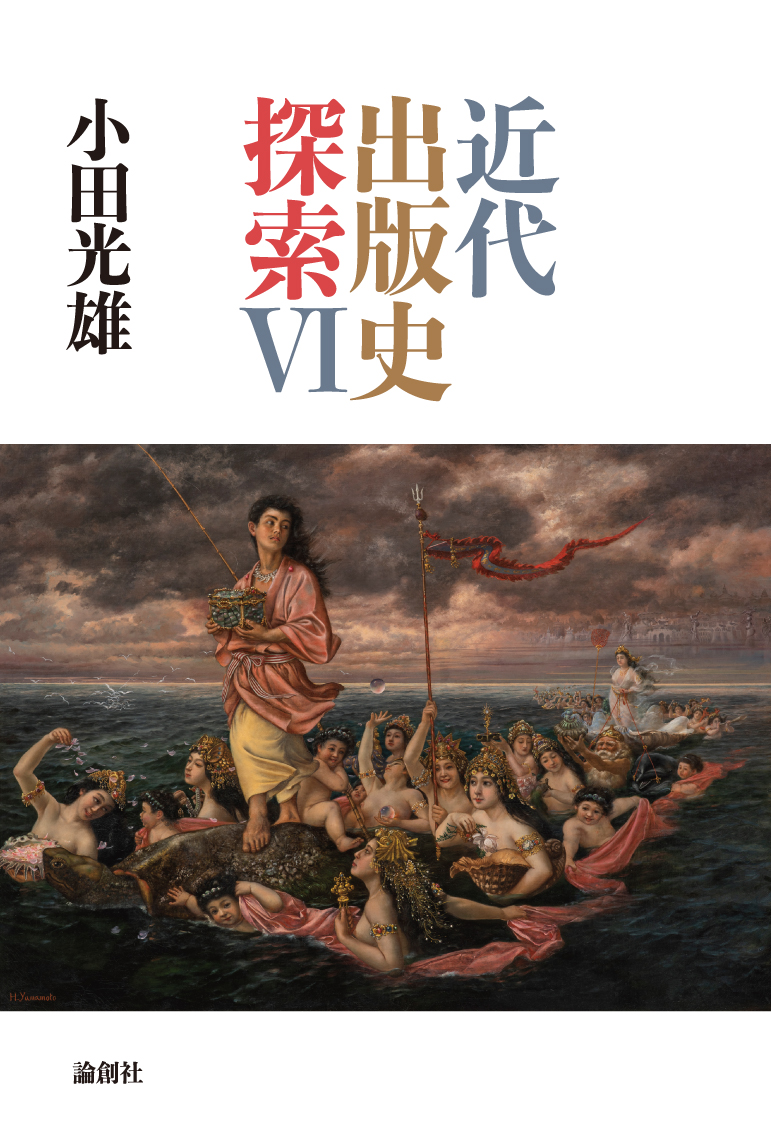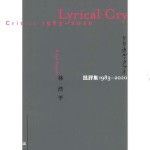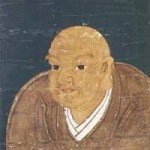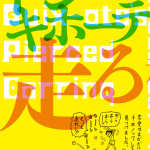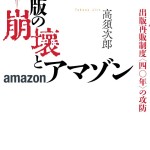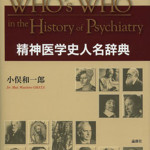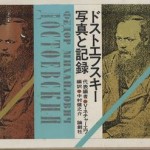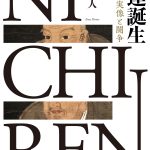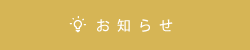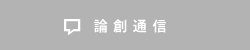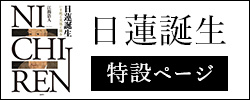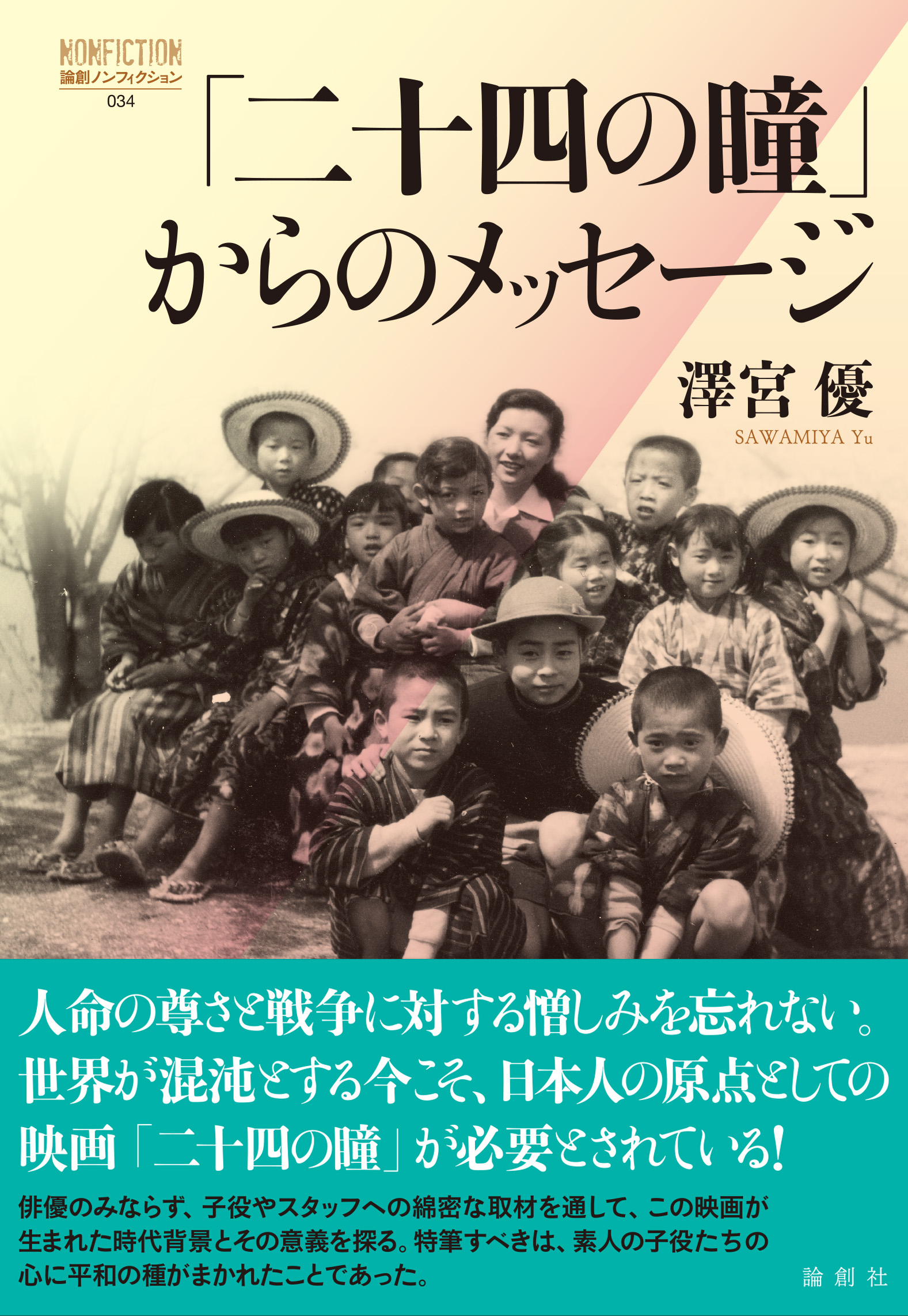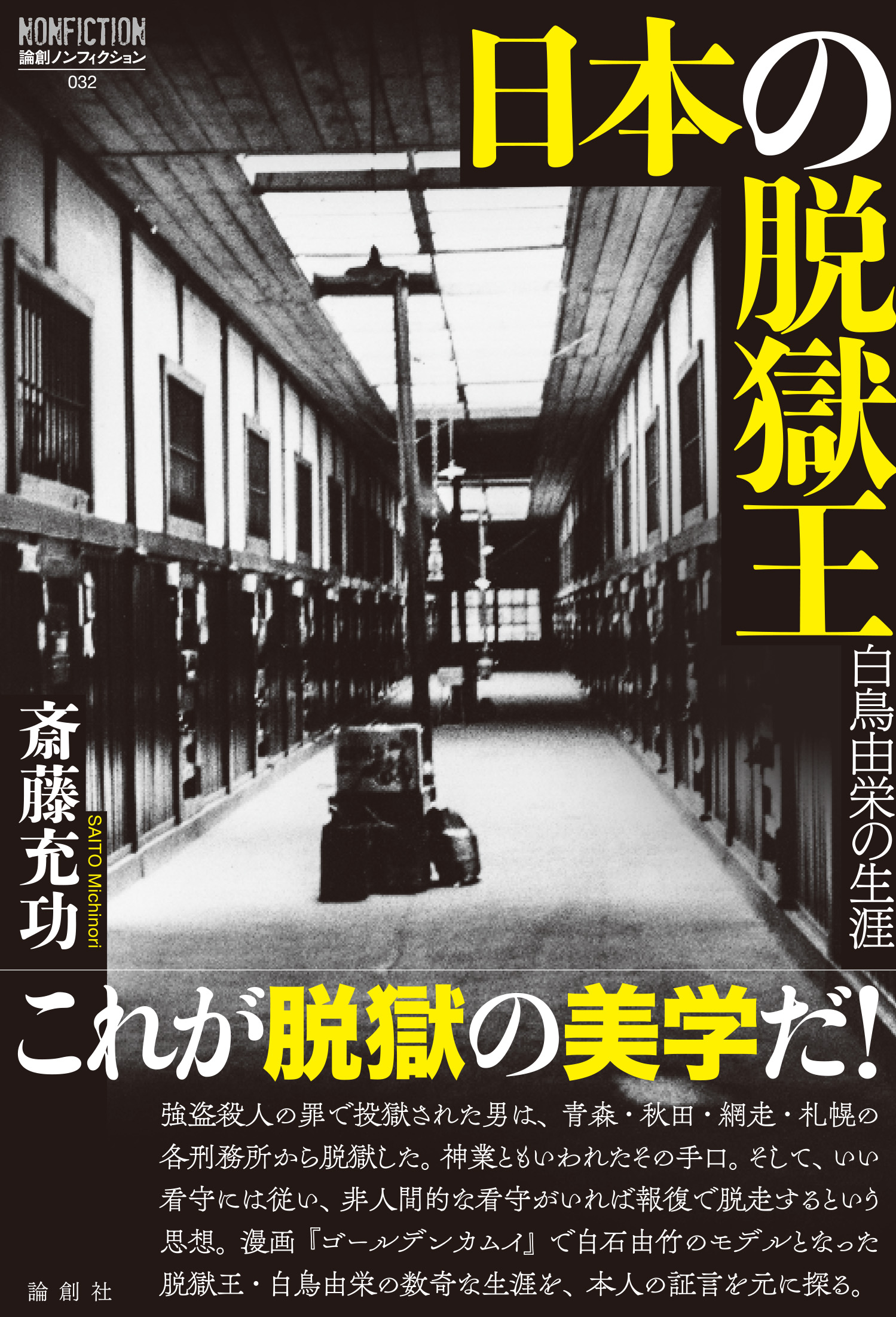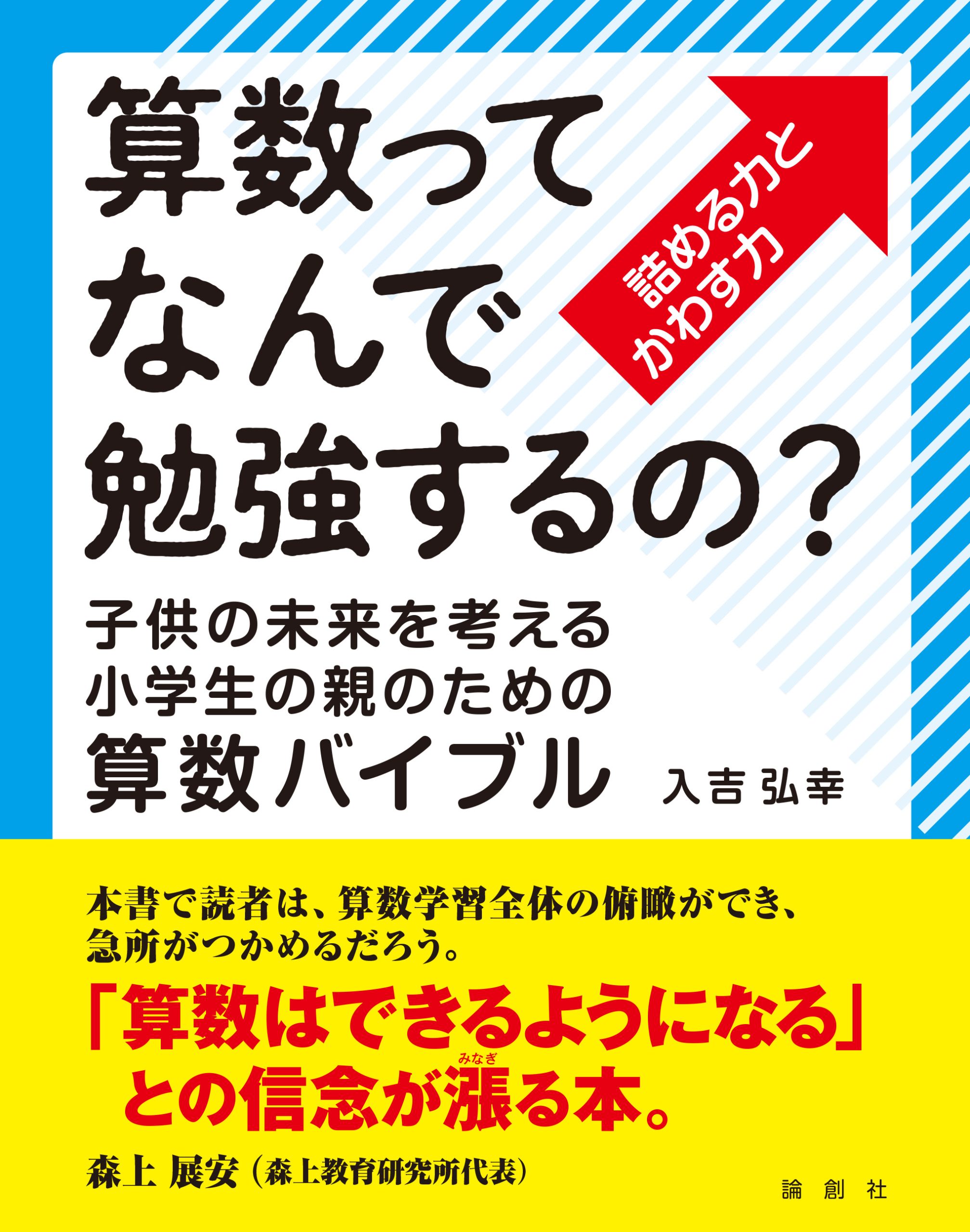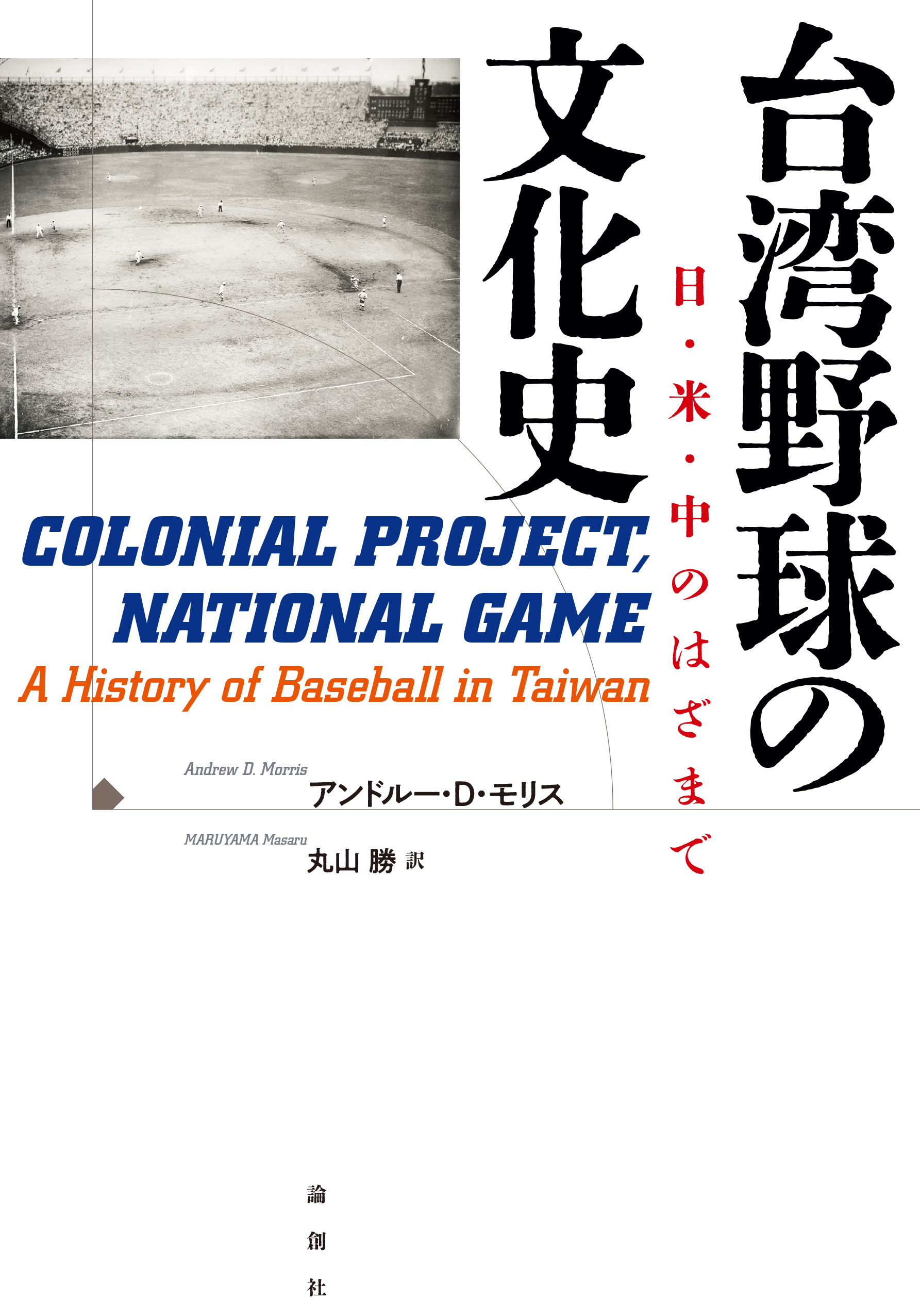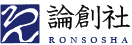- 2024-6-15
- お知らせ
(100)『魔像』と『平田弘史劇画創世期傑作選』
本連載94で短編誌『魔像』を挙げたが、これも『影』や『街』と同様に、農村の貸本屋で読んでいる。
その剣豪ブック『魔像』の別冊で、平田弘史特集『つんではくずし』『四十万石の執念』『我が剣の握れる迄』,『士魂物語』の第十、十二巻として、やはり平田の『侍』『刀匠』が手元にある。もちろん当時の貸本そのものではなく、1998年にサリュートから刊行された「日の丸文庫『魔像別冊単行本』完全復刻板」の『平田弘史劇画創世期傑作選』全五巻、これも浜松の時代舎で入手したことによっている。
これらも貸本屋で読んでいたかといえば、確たる記憶はないのだけれど、当時の少年マンガとしての竹内つなよし『赤胴鈴之助』などに比べ、まったく異なるマンガだという印象は貸本屋を通じてのものだったはずだ。この少年画報社版『赤胴鈴之助』も小学館クリエイティブによって復刻されている。その頃は当然のことながら、劇画という言葉も知らなかったが、それは平田の貸本マンガに最もふさわしかったのではないかと思える。ちなみに今回の復刻に付されたキャプションによって、『魔像』の別冊の三冊が1960、61年の刊行で、広田が23、24歳の作品、『士魂物語』の二冊がいずれも64年、26歳の者だと知り、その若さにも驚きを覚えた。
そして『平田弘史劇画創世期傑作選』解説に寄せられた少年画報の戸田利吉郎の「孤高の作家・平田弘史」における次のような一節に納得した次第だ。
平田弘史ほど短期間のうちに上達し、自分の画風を確立した漫画家は他に見当たらない。デッサンをはじめ、書や日本画の特別の素養もない彼が何故、短期間のうちに巧くなったのかは知る由もないが、デビュー後二年足らずのうちに貸本屋の人気を独占する勢いとなった。そして昭和35年4月に短編集『魔像』の別冊として、初めての長編である平田弘史特集『四十万石の執念』が刊行された。
平田弘史の作品の魅力は何かと問われると、何より作中の登場人物たちのひたむきさが挙げられる。下級武士や差別された主人公たちが、がんじがらめの状況から這い上がる姿を好んでリアルに描き、時として、いさぎよく美しく描いてみせた。創作の原点にあるものは、作中の作者の狂気とも思える思い入れだ。
確かに平田の貸本マンガがもたらしたイメージはそのようなものであるゆえに、私などの年少の読者にとって、その絵柄と文法から平田はかなり年配の人物だとばかり思いこんでいた。それに戸田がいうように、平田のデビューが1958年で、『魔像』の別冊刊行の頃に不動の人気を誇っていたことはまったく知らずにいた。それからこれも戸田が述べているように、三島由紀夫が平田のファンで、上野のガード下の貸本屋取次に出かけ、平田の作品を買い求めていたのであり、これも後に知った事実だった。
そうした貸本マンガにおける平田の人気や受容史ゆえに、1978年の双葉社の「現代コミック」11として、一巻本の『平田弘史集』、72年には青林堂の「現代漫画家自選シリーズ」の『始末妻』が編纂刊行されていたことになろう。また平成に入って、日本文芸社から『平田弘史傑作集』全十巻も刊行されるに至っている。だがその一方で、石子順造『戦後マンガ史ノート』(紀伊國屋新書)の「戦後マンガ史年表」にあるように、1961年には『つんではくずし』で部落民を描き問題を起こし、62年には『血だるま剣法』に対し、民科、部落解放同盟が抗議している。復刻の『つんではくずし』にそれはうかがわれないけれど、ネームの打ち直しに際して修正削除されたとも考えられる。
それらのことはひとまずおくにしても、石子の「同年表」で重要なのは66年6月のところに「青年劇画誌のはしり」として『コミックmagazine』(芳文社)の創刊が示され、8月からは「武士道無惨伝」が始まっている。先の双葉社の『平田弘史集』収録作品は「武士道無惨伝」連作で、8編のうちの7作は『コミックmagazine』に掲載されたものである。つまり言い換えれば、この『平田弘史集』は日の丸文庫(光伸書房)の短編誌『魔像』の平田特集の貸本屋マンガではなく、一般書店のための単行本化という色彩を伴っている。それは掲載誌の『コミックmagazine』にしても同様だったのである。そのように考えてみると、同時代に企画刊行された筑摩書房の「現代漫画」が戦後の広範なマンガ全集の試みであることに対して、双葉社の「現代コミック」はその13人のマンガ家のラインナップからして、貸本マンガの集成とも見なせるのである。
そのキーパーソンは平田昌平(兵)だと考えられる。平田は少年画報社や秋田書店を経て、芳文社に入り、66年に『コミックmagazine』を創刊し、平田弘史をコアとし、貸本マンガ家たちを召喚している。この『コミックmagazine』の成功を受け、67年 には『COM』(虫プロ商事)、『週刊漫画アクション』(双葉社)、『月刊ヤングコミック』(少年画報社)、『月刊ビッグコミック』(小学館)『プレイコミック』(秋田書店)が続々と創刊されていったのである。
その一方で、平田昌兵はさらにKKベストセラーズに移り、73年にはワニマガジンを設立し、『漫画エロトピア』などを創刊し、貸本マンガの系譜を引き継いでいくことになる。『平田弘史劇画創世期傑作選』の出版にしても、彼が関係しているのかもしれない。
(おだ・みつお)
本連載の執筆者である小田光雄さんが2024年6月8日にご逝去されました。
「本を読む」の連載は今回で最終回となります。
これまでもご愛読いただき誠にありがとうございました。
また、本連載をまとめた『近代出版史探索 外伝Ⅱ』を近日中に刊行する予定になっております。
バックナンバーはこちら➡︎『本を読む』
《筆者ブログはこちら》➡️http://d.hatena.ne.jp/OdaMitsuo/
【新刊のご案内】
『近代出版史探索Ⅶ』
【既刊のご案内】
好評発売中!
小田光雄さんの著書『古本屋散策』が第29回Bunkamuraドゥマゴ文学賞を受賞!