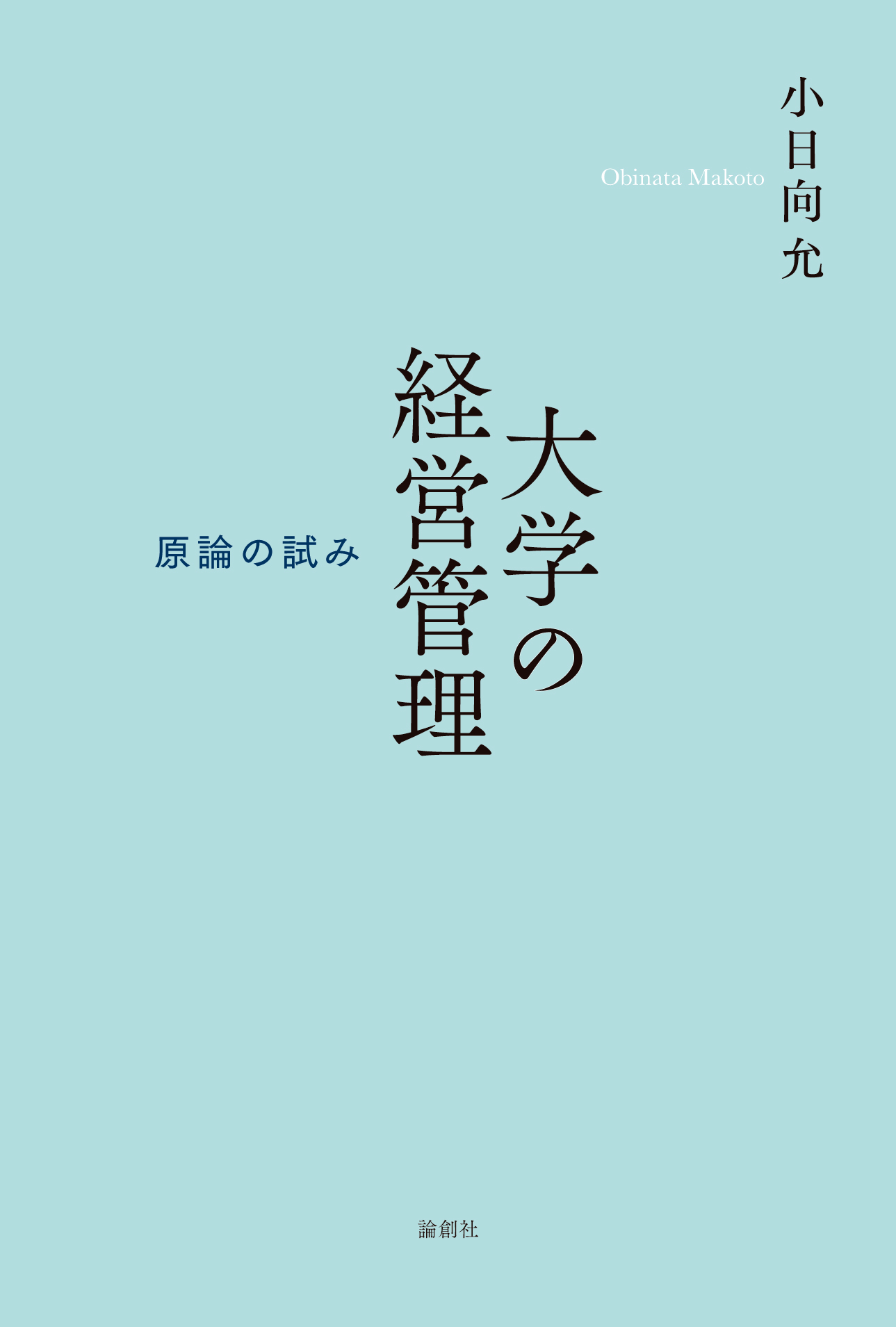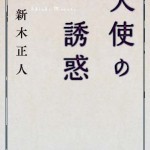- 2021-6-28
- お知らせ, 論創通信, 矢口英佑のナナメ読み
No.40 『大学の経営管理 言論の試み』
矢口英佑〈2021.6.28〉
現在、大学という教育機関に在籍する人は短期大学生を含めると、18歳人口の60%近くになっており、社会人や大学院生を含めれば、この数字はさらに伸びることになる。したがって大学の規模、学部や学科の種類、教育内容、教員の顔ぶれ、課外活動、就職先企業等々といった関心から大学を見る目を持つ人は多いだろう。しかし、利潤追求が何よりも優先される一般企業とまったく同じとは言えないにしても、大学も安定的経営が求められる組織体であることを真っ先に思い浮かべる人はそう多くないはずである。
本書は少数の人びとが目を注ぐにとどまるにちがいない経営組織体として捉える視点から大学の経営管理のあるべき姿とそこに至る道筋を示している。ただし、本書は決して少数の関心者のための一書ではない。
ところで、大学は国立、公立、私立大学と3種類に大別される。言うまでもないが、法人化されているとはいえ国立大学は国が、公立大学は自治体が経営母体である。それに対して私立大学は著者の言を借りれば、
私立大学は学校法人により設立され、経営管理と教育研究その他の活動を含めて学校法人が権利義務の主体として最終責任を負うことになる。設置主体の学校法人と、設置される大学の組織は二重構造であり、一般的な企業体や国立大学法人、公立大学法人の一元的な組織運営との決定的な相違点である
となる。
日本では大学生の約75%が私立大学生である。その意味では、著者の「大学の経営管理」の主たる対象が私立大学とみて差し支えないだろう。そして、一般企業や国公立大学との「決定的な相違点」=二重構造の指摘は、私が本書が少数の関心者のための一書ではないとする理由にもなっている。
著者が言う二重構造とは、一般的に大学と呼ばれる組織体は学校法人としての理事会と教育研究の組織の大学とに分かれていることを指している。
学校法人の組織は、私立学校法の定める理事会、監事、評議員会で構成され、理事会は理事長、理事で構成され、学長は理事の一員となる。一方、教育研究の組織である大学は教授会に所属する教員や校務に関わる職員で構成され、学長は学校教育法の言い方に従えば教職員を「統督」することになる。
この二重構造が一般企業と大きく異なることは著者が述べている通りであり、上意下達方式ですべてを進めることができない点である。法人と大学という二重構造の組織では意思決定を行なうに際し、対立や葛藤が起こりやすく、法人と大学、大学の教授会内部、専門職権限、教員と職員といった関係で互いの理解と納得のうえで進めなければならない。たとえば、教員の採用、任用職位、昇任などは大学(教授会)が主に行ない、職員の採用、昇任は法人である。また大学の各部署への職員の配属を決めるのは法人であって大学の都合では決められない。したがって、
往々にして企業人が学校法人のトップに就任した場合に意思疎通に齟齬を来すのは、大学の特質、教育研究は何のために行なうかの理解、効率・効果を早急に求められない特質のあること、どのような配慮が必要かなど、十分な理解と納得のないまま企業感覚で運営しようとする
との著者の指摘は、大学という組織の運営の難しさを突いているとも言える。
たとえば、大学に在籍した4年間、職員たちがきちんと丁寧に対応し、学びたいこと、学ぶべきことがしっかり身につき、学びやすい環境が整い、教師や仲間との交流も順調で、課外活動も就職活動も思い通りにでき、無事、社会へ飛び立てたと多くの学生が感じる大学があるとしよう。それには学生個人の努力も関わることは言うまでもない。さらに本書に即して言えば、法人と教職員たちが組織の二重構造を十二分に理解し、構成員の意思疎通が互いの努力で実践され、経営組織体として経営が安定していた証明とも言える。つまり本書の書名となっている「大学の経営管理」が確実に実践されていたことになる。
しかし現在、多くの大学はこの経営管理という面から見れば、道半ばであり、「大学の経営管理の研究は、まだ緒についたばかり」(本書「はじめに」)と著者は言う。
なぜなのか。
著者の見解に依拠しつつ記せば、
戦後、新制大学体制が出発し、ベビーブームによる子どもの増加が続き、高度成長時代には学生数は順調に伸びていた。財政は安定しており、大学は経営上の危機意識がないまま、「経営」に真剣に取り組む必要性に迫られていなかった。そのため大学運営に一定の見識と経験を積んだ人びとが大学には少なかった。そして、大学の経営という観点より大学内部のさまざまな関係、それぞれの利益や特権の擁護が優先されてきた。さらに実務を担当する職員とその組織は未成熟で、人材養成面でも個人的、個別的な努力に依存することが多かった。
しかし、現在では大学に入学する人口がもはや増加することは望めず、数字上は志願者全員が大学への入学が可能となった。そして18歳人口が減少に転ずる「2018年問題」以降、大学間の入学志願者、入学者の獲得競争はいっそう激しくなり、全国の大学の4割以上で定員割れを起こすまでになっている。
これが現在の大学を取り巻く状況であり、わかりやすく言えば、さまざまな店はあるけれど客は少なくなって、これまでの運営方式を続けていたのでは店じまいに追い込まれる事態さえ起こりかねないところまで来ているのである。
本書が訴える要点はまさに発想の転換であり、意識の変革を大学に求めていると言えるだろう。資金を「管理」し、大学を「運営」する「管理運営」という方式は、すでに資金不足が生じてきているところもある現在の大学では通用しなくなっている。だからこそ著者は「経営」という視点をしっかり持ち、大学を「管理」することの重要性を説くのである。
そのために第Ⅰ章「大学の存在」では、大学とは何かを説き、第Ⅱ章「大学の理念と大学の歴史」では、私立大学には創設者の建学の精神があり、それを大学の教育理念として守ることの大切さを説いている。第Ⅲ章「経営管理の確立」では従来の大学運営方式では大学を取り巻く状況が変化しているだけに、大学経営での意識改革の必要性を説明している。そして第Ⅳ章から第Ⅵ章までは大学という組織がいかなるものかを一般企業とは異なる二重構造を含めて分析、解説をしている。この3つの章はみずからが大学生(短期大学生)だった人でもほとんど深く考えることはなかった点ではないかと思われる。第Ⅶ章「経営改革と組織運営の課題」は著者が「この本の中心課題の解明であり、最も力を尽くした章」と述べるように、国の文教政策に基づき、それをいかに大学改革、教育改革に結びつけ、加えて経営管理をどのように展開するべきかを記している。
著者が大学というものがどのような組織であり、その内部はどのようになっているのかその構造を執拗に明らかにし、解説しているのは、大学が教育機関であり、単純に利潤追求だけでは成り立たず、社会貢献や地域との協働といった一面も強く求められているからである。さらには教員という教育・研究を進める集団と経営を進める法人集団という二つの集団が二重構造の下で、大学という組織体を構成しているからでもある。
その上で、大学が生き残るためには何をなすべきか。著者は教育・研究の変革が重要であり、教員は大学としてどのような教育を進めるのか学長のリーダーシップのもと一丸となって取り組み、何よりも学生の立場、目線の重視を説いている。
また職能集団として職員を育て、教員と相互互助の形で大学の運営に関わり、専門職として自立した職員として経営に参画していくことの重要さも説いている。
おそらく危機意識を高めている大学では本書が説く方向ですでに検討、実践に取り組んでいるにちがいない。しかし、どれだけ達成できているのかとなるとやはりまだ道半ばであり、試行錯誤の真っただ中と言えるのではないだろうか。
本書を手にした大学生として大学生活を送った読者には本書の視点から再度、母校を、そして、ご自分の学生時代を振り返ってごらんになると、これまでとは違った母校の姿が見えてくるかもしれない。
最後に本書の末尾に「厳しい環境のなかで奮闘している教職員、法人役員、読者の皆さんへ」として、著者が大学の経営管理について七項目の提言にまとめている。是非ご一読いただきたいところである。
(やぐち・えいすけ)
バックナンバー→矢口英佑のナナメ読み