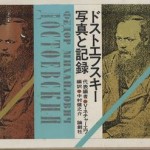- 2021-9-23
- お知らせ, 論創通信, 矢口英佑のナナメ読み
No.44『異邦人の歌 なかにし礼の<詩と真実>』
矢口英佑〈2021.9.23〉
「中西禮三」という人物のことをご存じですかと問われて即答できる人はそう多くないだろう。しかし、「なかにし礼」と聞けば、おそらく多くの日本人が作詞家として知られた、「ああ、あの人ね」となるにちがいない。
本書は一人の「中西禮三」がいかにして「なかにし礼」となり、いかにして昭和という時代を代表する作詞家となったのか、その出自から晩年までを著者・添田馨の目を通して論じられた〝なかにし礼評伝〟であり、同時に文学論、音楽論でもある。
なかにし礼が書き残したエッセー、自伝、小説、評論などを丁寧に読み込み、作詞という創作に行き着いたなかにし礼にとっての「作詞」とは何であったのか。さらには彼の小説の意味するものは何か。彼が考える音楽とは何かまで実に幅広く解き明かした優れた評論である。
一般的に作家や詩人には作品全集や選集といった形で後にまとめられて出版されることは珍しくない。言うまでもなく読者に作家や詩人の作品を一挙に、且つ簡便に読めるよう便宜を与えようとするからで、出版社の常套手段でもある。
しかし、「作詞家」と括られるとその「詞」が作品集としてまとめられ、出版されたという話はあまり聞かない。それは作詞家は作曲家と対になっていて、作詞と作曲が組み合わされ、さらに歌手がその歌を歌うことで完成形と見られるからだろう。確かに、多くの名詞を残したなかにし礼にしても、私のような音楽にはごく一般的な関心しか持たない者には、その詞だけで覚えているのではなく、作曲家が作った曲をある歌手が歌うことで一セットになって、はじめてその詞がごく自然に口をついて出てくるのが常だからである。
ただし作詞家は自分の詞にどのような曲がつけられるのか、作詞と作曲を自分の手で行なわない限りわからない。あるいは作詞家と作曲家が話し合いながら詞や曲が作られることもあるのだろう。だが多くは〝創る者〟の常として原初的には孤独な空間、時間のなかでその作業は始められると言っていい。
つまり、私たちが詞と曲と歌手の歌唱力とが一つになって一曲の歌としてその歌を聞き、自分の感性と結びつけて、時には涙さえ溢れさせて聞く世界とはまったく異なる世界が、その詞には込められていることを、なかにし礼は私たちに告げていたのである。
なかにし礼は多くの作詞家のなかでは異質の部類に入るだろう。みずからの思い(思想)を文字化させる手段を多く持つ作詞家だったからである。それは作詞だけでなく小説、評論、随筆、自伝と多岐にわたっていることからもわかる。
著者もこれらを有効な資料として大いに参考にして、なかにし礼に肉薄していく。この作詞家が発した多くの記述から核心となる言葉の抽出を試み、なかにし礼の骨の随に染み込んだ〝思想〟とも言うべき信念を明らかにしていく。その著者の着眼点に揺るぎはなく、筋道のつけ方、論理の展開はお見事と言うしかない。
その凝縮された言葉が本書の書名に見える「異邦人」にほかならない。
なぜ「異邦人」なのか。
なかにし礼は満洲(現中華人民共和国東北地域)で生まれ育った。満洲での何不自由ない生活は1945年の日本の敗戦によって暗転する。満州国が倒壊し、6歳の少年は死と隣り合わせの逃避行を体験しなければならなかった。日本を知らない日本人として日本へ追放された故郷喪失者となったのだった。日本人でありながら日本人でない〝よそ者〟意識と日本での疎外感覚が彼の思考方法に重大な影を落とすことになった。
なかにし礼は自伝的エッセイ『翔べ! わが想いよ』で満洲からの引き揚げ体験を「私の人生の核であり、私の感受性の中心部である」と記している(本書より)。
では「人生の核」から生み出されたものは何か。
平和への希求であり徹頭徹尾、戦争反対、軍国主義反対がそれだった。だからこそ2014年7月に安倍晋三政権が一方的な閣議決定で集団的自衛権の行使を容認し、憲法第9条の平和条項を骨抜きにした事実になかにし礼は「平和の申し子たちへ!」という激しい怒りと警鐘を打ち鳴らす詩を書くのである。
著者はこの詩を本書の冒頭に置き、「一読してまっさきに私にやってきたのは、とても居たたまれないような悲痛さの感覚と、取り返しようもない深い喪失感だった。私がこれまで知らなかったなかにし礼の姿が、そこにはあった(中略)これまでとはまったく相貌の異なる<闘う表現者>としてのイメージが、私のなかですっくと立ち上がったのだった」(本書「序章」)と記すのである。
著者が「平和の申し子たちへ!」を冒頭に置いたのは本書を著す衝動となったからにほかならない。だからこそなかにし礼の自分が作った歌詞の根っこには、すべて自分の戦争体験があったという言葉に鋭く感応し、なかにし礼の骨の随に染み込んだ〝思想〟になったと看破しているのである。
1967年、歌手黛ジュンンによって広く知られた『恋のハレルヤ』について語った、なかにし礼の言葉は著者が言うように「衝撃的な告白」になっている。
この歌からおよそ40年後になかにし礼は自分の戦争体験と向き合いながら歌謡曲を書いたと語り、「愛されたくて/愛したんじゃない/燃える想いを/あなたにぶっつけた だけなの」という『恋のハレルヤ』の歌詞に見える「あなた」は人間ではなく、日本、あるいは満洲であり、愛国心だといいきっているのである。
著者が言うように誰一人として想像し得なかった驚くべき「衝撃的な告白」だったのである。なかにし礼の作詞に込めた想いと受け手の私たちとの想いがもののみごとにかみ合っていない事実を知らされた私たちは、ある意味でなかにし礼の〝術中〟にいいようにはめられていたとも言えるのかもしれない。
著者はこの点について的確な分析をおこなっている。
「歌詞のモチーフが、一見したところ誰にも分かりやすい表の顔をもちながら、実はその裏側に隠れた別の顔をもっている――作詞家としてなかにし氏がとったこのような創作上の戦略を、ここでダブル・モチーフ戦略と呼ぶことにしたい(中略)受け手にとっては存在していないに等しいこの隠されたモチーフは、従って、それを編みだした作り手にとってのみ、重要な意味があるものだと考えられる」(第四章「歌謡曲と国家の影」)。
著者のなかにし礼に注がれる目は親しみに溢れ、なかにし礼を語る姿勢は、ひたむきに彼に近づき、寄り添い、かすかにしか聞こえない声にも耳を傾けようとしているかのようである。そうして感得したなかにし礼を著者は異邦人であり、平和憲法の擁護者であり、「闘う表現者」であったと断ずに至るのである。
かくして本書はなかにし礼を生み出した中西禮三という人物への人間賛歌となっているのである。
(やぐち・えいすけ)
バックナンバー→矢口英佑のナナメ読み