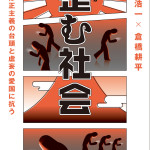- 2024-7-22
- お知らせ, 論創通信, 矢口英佑のナナメ読み
No.86『ネクスト・クエスチョン トランプのホワイトハウスで起きたこと』
矢口英佑
本書の原題は「I’LL TAKE YOUR QUESTIONS NOW WHAT I SAW AT THE TRUMP WHITE HOUSE」である。トランプ前アメリカ大統領が記者会見で質問を受ける際の常套句であり、前の質問者はもうそこまで、といった打ち切りのニュアンスが込められている。
副題は「トランプのホワイトハウスに見たものは」である。著者のステファニー・グリシャムは2017年3月にメラニアトランプ大統領夫人、すなわちファーストレディの広報部長に就任し、2019年から2020年までホワイトハウス報道官兼広報部長、その後はファーストレディ首席補佐官を歴任した経歴を持つ。
この経歴を見ればわかるように著者はトランプが大統領であった4年間、大統領としてのトランプとファーストレディの最も身近にいて、私生活にまで踏み込むこともあった濃厚な、しかも緊張した日々の連続であった時期の回想録である。
彼女は次のように言う。
「トランプ一家が政治活動に乗り出したほぼ当初から、私は彼らのそばにいた。政権中枢に最も近いところで大統領夫妻に同時に仕えたのは、歴史上私が唯一かもしれない。ほぼすべての休日をともに過ごし、一緒に世界中を飛び回った」
しかし、本書はトランプ大統領夫妻、およびトランプ大統領の4年間を高く評価し、またみずからの私生活を犠牲にした献身的な働きぶりを多少なりとも自負した内容ではない。
後悔と自責の念に捕らわれ、政治家としても人間としても見限ったトランプとその政権に留まっていた人びとの内情をぶちまけ、厳しく批判した決別の書にほかならない。
「本当にユニークで恐ろしく、奇妙で時におかしく、騒々しく狂気じみていて、そして時には悲劇的だった我が国の歴史の一時期を、私はつぶさに観察」するとともに、その仕事の役目上、「彼らのアドバイザーであり、手下であり、やかましい小言屋であり、噂話をする仲間であり、そして時には友人ですらあった−−−あるいは、自分にそう言い聞かせていた」のだった。
大統領夫妻にほぼ24時間仕え続けてきたと言っても過言ではない彼女が目にし、感じたことの多くが当事者たちの人間としての品格にも及んでいて、それらが本書でもののみごとに白日の下にさらされている。それだけに本書で取り上げられている人びと、とりわけトランプファミリーやトランプの取り巻きたちには、可能ならば刊行を阻止したかったに違いない危険な書物であることは疑いを入れない。
では、彼女はなぜ「時には友人ですらあった−−−あるいは自分にそう言い聞かせていた」などと記したのだろうか。
トランプ政権では発足からわずか7カ月足らずで大統領首席補佐官、国土安全保障長官、大統領報道官を交代させ、大統領広報部長に至っては3人目と目まぐるしく人事面での交代劇が起きていた。重要ポストのスタッフがいとも簡単に解任されていく現実を前にして、現在のポストに果たしていつまで留まっていられるのか、「どれだけ続くか」と思わずにいられない「自分」もいたからにほかならない。
大統領首席補佐官が3年間で4人目という常軌を逸した交代劇が繰り返される中で、
「私はようやく真相に気づいた———三年もかかったわけだ。つまり、トランプ、イヴァンカ、ジャレッドの三人(イヴァンカとは、トランプと前妻との間の娘であり、ジャレッドとは、ジャレッド・クシュナーでありイヴァンカの夫である。著者がこの二人を合わせて〝ジャヴァンカ〟、時には〝インターン〟と呼んだり、イヴァンカを〝お姫様〟などと呼んでこき下ろしている事象は本書に多く記されているが、著者がトランプ政権から常に排除したいと思っていた人物たちだった———筆者注)こそがホワイトハウスを牛耳っており、物事が失敗に終わっても責任をとることはない。支持率の急落、好ましくない報道、政策の混乱、大統領による約束の不履行、あるいは何らかのスキャンダルといった失策の責任は、常にスタッフが負わされるのだ。その解決策は、自分たちを失望させた当の人物、すなわち生け贄の排除であり、一時的には完璧な後任者がやって来る」
政権中枢部のスタッフはせいぜい見せしめや生け贄の対象でしかないことを確信した著者は「私は心のどこかで、マルバニー(3人目の大統領首席補佐官———筆者注)が去ったあと、自分が生け贄第二号にされるとわかっていた」とまで冷めた目で見るようになっていたのである。
結局、トランプ一家は「私は目的を果たすための手段に過ぎず、利用価値がなくなれば捨てるだけの存在」という行為をなんの躊躇もなく行える人びとに過ぎなかったのである。こうした認識を持たざるを得なかったことは、著者にはあまりにもむなしく、哀れで惨めな思いが襲ったであろうことは想像に難くない。しかし、だからこそ彼女は次のように断定するのである。
「本書を執筆したせいで、私はこれから色々な呼ばれ方をするだろう。裏切り者。下級スタッフ。弱虫。不正直者。無能。完全な人選ミス。(中略)大統領、そしておそらくファーストレディーは、私のことなどまるで知らないふりをするか、訴訟を起こすか、あるいはその両方を実行するだろう。そんなことはわかっている。真実を告げる決心をしたり、不正に対して立ち上がったりした他の全員に、私たちはそうしてきたのだから。私自身も多くの人たちにそんなことをした。それがトランプ流のやり方だからだ。輪の中にいればいいけれど、輪の外に出れば———否定され、破壊される。私自身がかつて破壊者だったのは、一種の報いと言えるだろう」
私が本書を好ましく思うのは、多くの暴露本に見受けられる強い思い込みと一面的な断定による対象者への批判と自己正当化だけで終始していない執筆姿勢が見られるからである。著者はトランプ政権時代にはみずからが加害者の立場で批判者や反対者を強引に排除してきた事実を客観的に見つめなおし、反省し、正直に認めているのである。
彼女はトランプ流がどのようなものであるのか知り尽くし、その実情に目を覆いたくなることも多々ありながら、敢えて「輪の外」に飛び出そうとせず、権力をバックにした心地良さに絡め取られていたのだった。
「自分はトランプの特別な側近だと考えるほど、自分のエゴが手のつけられないものになっていた」ことをとことん思い知ったからこそ、次のような自己批判も可能にさせていると言えるだろう。
「私の責任は明らかである。権力の虜に、そして自信過剰になっていた。ホワイトハウスという、私たちの国で、そしておそらく世界で最も重要な建物の中に入り、他のどんな場所とも違う扱いを受ける。アメリカ国民を支えたいと思ってホワイトハウスに入るものの、トランプ政権においては、そこを立ち去るまで初志を貫徹できた人は少ないし、私もそうできなかったことは間違いない」
さらにトランプのホワイトハウスで働いている限り、そこは生産的な仕事に専念することができず、誰もが相手を潰し、排除しようとする世界であり、だからこそ、
「ただ生き延びたいと願うのだ。生き延びるためなら何でも行ない、自分と、あるいは自分自身が納得していない倫理観と妥協する。私はそれについても有罪だった」
とみずからを断罪するのである。
彼女にトランプ政権の輪の外に飛び出す決定的な事件が起きた。議会議事堂襲撃事件である。2020年の大統領選挙でジョー・バイデンが次期大統領として選ばれたが、トランプは選挙に不正があったとして選挙無効を主張し続けていて、2021年1月6日は議会でバイデンの次期大統領就任が正式に確定する日だった。
数カ月にわたるトランプの数々の謀議に先導されて怒り、興奮した群衆が議事堂を襲撃している事実を彼女は「それは恐ろしく、気分が悪くなるほど悲しい光景」だったと記している。しかし、彼女はファーストレディーの主席補佐官として、すぐに暴力行為を終わらせ、人々を落ち着かせるために「平和的な抗議運動は全アメリカ人の権利だが、不法と暴力は許されない」とツイートを発信するよう提案した。だが大統領夫人の回答はたった一言「ノー」だった。
著者のステファニー・グリシャムにとって、大統領夫人の回答はあまりにも衝撃的だった。著者がこれまでも何らかの理由でホワイトハウスを去ろうとするたびに、ファーストレディーだけには「私が一番親しみを感じ」、いつも「何かにつけて守ってくれ」ていたため、辞任を思いとどまってきたのだった。だが、その期待は踏み躙られてしまったのである。
2021年1月6日、彼女はホワイトハウスを去った。一人の男性と一人の女性のために仕え、アメリカという国家のために貢献できなかったという深い後悔を残して。
本書の「エピローグ」で彼女はこのように記している
「私たちの党を支配する権力が一人の男によって独占されるのを、大勢の共和党員が許しているのを見るたび、私は悲しくなる。それは独裁制であって、この国はそんな思想の上に建国されたのではない。(中略)トランプ政権は優れた政策を数多く実施したと私は信じているし、それらが続くことを望んでいるけれど、いずれも共和党の政策であって、トランプの政策ではない。それらの政策は彼のものではなく、私たち共和党員は一丸となって前進するとともに、分裂を引き起こし、スキャンダルにまみれたトランプ時代のドラマと決別すべきだと、固く信じている」
2024年7月現在、アメリカ大統領選挙が再び近づいてきている。高齢が取り沙汰されている現大統領と狙撃された前大統領、共和党から大統領候補として正式指名を受けた前大統領。まだ民主党から正式指名を受けていないだけでなく出馬断念もあり得る現大統領。
このようなアメリカを著者のステファニー・グリシャムは今、どのように見ているのだろうか。
*このコラムはトランプ元大統領銃撃事件時に執筆されており、その時点での現状が反映されたものです。(編集部)