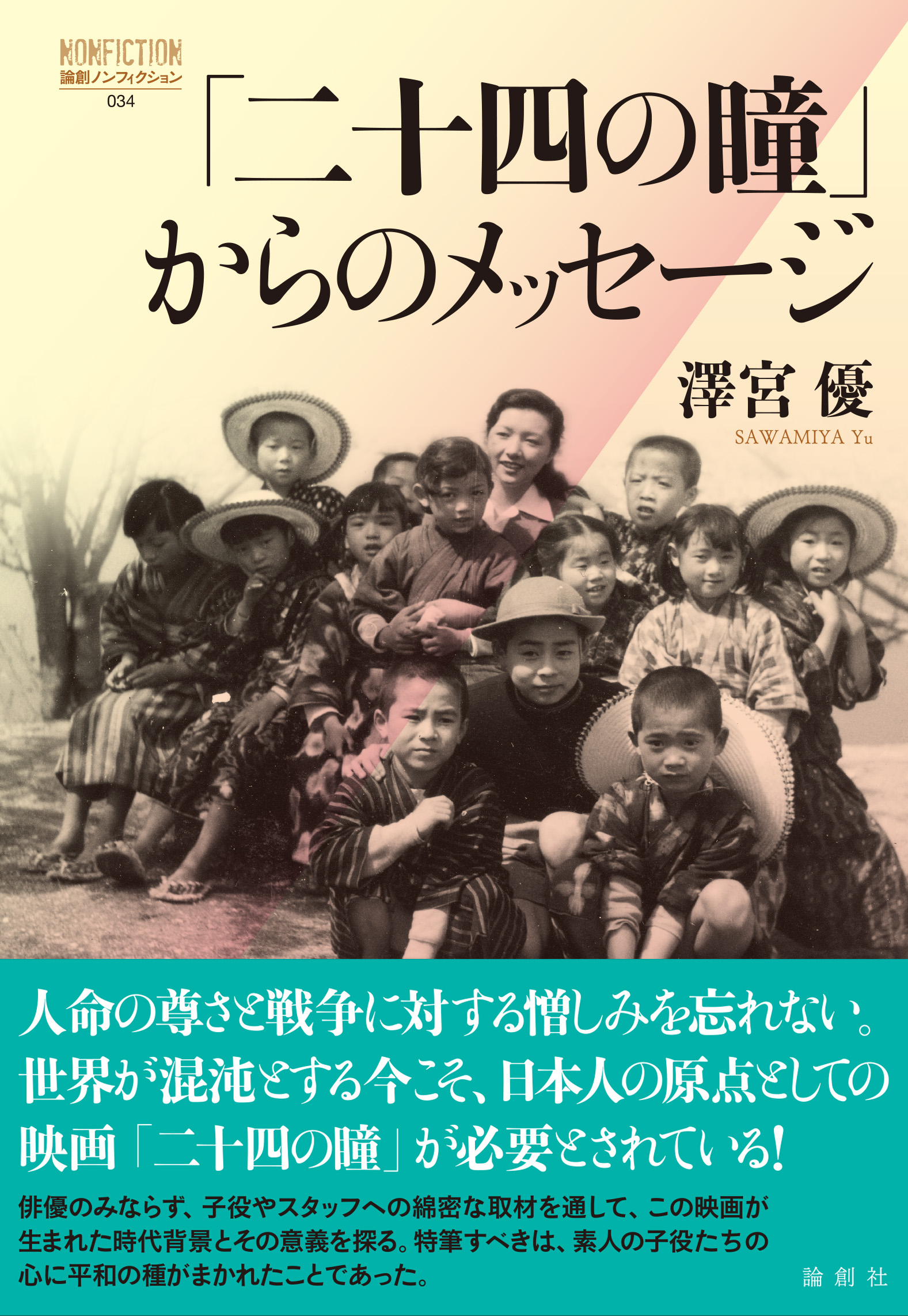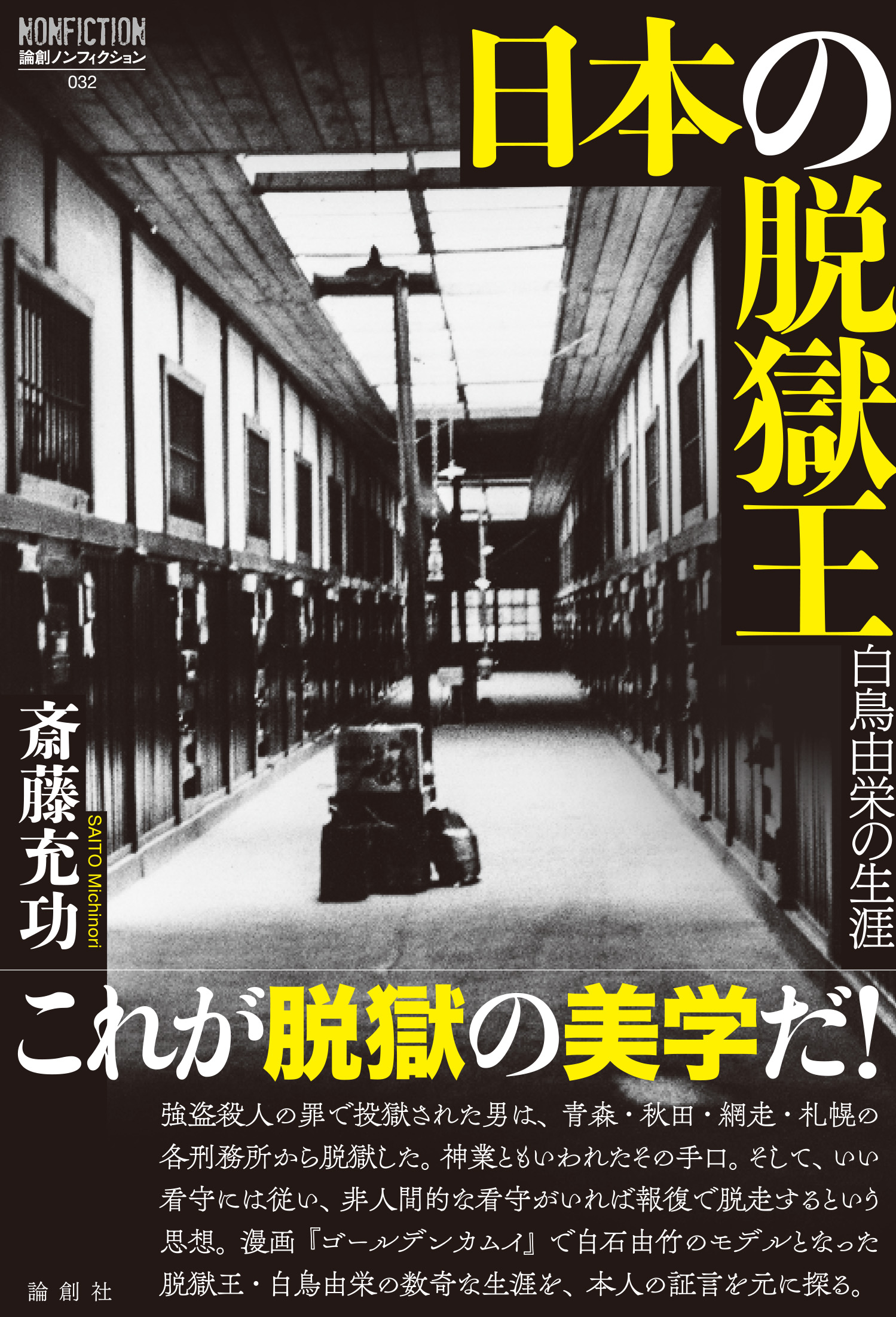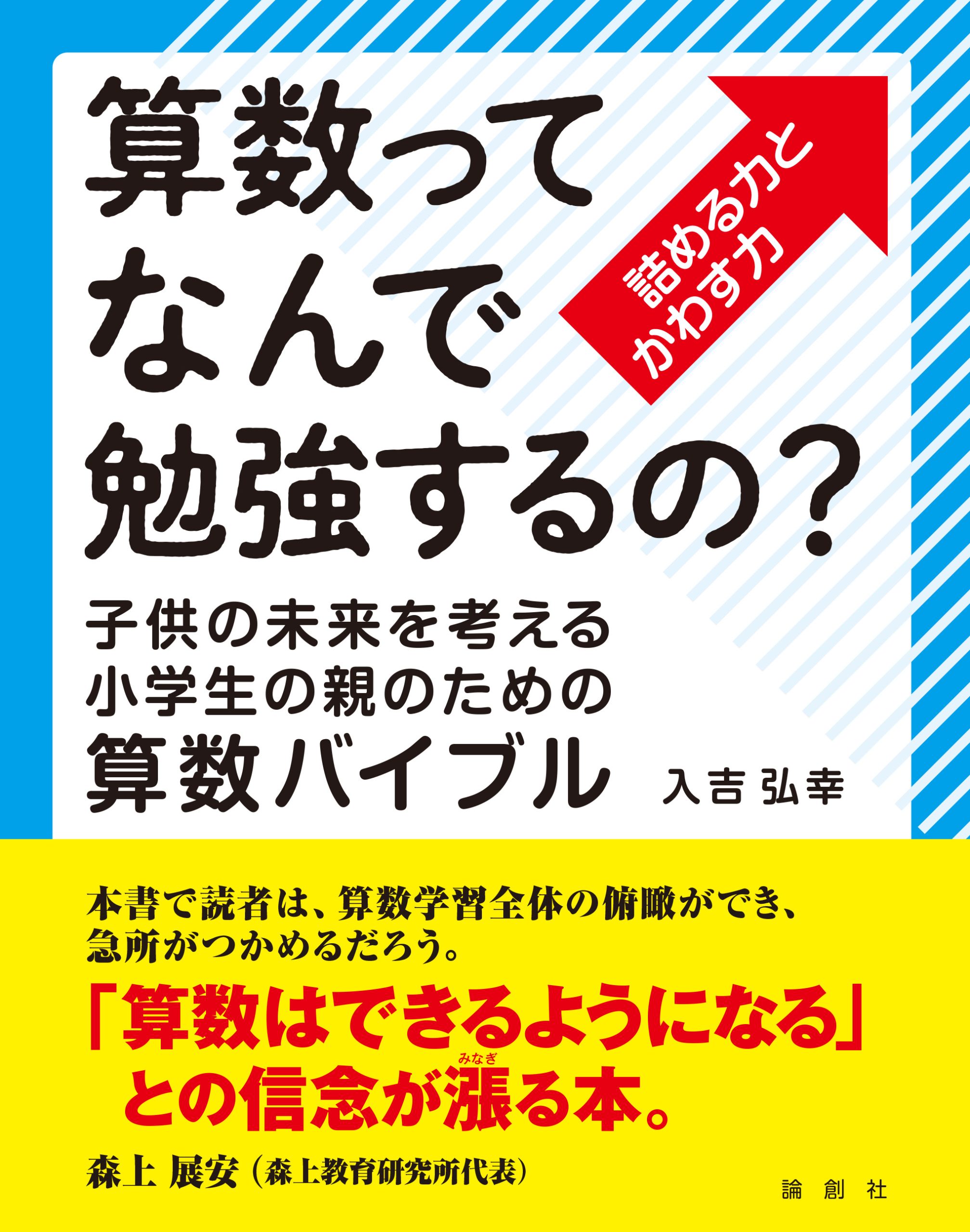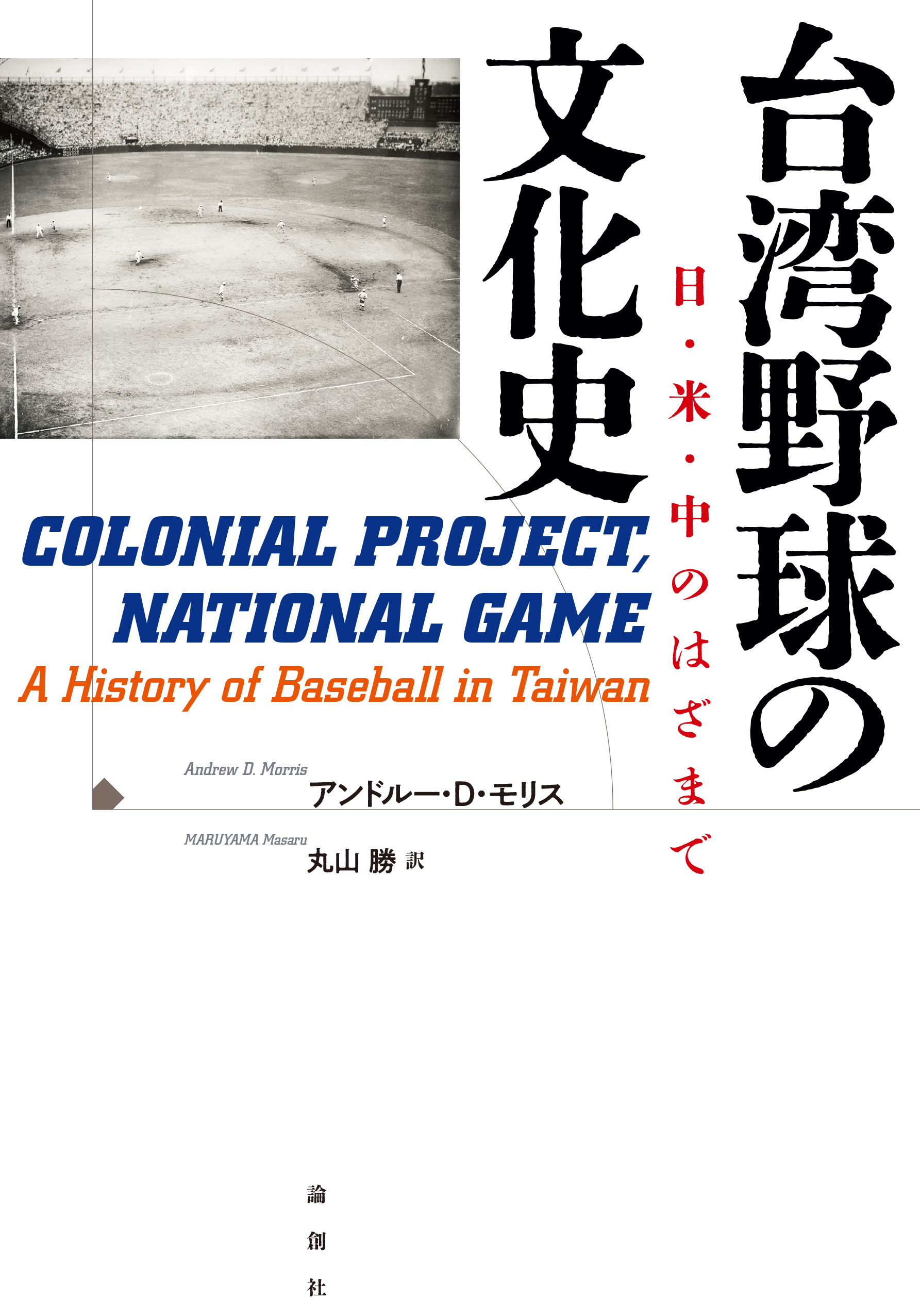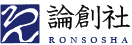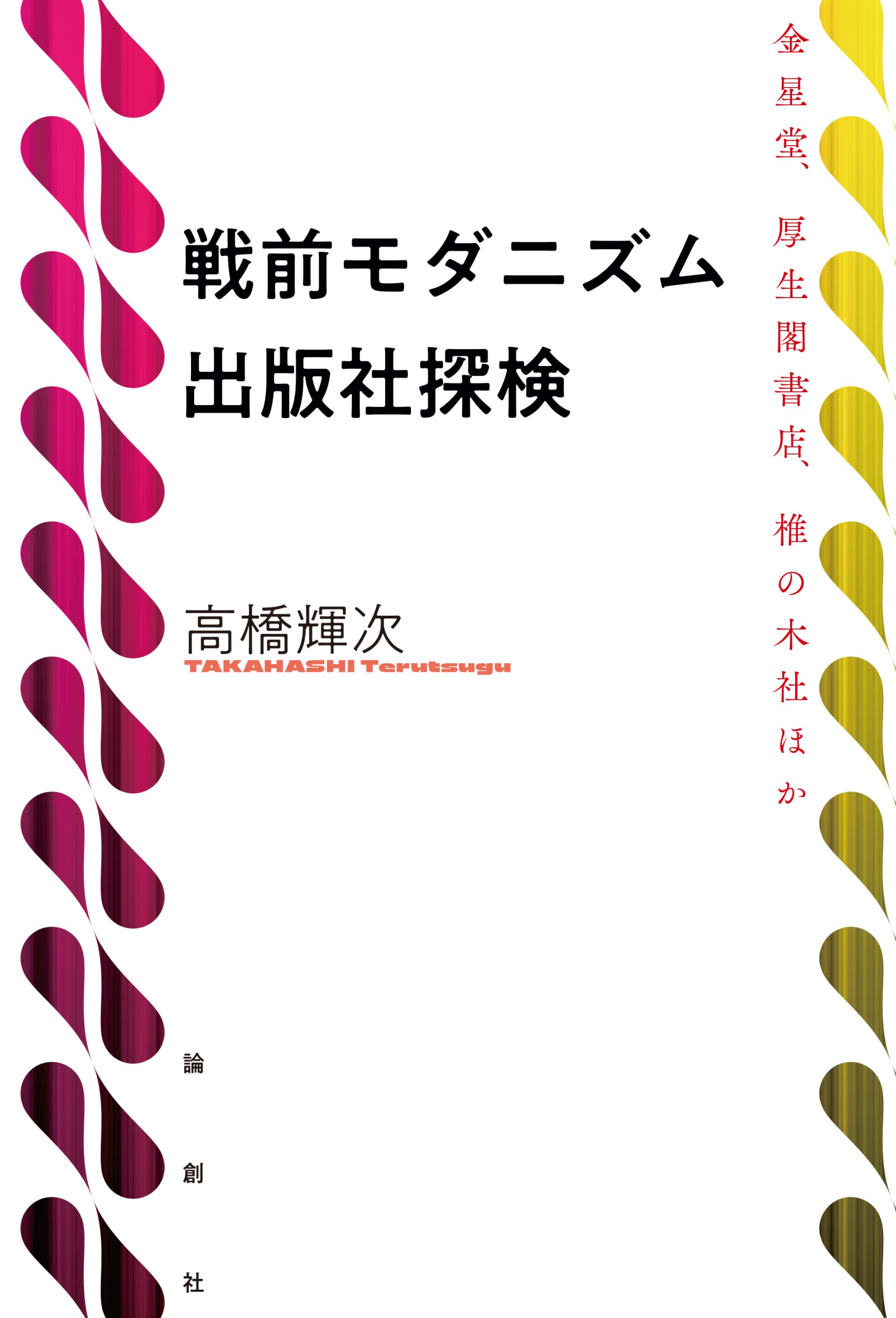
| タイトル | 戦前モダニズム出版社探検 |
|---|---|
| サブタイトル | 金星堂、厚生閣書店、椎の木社ほか |
| 刊行日 | 2024年11月08日 |
| 著者 | 高橋輝次 |
| 定価 | 3000円+税 |
| ISBN | 978-4-8460-2405-5 |
| Cコード | C0095 |
| ページ数 | 408 |
| 判型 | 四六 |
| 製本 | 並製 |
電子書籍はこちらから▼
内容
出版史のジャングルを探索する
大正末期から昭和初期にかけて、西欧の新しい文学・芸術思潮の影響を受けたモダニズム文学を支えた出版社と、その周辺を逍遥する古本エッセイ集。
大正末期から昭和初期にかけて、西欧の新しい文学・芸術思潮の影響を受けたモダニズム文学を支えた出版社と、その周辺を逍遥する古本エッセイ集。
著者紹介
高橋輝次(たかはし・てるつぐ)
元編集者。1946 年、三重県伊勢市に生まれ、神戸で育つ。大阪外国語大学英語科卒業後、一年間協和銀行勤務。1969 年に創元社に入社するも、1992 年には病気のために退社し、フリーの編集者となる。古本についての編著をなす。
主要著書『古書往来』(みずのわ出版)
『関西古本探検』(右文書院)
『古本が古本を呼ぶ』(青弓社)
『ぼくの創元社覚え書』(亀鳴屋)
『雑誌渉猟日録』(皓星社)
『編集者の生きた空間』(論創社)
『増補版 誤植読本』(ちくま文庫)アンソロジー
『タイトル読本』(左右社)
元編集者。1946 年、三重県伊勢市に生まれ、神戸で育つ。大阪外国語大学英語科卒業後、一年間協和銀行勤務。1969 年に創元社に入社するも、1992 年には病気のために退社し、フリーの編集者となる。古本についての編著をなす。
主要著書『古書往来』(みずのわ出版)
『関西古本探検』(右文書院)
『古本が古本を呼ぶ』(青弓社)
『ぼくの創元社覚え書』(亀鳴屋)
『雑誌渉猟日録』(皓星社)
『編集者の生きた空間』(論創社)
『増補版 誤植読本』(ちくま文庫)アンソロジー
『タイトル読本』(左右社)
目次
プロローグ
一 種村季弘の編集者時代―光文社での三年間を追って
二 森泉笙子『新宿の夜はキャラ色』を読む
―「バー・カヌー」の六年間を垣間見る
三 創元社(戦前の東京支店)のある編集者のこと―松村泰太郎の事蹟と小説から
四 創元社二代目社主、矢部文治遺稿集『本・三代』を読む
五 白鳥省吾童謡集『黄金のたんぽぽ』との出会い
―金星堂主人、福岡益雄と二人の編集者
六 「金星堂」余話―吉田一穂、亀山巌、伊藤整、川端康成ほか
1 伊藤整、町野静雄が編集部にいた!
2 吉田一穂『海の聖母』出版をめぐって―装幀者、亀山巌との微妙な関係を探る
3 紅野敏郎『大正期の文芸叢書』から
4 PR誌『金星』のこと
5 『金星堂ニュース』を見つける!
6 『小野幸吉画集』出版をめぐる話 2
7 福岡真寸夫句集『牡丹の芽』を読む
8 『伊豆の踊子』出版の周辺——吉田謙吉の装幀を中心に
七 曽根博義「厚生閣(書店)とモダニズム文学出版」を読む 2
―春山行夫の仕事を中心に
八 椎の木社と『椎の木』探索―百田宗治と同人の詩人たち 2
エピローグ︱田居尚『蘇春記』から
あとがき
一 種村季弘の編集者時代―光文社での三年間を追って
二 森泉笙子『新宿の夜はキャラ色』を読む
―「バー・カヌー」の六年間を垣間見る
三 創元社(戦前の東京支店)のある編集者のこと―松村泰太郎の事蹟と小説から
四 創元社二代目社主、矢部文治遺稿集『本・三代』を読む
五 白鳥省吾童謡集『黄金のたんぽぽ』との出会い
―金星堂主人、福岡益雄と二人の編集者
六 「金星堂」余話―吉田一穂、亀山巌、伊藤整、川端康成ほか
1 伊藤整、町野静雄が編集部にいた!
2 吉田一穂『海の聖母』出版をめぐって―装幀者、亀山巌との微妙な関係を探る
3 紅野敏郎『大正期の文芸叢書』から
4 PR誌『金星』のこと
5 『金星堂ニュース』を見つける!
6 『小野幸吉画集』出版をめぐる話 2
7 福岡真寸夫句集『牡丹の芽』を読む
8 『伊豆の踊子』出版の周辺——吉田謙吉の装幀を中心に
七 曽根博義「厚生閣(書店)とモダニズム文学出版」を読む 2
―春山行夫の仕事を中心に
八 椎の木社と『椎の木』探索―百田宗治と同人の詩人たち 2
エピローグ︱田居尚『蘇春記』から
あとがき
関連書籍